火事で家を解体するとき、どの補助金が使え、いくら支給され、どう申請すればよいかをこの記事で一気に把握できます。国土交通省の資料・通知に基づき、個別火災と大規模災害で異なる制度の位置づけ、国の支援と自治体補助・火災保険(共済)の役割分担、対象要件と対象外、支給上限や補助率、解体費用相場、必要書類と申請手順(事前申請・着工制限・交付決定・実績報告・精算)まで具体的に解説します。結論として、個別火災は原則「公費解体」の対象外ですが、危険度判定や空家等対策の除却補助、火災ごみ搬出助成で支援を受けられる可能性があります。多くは事前申請と罹災証明書が鍵で、保険金との重複受給に注意しつつ自己負担を最小化する実務ポイント(見積書・写真・図面、アスベスト・建設リサイクル法対応、近隣対策・道路占用、税務の基礎)まで網羅します。
Contents
1. 最初に結論 火事で家を解体する時に使える補助金の全体像

結論から言うと、火事後の解体費用を公的支援で軽減する道筋は「大規模災害時の公費解体」「通常時の自治体の除却補助」「火災保険・共済の活用」の三本柱で、起点は必ず市区町村窓口、根拠は国土交通省の枠組みに沿う自治体要綱です。
大規模災害に伴う多数の被災では、市区町村が国の交付金等を活用して実施する「被災危険家屋等解体撤去事業」により公費解体が行われるのが基本です。個別の火災(単独火災)では、老朽・危険度などの基準を満たす場合に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を背景とした除却補助や独自助成が使える可能性があります。また、火災保険や共済の保険金は生活再建の中心資金で、補助金算定時に重複受給調整(保険金控除)が行われる運用が多い点に注意が必要です。
共通の重要ポイントは、罹災証明書等の提出、事前申請と交付決定前着工の禁止、石綿(アスベスト)事前調査・法令届出の遵守です。
1.1 個別の火災と大規模災害で制度が大きく異なる
制度の入口は「災害スケール」で二分されます。地震・豪雨・大規模火災など多数被害が発生した場合は、倒壊の危険がある被災家屋を対象に市区町村が公費で撤去する枠組みが動きます。単独の火事では、原則は自己負担ですが、危険老朽家屋の除却補助や火災ごみ搬出助成など自治体独自制度の活用余地があります。いずれも自治体の危険度判定や要綱に即した運用が前提です。
| 比較項目 | 個別の火災(単独火災) | 大規模災害時(多数被災) |
|---|---|---|
| 費用の原則 | 原則自己負担。自治体の老朽危険家屋除却補助や火災ごみ助成があれば一部補助。 | 市区町村による公費解体が基本。対象は倒壊の恐れがある被災危険家屋等。 |
| 主な根拠 | 空家等対策の推進に関する特別措置法、自治体要綱(除却補助・助成)。 | 国土交通省の枠組みに沿った「被災危険家屋等解体撤去事業」等による自治体実施。 |
| 必要書類の要点 | 罹災証明書や現況写真、見積書、所有・同意関係書類等。 | 罹災証明書、危険度判定、所有者同意書等。 |
| 申請・同意 | 所有者による補助申請(交付決定前の着工不可)。 | 自治体の実施に対する所有者同意が必要。 |
| 法令対応 | 建設リサイクル法届出(規模要件該当時)、大気汚染防止法の石綿事前調査・届出。 | 同左(自治体が手続を支援・実施する場合あり)。 |
| 対象範囲の違い | 対象経費は要綱次第(付帯工・残置物処分は対象外が多い)。 | 災害廃棄物の撤去が公費対象。基礎や地中障害物の扱いは自治体基準。 |
1.2 国の補助と自治体の補助と民間保険の役割分担
実務では、国は交付金等で自治体事業を下支えし、自治体が住民向け制度を設計・実施します。民間の火災保険・共済は損害に応じて支払われ、解体費や再建費に充当されます。三者の役割が噛み合うことで、被災後の安全確保と生活再建が進みます。
| 主体 | 代表的な制度・資金 | 主な役割 | 補助率・上限額の扱い | 申請先・起点 |
|---|---|---|---|---|
| 国(国土交通省等) | 被災危険家屋等解体撤去事業の財政支援、空家等対策推進交付金など。 | 自治体事業を財政・技術面で支援し、手引き・通知で運用基準を示す。 | 住民個人への直接給付ではなく、自治体の実施経費を支援。 | 国への個人申請は不可。自治体制度を通じて活用。 |
| 自治体(市区町村) | 公費解体の実施、老朽危険家屋除却補助、火災ごみ搬出助成 等。 | 窓口・審査・危険度判定・交付決定・精算までの実施主体。 | 上限額・補助率は自治体要綱で設定(例:上限額は各自治体が設定、保険金等は控除して算定する運用が多い)。 | 市区町村の担当課に事前相談し、必要書類を整えて申請。 |
| 民間(火災保険・共済) | 建物・家財の火災保険、共済金。 | 損害額に応じた保険金で生活再建を支援。解体・撤去費用特約がある場合も。 | 契約条件に従い支払。公的補助の対象経費から控除される場合がある。 | 加入先の保険会社・共済組合に事故連絡・請求。 |
出発点は自治体窓口での事前相談と制度選択、次に保険金の見込みを踏まえた補助額試算、そして交付決定後に解体契約・着工という順番を厳守することが、支援を最大化する最短ルートです。
1.3 火事 解体 補助金の対象になる基本要件
対象建物は、火災で全焼・半焼・部分焼となり、倒壊・延焼などの危険があるため解体が必要と自治体が認める住宅や付属建物が中心です。空き家の場合でも、危険性が高い「特定空家等」の要件に該当するなど、自治体基準を満たすことが求められます。用途・構造・規模により対象外や優先度の違いが生じることがあります。
申請者は原則として所有者(相続人・管理者を含む)で、共有名義は全員の同意が必要です。反社会的勢力排除の誓約、税公課の納付状況等に関する要件が設けられることがあります。公費解体や補助に際しては所有権・占有の確認が不可欠です。
必要書類の基本は、火災被害の程度を示す罹災証明書(または被災証明書)、建物の登記事項証明書や固定資産課税台帳の写し、現況写真、解体工事見積書、平面図・配置図・延床面積のわかる資料、所有者・同意関係書類です。加えて、大気汚染防止法に基づく石綿事前調査の結果、必要に応じた届出書、建設リサイクル法の届出(解体が延べ床面積80平方メートル以上などの規模要件に該当する場合)の写しを求められるのが一般的です。
対象経費は、解体工事費、仮設足場・養生、分別・運搬・処分などの産業廃棄物処理費、アスベストの飛散防止対策・除去に関する費用などが中心ですが、範囲は自治体要綱で異なります。家庭の残置物処分や整地・舗装・更地管理費、任意の外構撤去、測量・登記等は対象外となることが少なくありません。大規模災害の公費解体では災害廃棄物の撤去が公費対象となる一方、基礎や地中障害物の扱いは自治体の基準に従います。
手続の原則は、事前相談→申請→審査→交付決定→契約・着工→実績報告→精算・交付請求という流れで、交付決定前の着工は原則として補助対象外です。解体業者の見積りは、分別項目やアスベスト対応の内訳が明確なものを用意し、必要に応じて相見積もりで妥当性を示します。
法令遵守は必須です。建設リサイクル法に基づく事前届出(解体工事で延べ床面積80平方メートル以上等の規模要件に該当する場合)と、大気汚染防止法に基づく石綿含有建材の事前調査・結果の掲示・届出を確実に行い、飛散防止措置やマニフェスト管理まで一体で管理することが求められます。
2. 国土交通省資料で確認できる制度の位置づけ

この章では、火災により家屋を解体する局面で関わる制度を、国土交通省が公表する手引き・通知・ガイドラインで整理できる範囲に限定して位置づけます。対象は主に「大規模災害時の公費解体」「空家等対策に基づく除却支援」「解体工事に必須の法令手続(建設リサイクル法・大気汚染防止法)」です。個別の火災(単独火災)と、災害救助法の適用等を伴う大規模災害では制度の入口と費用の持ち方が根本的に異なる点をまず押さえてください。
| 制度・根拠 | 想定する災害/場面 | 主な対象 | 実施主体 | 経費の扱い(概要) | 所有者の位置づけ |
|---|---|---|---|---|---|
| 被災危険家屋等解体撤去事業 | 災害救助法適用等の大規模災害 | 倒壊等の危険がある被災家屋の解体・撤去 | 市区町村(国の補助対象事業) | 自治体事業費に国が補助。所有者負担は自治体要綱により取り扱い | 同意・申請が必要。私有財産原則の例外として公費解体を容認 |
| 空家等対策の推進に関する特別措置法 | 平時の危険空家対策(火災で荒廃・放置された空家含む) | 特定空家等の除却・適切な管理 | 市区町村(国交省の交付金を活用) | 交付金を原資に自治体が補助制度を設計(上限・対象経費は各自治体) | 所有者責務が原則。補助は公助による支援の位置づけ |
| 建設リサイクル法 | 全ての解体工事(火災の有無を問わない) | 分別解体、事前届出(一定規模以上) | 発注者・元請業者(届出先は市区町村等) | 届出・分別解体・再資源化等は法令遵守事項(補助の前提) | 発注者は届出義務者。適合していないと補助対象外になり得る |
| 大気汚染防止法(石綿) | 全ての解体・改修工事 | 石綿事前調査、届出、飛散防止措置 | 元請業者(届出先は都道府県等) | 調査・届出・作業基準の遵守は法令義務(違反は罰則) | 所有者は調査に必要な情報提供・立入の協力が求められる |
2.1 被災危険家屋等解体撤去事業の全体像
被災危険家屋等解体撤去事業は、地震・台風・豪雨等の大規模災害に伴い倒壊・崩落の危険がある家屋を、市区町村が公費で解体・撤去する枠組みです。国は自治体の実施経費を補助し、私有財産であっても二次災害防止・生活再建の観点から公的介入を可能にします。個別の火災のみの場合は対象外であるのが通常で、災害救助法の適用や自治体の実施方針が前提になります。
実施にあたっては、罹災証明書、危険度判定、所有者の同意を確認したうえで、自治体が設計・積算・入札・施工・産業廃棄物処理・実績報告までを一貫して行います。所有者が先に自己負担で解体着手した場合、公費解体の対象外になる運用が一般的なため、事前相談が欠かせません。
2.1.1 公費解体の対象となる危険度判定と適用範囲
対象判定は、建築物の応急危険度判定等の枠組みや自治体による現地調査結果に基づきます。典型的には、次のような要素が総合的に勘案されます。
- 外壁・躯体の損傷が著しく、倒壊・崩落・落下物の危険が高いこと
- 道路・隣接地を占用し、避難・復旧活動を阻害するおそれがあること
- 火災・浸水等により内部立入が困難で、速やかな除却が安全上必要であること
加えて、私有財産に対する公的関与の原則整理として、所有者の同意、関係権利者の調整、立木・附属物を含む範囲の明確化が求められます。境界確定や敷地内残置物(家財等)の扱いは自治体要綱で定められ、対象・対象外の線引きが行われます。
2.1.2 費用負担と補助率の目安と自治体実施の流れ
費用は「調査・設計・積算」「解体工事(足場・養生含む)」「運搬・処分(災害廃棄物)」「現場管理・安全対策」等で構成され、国の補助対象は自治体が実施する事業費です。所有者負担の有無・範囲(例えば庭木や工作物の扱い等)は各自治体の実施要綱で定められます。
| 段階 | 主な内容 | 関与する書類・根拠 |
|---|---|---|
| 1. 事前受付 | 所有者からの申請・同意取得、権利関係確認 | 罹災証明書、同意書、本人確認資料 |
| 2. 対象判定 | 危険度判定・現地調査、対象範囲の特定 | 応急危険度判定結果、現況写真・図面 |
| 3. 設計・積算 | 工法・仮設・運搬経路の計画、数量算出 | 積算書、工程表、安全計画 |
| 4. 発注・施工 | 入札・契約、解体、分別・搬出、処分 | 契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト) |
| 5. 完了・精算 | 出来高確認、実績報告、国の補助交付手続 | 実績報告書、検査調書、写真台帳 |
公費解体の可否・範囲・自己負担の有無は、災害の指定と自治体要綱により確定するため、告示・要綱・手引きの公開内容を必ず確認しましょう。
2.2 空家等対策の推進に関する特別措置法と除却補助
空家等対策の推進に関する特別措置法は、倒壊等の危険がある空家等(特定空家等)への措置や、適切な管理を促すための枠組みを定めています。国土交通省は自治体の取り組みを支援するための交付金を整備しており、自治体は交付金を原資に、老朽・危険空家の除却費を助成する制度を設けることができます。
火災によって居住不能となり、その後放置された空家が周辺に危険・衛生上の支障を与える場合、自治体が定める基準に適合すれば除却補助の対象になり得ます。一方、生活再建のための個別火災直後の解体費は、本法の補助対象と直結しないのが一般的で、自治体の空家定義・認定手続に従った判定が必要です。
2.2.1 国土交通省の空家等対策推進交付金の活用ポイント
空家等対策推進交付金は、自治体が実施する「除却補助」「適正管理の指導・代執行」「地域活用」の各メニューを支える交付金です。除却補助に関しては、自治体が対象要件(危険度、周辺影響、管理不全の程度等)、対象経費(解体工事費、仮設・養生、廃棄物処分費等)、上限額や補助率を要綱で規定します。
したがって、同じ“空家除却補助”でも自治体ごとに上限額・自己負担・対象範囲が異なる点に注意が必要です。申請前に自治体の要綱・手引き・申請書式を確認し、事前相談で対象判定と必要書類(所有権確認、現況写真、見積書、近隣同意等)をすり合わせてください。
2.3 建設リサイクル法に基づく解体工事の届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、解体工事で発生する特定建設資材(コンクリート、コンクリート・アスファルト、木材など)の分別解体・再資源化等を義務づけています。延べ床面積が一定以上(建築物の解体は80平方メートル超)となる工事は、着工前に届出が必要です。
届出は原則として発注者が行い、工期や工法、再資源化の方法等を記載します。元請業者は分別解体や再資源化等の実施、現場標識の掲示、記録の作成・保存などの義務を負います。補助金の交付要件として、建設リサイクル法に適合していることが求められるのが通例であり、未届出や分別不備は対象外・減額のリスクになります。
2.4 大気汚染防止法と石綿事前調査の義務
大気汚染防止法では、解体・改修工事の際の石綿(アスベスト)飛散防止のため、工事前に有資格者による石綿含有建材の事前調査を実施し、その結果に応じて届出・作業基準を遵守することが義務づけられています。事前調査は全ての解体・改修工事で必要で、結果の記録・保存が求められます。
特定粉じん排出等作業に該当する場合は、工事開始の少なくとも14日前までに所管自治体(都道府県等)へ届出し、隔離養生、負圧集じん、湿潤化、適切な保護具の使用などの作業基準に従います。違反には罰則が設けられており、補助金の交付対象であっても、石綿規制の不適合が判明すれば交付取消・減額等のリスクがあります。工事発注前に、調査者資格・届出・作業計画の整合を必ず確認してください。
3. 自治体の補助金で対象になるケースを整理

自治体の解体関連の補助・助成は、交付要綱や運用で差が大きく、火災に起因する除却が常に対象になるわけではありません。対象になり得るのは、制度の目的(安全確保、生活再建、良好な住環境の回復など)に合致し、現地の危険性や管理不全の度合いが要件を満たすケースです。火事が原因でも、制度趣旨と要件に適合し、事前申請と交付決定を経てから着工することが前提になります。
| 制度類型 | 根拠・位置づけ | 火災家屋の対象化の考え方 | 主な条件 | 対象経費の例 |
|---|---|---|---|---|
| 老朽危険家屋除却補助 | 自治体の交付要綱(空家等対策、建築安全、景観・防災など) | 火災で損壊し倒壊・落下等の危険が顕著な場合に、老朽危険家屋と同視して対象化されることがある | 所有者の同意、現地調査の危険度判定、事前申請、解体工事の法令遵守、重複受給の回避 | 本体解体、足場・養生、仮設工、残置物撤去の一部、運搬・処分費、発生土処理など(要綱の対象経費に限定) |
| 特定空家等除却補助 | 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく運用 | 火災後に管理不全が著しく、特定空家等相当と判断される場合に支援対象となることがある | 特定空家等の認定または同程度の状態、近隣への危険・著しい景観悪化、是正指導の履行、事前協議 | 除却工事費、付帯工事の一部、搬出・処分費(自治体の基準内) |
| 地区指定型(木密対策・防災まちづくり) | 防災市街地整備や木造密集地域の独自メニュー | 延焼危険性の高い区域で、街区の防災性向上の観点から火災後の除却を後押し | 対象区域内、配置・敷地条件の適合、隣地協議、まちづくり方針との整合 | 除却費、塀・工作物の除却、セットバック関連の付帯費 |
| り災者支援(処分費・手数料減免) | 清掃・環境部門の減免要綱 | 火災で発生した「災害廃棄物」相当の搬出・処分について、手数料の免除・減額や臨時収集で支援 | 罹災を証する書類の提示、事前申請、分別・搬入ルールの遵守、アスベスト等の除外品目への対応 | 粗大ごみ手数料、臨時収集の運搬・処分、清掃工場への持込手数料など(対象と上限は自治体の定めによる) |
3.1 老朽危険家屋除却補助の火災適用の可否
老朽危険家屋除却補助は、地域の安全性確保や良好な住環境の回復を目的とするため、火災による損壊が著しく、倒壊・落下・延焼の危険があると自治体が判断する場合に、対象となる余地があります。判断材料は、現地確認による危険度判定、周辺道路・隣接地への影響、焼失後の管理状況(無管理での散乱・臭気・害虫等)などです。
火災保険や共済で除却費用を充当する場合は、自治体補助と重複受給にならないよう精算方法の確認が必須です。一般に、交付要綱は「他の補助・給付・保険金等と同一経費の二重受給禁止」を定めています。保険会社への見積内訳提示や、自治体への収支内訳の提出で整合を図ります。
また、事前申請・交付決定前の着工は対象外になるのが通例です。所有者要件(共有名義・相続未了時の同意、滞納等に関する条項、暴力団排除条項)、解体業者の許可・登録、石綿事前調査の実施・届出など、申請時に満たすべき条件を確認してください。
3.2 火災ごみの搬出処分費助成と手続き
火災で発生した廃材・家具・家電・焼け殻等は、自治体により「災害廃棄物」や「り災ごみ」として手数料の免除・減額、臨時の収集・持込受付を行う場合があります。対象・上限・期間は自治体で異なりますが、以下の流れが一般的です。
まず、清掃・環境部門の窓口で事前相談し、罹災を証する書類を提示して申請します。持込の場合は搬入先(清掃工場・環境事業所)の指定と日時の予約、収集の場合は分別・集積場所・立会い方法が案内されます。アスベスト含有建材、消火器、バッテリー等の危険物は別途の取り扱いとなるため、解体業者の産業廃棄物処理ルートを使うのが原則です。
処分費助成は「生活再建支援」としての位置づけであり、建物の解体工事費そのものの補助とは区別されます。解体補助と併用する場合は、対象経費の重複がないように領収書・マニフェスト・搬入伝票を分けて管理します。店舗併用住宅など事業系廃棄物が混在するケースでは、事業分は減免対象外となる取扱いが多いため注意が必要です。
3.3 罹災証明書と被災証明書の違いと使い分け
火災関連の申請で求められる証明書は複数の名称があり、用途と発行機関が異なります。自治体補助の申請要領が「どの証明で代替可能か」を明記していることが多いので、名称ではなく求められる記載内容で確認するのが実務上の要点です。
| 書類名 | 発行機関 | 主な用途 | 記載内容の傾向 | 補助金申請での使い方 |
|---|---|---|---|---|
| り災届出証明書・火災発生証明等 | 消防機関 | 火災の発生事実の証明、保険会社への提出など | 発生日時・場所、出火概要、届出の事実 | 火災の事実確認として求められることがある |
| 罹災証明書 | 市区町村 | 住家等の被害程度の証明、減免・支援制度の申請 | 住家被害の分類、住所、世帯情報等 | 除却補助や処分費減免の根拠資料として指定される場合がある |
| 被災証明書 | 市区町村 | 災害に遭った事実の証明(被災期間・居住実態等) | 被災の事実、期間、所在地、申請者情報 | 罹災証明の代替として認める運用がある(要項目の適合が条件) |
解体補助の審査では、証明書に加えて、現況写真、見取図・位置図、固定資産課税台帳の写し、登記事項証明書などで所有・対象建物の同一性を担保します。共有名義や相続登記未了の場合は、全員の同意書や委任状が求められるのが一般的です。
3.4 主要自治体の制度の比較ポイント
制度ごとの差異は、対象建築物の範囲(住家限定か、附属建物・工作物を含むか)、危険度の定義、対象経費(付帯工事・仮設費・残置物撤去の扱い)、上限額の設定方法(定額・定率・面積連動)、採択方式(先着・審査・予算枠)、事前申請の厳格度、解体後の土地利用(更地管理)の要件などに現れます。
特に、着工制限と重複受給の考え方、石綿事前調査・届出の提出要否、事業系混在時の按分ルールは、自治体で明確なローカルルールがあるため、要綱・要領・Q&Aで必ず確認してください。相見積もりの取り扱い(件数・様式)や、標準単価表・数量算定基準を公表している自治体もあります。
3.4.1 東京23区に多いメニューの傾向
東京23区では、空家等対策や木造密集地域の防災を背景に、老朽危険家屋・特定空家等の除却補助、地区指定型の防災まちづくりメニュー、り災者支援としての粗大ごみ手数料の免除・減額といった施策が組み合わさる傾向があります。区域指定がある場合は、道路後退(セットバック)や塀・擁壁等の除却も対象範囲に含める運用がみられます。
申請面では、オンライン・郵送と窓口の併用、写真・図面の様式指定、石綿含有建材の事前調査結果の添付、近隣周知の実施記録など、書類の整合性を重視する運用が一般的です。清掃工場への持込は予約制・分別厳格化の運用が多く、り災時の臨時受入れでも品目制限が明確に示されます。
3.4.2 政令指定都市の運用の傾向
政令指定都市では、建築安全や住宅政策と清掃・環境部門の連携が進み、除却補助と災害廃棄物の減免をワンストップで案内する体制が整備されている例がみられます。解体工事費の査定では、数量積算や標準歩掛のガイドを提示して透明性を高める運用が採られることがあります。
また、石綿(アスベスト)対策と大気汚染防止法に基づく手続きの徹底、建設リサイクル法の届出・適合解体の指導、マニフェストの適正管理確認など、コンプライアンス面のチェックが厳格です。り災証明の取得から交付決定、実績報告までのスケジュール感も明確化される傾向があり、交付決定前の契約・着工を避け、証拠書類(見積書・契約書・マニフェスト・帳票類)を適切に分けて保管する実務が求められます。
4. 補助金の対象と対象外の判定ポイント

火災後の解体に関する補助対象は、制度(公費解体、老朽危険家屋除却補助、災害時の被災家屋解体支援など)ごとに要件が定められています。判定の基本は、罹災証明書などの公的な被害区分と、倒壊等の危険性や生活環境上の支障の有無、そして解体工事に不可欠な費用かどうかという「必要性・相当性」の観点です。以下では、対象・対象外を見極めるうえでの実務的な基準を整理します。
4.1 全焼 半焼 部分焼での取り扱いの違い
火災の被害程度は、自治体が交付する罹災証明書の区分(例:全焼・半焼・一部焼)により整理され、解体補助の判定にも活用されます。全焼で安全性を著しく損なっている場合は対象となる可能性が高く、半焼・部分焼でも倒壊や延焼の危険、生活環境の悪化(悪臭・すす・害虫等)の要因が認められると対象となるケースがあります。一方、補修で安全が確保できると判断される場合や、居住性・構造安全性の回復が可能な場合は対象外とされるのが一般的です。
| 被害区分 | 判定の主な根拠 | 補助対象となりやすい条件 | 対象外となりやすい例 |
|---|---|---|---|
| 全焼 | 罹災証明書(全焼)/現地危険度確認 | 構造材の大部分が焼失し、倒壊等の危険が明白、居住継続不能 | 用地再整備のための任意解体のみを目的とする場合 |
| 半焼 | 罹災証明書(半焼)/建物診断 | 主要構造部の損傷で安全性が確保できず、修繕より解体が合理的 | 限定的補修で安全確保が可能と確認された場合 |
| 部分焼 | 罹災証明書(一部焼)/危険箇所の特定 | 焼損により全体の安定性が低下、延焼・落下物の危険、衛生上の支障 | 焼損部の部分補修・清掃で機能回復が見込める場合 |
いずれの区分でも、「所有者の任意・利便のための解体」か「公共性・安全性に資する解体」かが判断の分岐点となります。判定には、現地調査結果、写真、見積書の内訳、被災状況の説明資料を整えることが重要です。
4.2 付帯工事の対象例 仮設費 養生費 残置物撤去
補助対象は「解体本体工事」に加え、工事の安全・適正実施に不可欠な付帯工事や費用を含むのが一般的です。ただし、範囲と上限は制度ごとに異なり、豪華・過剰な仕様は対象外となります。
| 項目 | 原則的な扱い | 留意点(必要性・相当性) |
|---|---|---|
| 足場・養生(飛散防止シート等) | 対象になりやすい | 近隣保全・安全対策として必須。過剰な仮設規模や高級仕様は不可。 |
| 仮設電気・仮設水道 | 対象になりやすい | 解体作業に必要な範囲に限定。現場外の設備更新費は不可。 |
| 交通誘導・近隣対策 | 対象になりやすい | 狭隘道路や通学路等での安全確保に必要な範囲。 |
| 産業廃棄物の分別・運搬・処分 | 対象になりやすい | 法令に基づく適正処理が前提。マニフェスト交付等の実費を含む。 |
| アスベスト事前調査・除去 | 対象になることがある | 大気汚染防止法に基づく義務。調査区分・除去工法は法令適合が必須。 |
| 残置物撤去(家財・可燃物) | 対象になることがある | 災害により発生した廃棄物の処理は対象となる場合あり。通常の片付け費は不可。 |
| 仮囲い・防犯対策 | 対象になることがある | 工事期間中の安全確保に必要な最小限度に限る。 |
| 設計・監理・書類作成 | 対象外になりやすい | 申請代行費や一般的なコンサル費は対象外の取扱いが多い。 |
| 再建に関する費用 | 対象外 | 新築設計、地盤改良、建材購入等は不可。 |
残置物は、「災害(火災)に起因して発生した廃棄物」か「日常的な家財処分」かが判定の鍵です。前者は対象となる場合がある一方、後者は対象外の取扱いが一般的です。見積書の品目・数量・単価の明確化、写真による焼損・汚損の確認が有効です。
4.3 基礎 ブロック塀 井戸 樹木 地中障害の扱い
建物に付随する工作物・附属設備の取り扱いは、安全性の回復や解体の完遂に必要かどうかで判断されます。敷地外や他人地に属するもの、再整備を目的とした撤去は対象外となりがちです。
| 対象物 | 原則取扱い | 対象となる条件の例 | 対象外となる例 |
|---|---|---|---|
| 建物基礎・土間コンクリート | 対象になりやすい | 建物解体の完了に必要、突出による危険除去 | 必要以上の深度の撤去、再建用の造成を兼ねた工事 |
| ブロック塀・門柱・フェンス | 対象になることがある | 火災で損傷し倒壊危険がある、解体作業上撤去が不可欠 | 美観目的の全面更新、新設を前提とした撤去 |
| 井戸・浄化槽・合併処理槽 | 対象になることがある | 衛生上の支障・沈下の危険、埋戻し含む安全措置 | 将来の外構計画に合わせた任意の撤去 |
| 樹木・生垣・庭石 | 対象外になりやすい | 工事動線確保や安全確保に必要な最小限の撤去 | 庭園のリニューアル・伐採・移植の一体発注 |
| 地中障害(基礎杭・埋設配管・コンクリートガラ等) | 条件付き | 解体に伴い顕在化し、安全・衛生上の支障がある範囲の撤去 | 再建計画の支障解消を目的とする全面撤去 |
隣地・道路境界に関わる工作物は、所有権・管理者の確認が前提です。所有関係や境界確認が不明確なままの撤去は対象外やトラブルの原因となるため、事前に権利関係資料(公図・地積測量図・境界確認書等)で確認しましょう。
4.4 整地 舗装 更地管理費用の対象外に注意
解体後の整地は、工事の安全な完了に必要な最低限の復旧に限って対象となることが多い一方、再建・利便性向上のための工事は対象外です。特に、砕石敷き厚盛り、アスファルト舗装、コンクリート打設、雨水排水のための造成、フェンスやゲート新設などは補助対象外となるのが一般的です。
- 対象になりやすい整地の例:解体後の穴埋め・転圧・表面の安全確保などの最小限の原状回復。
- 対象外になりやすい工事の例:舗装・駐車場化、防草シート全面敷設、砕石厚盛り、外構の新設・更新、植栽工事。
- 更地管理費の例:除草・定期清掃・仮囲いの長期維持費、警備費等は原則対象外。
なお、火災保険・共済で補填される部分と同一の費用は、重複受給の回避の観点から対象外または減額調整となる取扱いが一般的です。見積書と保険支払明細の対応関係を整理し、補助対象経費と非対象経費を明確化して申請しましょう。
5. 支給金額の目安と解体費用相場
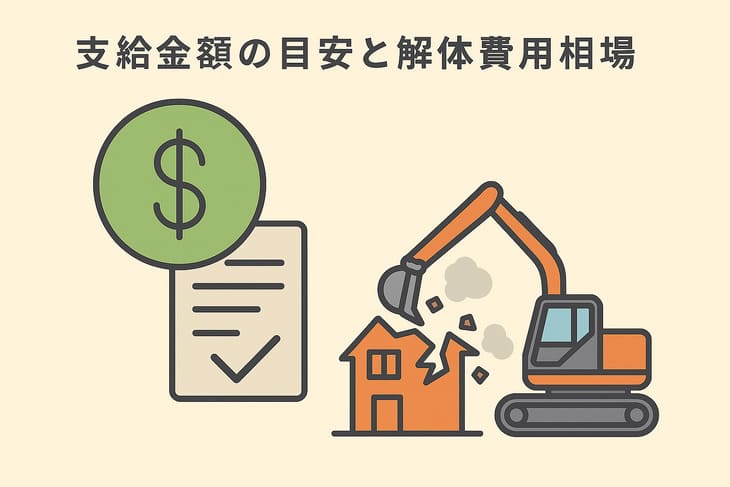
この章では、火事による家屋の解体で想定すべき費用相場と、補助金の支給金額の考え方を整理します。相場は「構造」「延床面積」「現場条件」「アスベストの有無」「火災ごみの量」などで大きく変動します。見積書は複数社から取り、付帯工事や産業廃棄物の処分単価まで明細で比較することが重要です。
5.1 木造住宅の解体単価と延床面積別の相場感
木造(在来工法・2×4等)の解体は、一般に「延床面積×単価」で試算します。全国的な実務の目安としては、付帯工事や特殊処分を除いた本体の解体費用が1平米あたり約12,000〜30,000円(坪あたり約4.0〜10.0万円)で推移します。都市部の狭小地や前面道路が狭い場合、足場・養生や小型重機・手壊しの比率が増え、上限側に寄りやすくなります。
| 延床面積(m²) | 坪換算(坪) | 本体解体の概算相場 | 前提条件 |
|---|---|---|---|
| 50 | 約15.1 | 約60万〜150万円 | 木造・整地簡易・付帯工事/特殊処分を除く |
| 80 | 約24.2 | 約96万〜240万円 | 同上 |
| 100 | 約30.3 | 約120万〜300万円 | 同上 |
| 120 | 約36.3 | 約144万〜360万円 | 同上 |
上記は本体の解体工事に限った概算で、別途計上されやすい費用として、足場・飛散防止養生、仮設電気・水、重機回送、残置物撤去、焼け跡(可燃物・金属・コンクリート等)の分別・搬出、産業廃棄物の中間処理・最終処分、道路使用・占用、近隣対策(散水・消臭)などがあります。火災後は焼損物の含水・混合により処分費が増えがちです。
5.2 鉄骨造 鉄筋コンクリート造の相場感と増減要因
鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)は、躯体の切断・破砕・積込みに要する時間と、コンクリート・鉄の処分の手間が増えるため、木造より単価が高くなる傾向です。以下は単価の比較目安です。
| 構造種別 | 単価の目安(円/m²) | 坪単価の目安(万円/坪) | 単価が上がりやすい条件 |
|---|---|---|---|
| 木造(W造) | 約12,000〜30,000 | 約4.0〜10.0 | 狭小地・前面道路4m未満・手壊し多用・残置物多量 |
| 鉄骨造(S造) | 約15,000〜38,000 | 約5.0〜12.6 | 厚肉H形鋼・溶断作業増・高所作業・ボルト抜き難航 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 約20,000〜50,000 | 約6.6〜16.5 | 壁式RC・基礎深い・鉄筋量多・ガラ搬出距離長 |
増減要因の代表例は次の通りです。
- 立地・搬入出条件:前面道路幅員、電線・街路樹、隣家との離隔、接道長
- 付帯工事の有無:外構(ブロック塀、門柱、カーポート)、土間コンクリート、樹木・庭石、井戸
- アスベスト:事前調査結果とレベル区分に応じた養生・除去・処分費の追加
- 火災特有の処分:焼損材の分別、臭気対策、消防放水後の含水廃材の重量増による運搬・処分費の増
- 地中障害:旧基礎・地中梁・浄化槽・ガラ埋設の掘削・処分
- 仮設・近隣対策:足場・防音シート、散水、粉じん・飛散防止、工事時間帯の制限
見積書では「本体」と「付帯工事」「産業廃棄物の品目別処分」「アスベスト対策費」「現場管理費」を分けて提示してもらうことで、相場との差異や増減要因を具体的に判断できます。
5.3 火事 解体 補助金の金額上限と自己負担の考え方
補助金の上限額・補助率は自治体要綱で定められます。一般的な設計は「定額(上限◯万円まで)」「定率(工事費の◯%・上限◯万円)」「面積連動(m²あたり◯円・上限◯m²)」のいずれか、または組み合わせです。対象経費は原則として「解体本体+必要最小限の付帯工事」に限定され、整地の高度化(砕石敷均し・舗装)や更地の維持管理費などは対象外になるのが通例です。
自己負担の基本式は自己負担額 = 解体工事費(見積契約額) − 補助金(交付決定額) − 火災保険・共済からの対象保険金です。ただし、同一経費の二重補填を避けるため、保険金相当分が補助金から控除・減額される、あるいは補助対象から除外される取扱いが定められている場合があります。
| 例 | 補助方式 | モデル工事費 | 補助金の考え方 | 自己負担の考え方 |
|---|---|---|---|---|
| A | 定率1/2・上限80万円 | 180万円(木造100m²、付帯最小) | 180万円×1/2=90万円 → 上限により80万円 | 180万円 − 80万円 −(保険金相当) |
| B | 定率2/3・上限150万円 | 240万円(木造120m²、付帯含む) | 240万円×2/3=160万円 → 上限により150万円 | 240万円 − 150万円 −(保険金相当) |
| C | 面積連動(10,000円/m²・上限100m²) | 300万円(RC造100m²) | 10,000円×100m²=100万円 | 300万円 − 100万円 −(保険金相当) |
補助金は「交付決定」前の着工で対象外となる取り扱いが一般的なため、自己負担額の見通しを立てる際も、交付決定額の確定後に契約・着工する前提で資金計画を組むことが肝要です。補助率や上限、対象経費の範囲は自治体により異なるため、担当課で最新の要綱・手引きの該当条項を必ず確認してください。
5.4 火災保険や共済との併用時の注意点
火災保険・共済には、建物本体の損害保険金とは別に「残存物取片付け費用」「損害防止費用」「臨時費用保険金」「失火見舞費用」など、解体・片付けや緊急措置に関連する付帯費用保険金が設定されている場合があります。約款・特約の有無と限度額(割合や上限金額)を保険会社に確認しましょう。
- 二重補填の回避:同一の解体・処分費に対して、保険金と補助金を重複受給することは認められません。通常は、保険金支払決定通知や支払金額が補助金の「減額要素」として扱われます。
- 申請書類の整合:補助金の交付申請・交付請求では、見積書・内訳書・写真・罹災証明書に加え、保険金の支払内容がわかる書面の提出を求められる場合があります。
- 名義の一致:被保険者(契約者)と補助金の申請者・交付請求の受取口座名義が一致しているかを確認します。
- 費目の切り分け:解体本体、残置物撤去、火災ごみの搬出処分、外構撤去など、費目を見積書で区分し、対象外経費が補助申請に混在しないようにします。
- 時系列の管理:事故の連絡→罹災証明書の取得→見積取得→補助金の事前相談→交付決定→契約・工事→実績報告→交付請求の順に、決定通知の有無を都度確認します。
保険の支払決定額が確定していない場合、補助金の交付決定額も仮置き(精算時に調整)となることがあります。精算時の減額・返還リスクを避けるため、併用前提のケースでは、保険会社・自治体窓口の双方に見積書を提示し、重複受給の判定と必要書類を事前にすり合わせておくと安心です。
6. 火事 解体 補助金の申請手順

火事で損壊した建物を解体し補助金(助成金・公費解体を含む)を受けるには、窓口での事前相談から精算・入金まで、法令上の届出と自治体の補助要綱に沿った段階的な手続きが必要です。以下では、申請から交付決定、工事、実績報告、精算に至るまでの流れを、必要書類や注意点とともに具体的に説明します。
6.1 事前相談と現地確認の準備
最初に、市区町村の担当課(危機管理、防災、建築指導、空家等対策、まちづくり、環境など制度所管課)へ連絡し、火災による解体で利用できる補助制度の有無と適用条件を確認します。所有者(共有者を含む)、建物用途(専用住宅、併用住宅、付属建物等)、構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)、延床面積、被災程度(全焼・半焼・部分焼)を整理した上で、現地確認(職員の立会いや委託事業者の確認)が必要かを調整します。
事前相談では、老朽危険家屋除却補助、公費解体(被災危険家屋等解体撤去事業)、火災ごみ搬出処分費助成など、対象メニューと排他関係、火災保険・共済との併用可否、補助対象経費の範囲、自己負担の有無を確認します。併せて、解体に伴う法定届出(建設リサイクル法の届出や大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)事前調査・届出)の要否と期限、道路占用・路上使用が必要な場合の手続きの見込みも把握します。
所有者が複数いる、相続登記が未了、借地・借家関係や区分所有(分譲マンション)など権利関係が複雑な場合は、同意書や委任状、代表者選任届等の準備が早期に必要となります。現地写真は四方向の外観、被災箇所、隣地との境界、付帯構造物(ブロック塀・付属建物・井戸・樹木など)を網羅的に撮影し、日付入りで整理します。
| 事前準備の項目 | 内容 | 用意する人 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 所有者・申請者確認 | 登記事項証明書、固定資産課税台帳の名寄せ、本人確認書類 | 申請者 | 共有者・相続人の同意や委任体制を事前に調整 |
| 敷地・建物情報 | 地番・家屋番号、延床面積、構造、用途、建築年 | 申請者 | 見積や届出の前提となるため正確性が重要 |
| 被災状況の把握 | 全焼・半焼・部分焼の区分、危険度、応急措置の有無 | 申請者 | 後日の判定・審査で参照される写真・記録を整備 |
| 関係者同意 | 共有者・賃借人・隣地所有者などの同意や立会い | 申請者 | 境界・残置物・付帯工作物の扱いを事前合意 |
| 近隣・道路条件 | 前面道路幅員、電線・ガス・水道・下水の撤去条件 | 解体業者 | 道路占用・路上使用許可の見込みを把握 |
| 法定届出の要否 | 建設リサイクル法届出、石綿事前調査・届出等 | 解体業者 | 届出期限を工程に反映し、補助の着工制限と整合 |
| 資金・工程計画 | 自己負担額の見込み、工期、写真記録の体制 | 申請者・業者 | 中間・完了検査や撮影要件を契約に明記 |
6.2 必要書類 罹災証明書 見積書 図面 写真
申請に必要な様式は自治体が指定します。共通して求められやすい書類は以下のとおりです。火災に関する公的証明は、消防機関が発行する「り災に関する証明」や市区町村が発行する「罹災証明書」など、自治体の運用で呼称・発行主体が異なるため、担当課の案内に従い取得してください。
| 書類名 | 発行元・作成者 | 提出タイミング | 重要ポイント |
|---|---|---|---|
| 交付申請書・申請様式一式 | 市区町村 | 申請時 | 補助要綱に沿って記載。押印・署名の要否を確認 |
| 火災に関する公的証明 | 消防機関/市区町村 | 申請時 | 火災発生の事実・被害の程度が分かる書式を取得 |
| 登記事項証明書・課税証明 | 法務局/市区町村 | 申請時 | 所有者・所在・床面積等の確認用 |
| 見積書(内訳明細) | 解体業者 | 申請時 | 数量・単価・仮設費・養生費・搬出運搬・処分費・諸経費・消費税まで明記 |
| 積算根拠・工事内訳書 | 解体業者 | 申請時 | 延床面積や実測数量、工法、搬出経路の条件を反映 |
| 位置図・配置図・図面 | 申請者・業者 | 申請時 | 住宅地図、敷地配置、各階平面等で対象範囲を明確化 |
| 被災状況・現況写真 | 申請者・業者 | 申請時 | 外観四方向、内部被災、付帯工作物、隣地境界を網羅 |
| 石綿(アスベスト)事前調査結果 | 調査者(有資格者を含む) | 申請時〜着工前 | 該当時は届出・掲示・作業計画と整合が必要 |
| 建設リサイクル法の届出(写し) | 発注者(通常は申請者) | 着工前 | 対象規模なら所定期日までに届出。副本の写しを提出 |
| 産業廃棄物処理計画 | 解体業者 | 申請時〜着工前 | 分別区分、運搬先、最終処分先、マニフェスト運用 |
| 同意書・委任状 | 共有者・権利者 | 申請時 | 共有・借地等の権利関係整理に必須 |
| 口座情報・本人確認 | 申請者 | 申請時 | 名義一致(氏名・住所・フリガナ)を厳密に確認 |
| 誓約書・反社会的勢力排除に関する確認 | 申請者・業者 | 申請時 | 虚偽申請の禁止、適正施工の遵守を誓約 |
| 他補助・保険金の受給状況申出 | 申請者 | 申請時 | 重複受給の調整に用いるため正確に記載 |
見積は仕様・数量・工程写真の撮影体制を含めて具体的に合わせ、後日の増減精算や設計変更が生じた場合の手続(変更承認)を契約条件に明記しておくと、審査が円滑です。
6.3 事前申請が必須の理由と着工制限
多くの自治体で、交付決定(内示・本決定)の前に契約締結や工事着手をすると補助対象外(遡及不可)となります。やむを得ない応急対策(倒壊防止の最小限の養生など)を除き、着工や請負契約の締結は交付決定後に行うのが原則です。相見積もりの提出や価格の妥当性確認を求める運用もあるため、見積取得・選定のプロセスは記録を残します。
| 着工前に避けるべき行為 | 想定リスク |
|---|---|
| 請負契約の締結・前払 | 交付決定前契約として不採択や対象外となる可能性 |
| 解体工事の開始 | 工事費が全額自己負担になるおそれ |
| 仕様・数量の無承認変更 | 増額分が不補助扱い、実績不認定 |
| 法定届出の欠落 | 行政指導・工事停止・補助不交付のリスク |
法令上の事前手続(例:建設リサイクル法の届出、石綿(アスベスト)に係る事前調査・届出、道路占用の許可など)には所定の期限があります。補助金の着工制限と各種法令の届出期限が矛盾しない工程表を組み、届出副本や受理通知を確実に保管・提出することが重要です。
6.4 交付決定後の契約 工事 実績報告の流れ
交付決定通知の受領後、見積・内訳に基づく請負契約を締結し、工事に着手します。近隣への事前周知(工期・作業時間・粉じん・騒音対策・搬出経路)、仮囲い・養生、アスベスト飛散防止措置、分別解体、適正運搬・処分、工程毎の写真記録とマニフェスト管理を確実に行います。数量差異や地中障害の発見など、契約内容に対する増減が生じる場合は、担当課へ速やかに相談し、必要な変更承認を得ます。
| 局面 | 申請者の作業 | 事業者の作業 | 提出物・記録 |
|---|---|---|---|
| 交付決定〜契約 | 契約書締結、工程表の共有 | 内訳確定、施工計画書作成 | 契約書写し、工程表 |
| 着工前手続 | 近隣周知、鍵・立入手配 | 石綿掲示、建リサ届出副本の現場備付 | 届出副本、周知チラシ |
| 工事中 | 進捗確認、変更の承認手続 | 分別・飛散防止、工程写真撮影、マニフェスト運用 | 中間写真、変更承認書、マニフェスト写し |
| 完了 | 出来高確認、検収 | 完了写真整理、請求書発行 | 完了写真、請求書、検収書 |
| 実績報告 | 実績報告書の提出 | 内訳書・証憑の提供 | 実績報告書、マニフェスト(B2〜E票)写し、領収書、通帳写し等 |
写真は「着工前(全景・各方向)」「工程中(分別状況・養生・撤去前後)」「完了(更地全景・境界・付帯物)」の時系列で不足がないよう撮影し、日付・撮影位置・対象をキャプション化して提出します。自治体の検査(書面・現地)が入る場合は、立会日程を早めに調整します。
6.5 精算 交付請求 入金までのスケジュール
実績報告の審査後、補助対象経費と交付額が確定し、交付決定の内容に基づいて交付請求を行います。交付方法は精算払い(いったん全額支払い後に補助分が振込)を基本とする運用が一般的で、自治体によっては代理受領方式等を採用している場合があります。入金は審査完了後に指定口座へ振り込まれます。
| 段階 | 主体 | 主な書類 | 審査・確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 実績報告 | 申請者 | 実績報告書、完了写真、請求書・領収書、マニフェスト写し、契約書写し | 数量・単価・範囲が交付決定・内訳と一致しているか |
| 実績審査・検査 | 自治体 | — | 対象外経費の除外、重複受給の有無、証憑の真正性 |
| 交付額の確定 | 自治体 | 交付確定通知 | 補助率・上限の適用、増減精算の反映 |
| 交付請求 | 申請者 | 交付請求書、口座情報 | 名義一致・誤記修正、押印要否の確認 |
| 入金 | 自治体 | — | 入金日・金額を確認し、保管書類を整理 |
交付決定前の費用や、対象外経費(整地・舗装・残置物の一部等)が含まれる場合は補助の対象になりません。審査期間や締切(申請期限・工期・実績報告期限)は自治体ごとに定められているため、事前相談時に必ず確認し、工程表と資金計画に反映させてください。
7. 解体工事の実務ポイント

7.1 解体業者の選び方と相見積もりの取り方
解体は一度きりの発注が多く、価格・安全・法令順守のバランスが重要です。業者を選ぶ際は、建設業許可(解体工事業)または解体工事業の登録の有無、産業廃棄物収集運搬業の許可、技術管理者(解体工事施工技士など)の配置体制、労災保険・請負業者賠償責任保険への加入状況を必ず確認します。現地調査なしの「坪単価のみ提示」はトラブルの原因になりやすいため避け、必ず現場を見たうえでの内訳見積を比較しましょう。
| 比較項目 | 確認ポイント | 留意点 |
|---|---|---|
| 資格・許可 | 建設業許可(解体工事)/ 解体工事業登録、産廃収集運搬業許可番号 | 許可の「業種・有効期限・対応エリア」を書面で確認 |
| 法令対応 | 建設リサイクル法の届出、石綿事前調査・届出の代行可否 | 届出の手順・期間・費用負担の有無を明確化 |
| 見積内訳 | 解体工事費・養生足場・残置物撤去・運搬処分・重機回送・交通誘導員 | 「地中障害・アスベスト・道路占用」は別途精算条件の有無を確認 |
| 安全・近隣配慮 | 粉じん・騒音・振動対策、警備計画、工程表 | 事前近隣挨拶・工事看板・クレーム窓口の明示 |
| 廃棄物管理 | 分別解体、搬出先、中間処理・最終処分場、マニフェスト運用 | マニフェスト写し・最終処分確認までの報告方法を取り決め |
| 保険 | 請負業者賠償責任保険・建設工事保険の加入証明 | 近隣物損・第三者傷害への補償範囲を確認 |
| 支払い条件 | 支払時期(着手金・中間・完了)、請求書・領収書の形式 | 補助金の交付決定後の契約・支払フローとの整合 |
相見積もりは最低でも2〜3社で実施し、同一条件の見積依頼書を用いて比較します。現場条件(前面道路幅、電線や電柱の位置、隣地との離隔、地下埋設物の有無、残置物量、アスベスト疑い箇所)を業者間で共通化し、写真・図面・罹災状況を共有することで、後日の増額リスクを抑えられます。電気・ガス・水道・通信の停止・撤去(メーター撤去、引込線撤去)や仮設電気・仮設水道の手配の担当(発注者/業者)を事前に決めておきましょう。
火災現場は構造体の劣化が進んでいるため、安全確保を最優先に、立入範囲の管理・倒壊リスク評価・消防や保険会社の調査完了の確認・現況写真の保存を徹底します。
7.2 アスベスト飛散防止と近隣対策
解体・改修に先立ち、大気汚染防止法に基づく石綿(アスベスト)含有建材の事前調査が義務です。調査は所定の知見を有する者が実施し、結果の記録・掲示、必要に応じて所管行政機関への届出を行います。石綿含有が判明した場合は、作業区分に応じた隔離養生、負圧集じん、湿潤化、飛散防止措置、作業基準の遵守が必須です。火災によりスレート屋根材や外壁材が破砕・脆化している場合は特に飛散リスクが高まるため、計画段階から対策を強化します。
| 対策項目 | 実施の要点 | 根拠・関連 |
|---|---|---|
| 石綿事前調査 | 図面・台帳・現地採取をもとに建材を特定、必要に応じ分析 | 大気汚染防止法、石綿障害予防規則 |
| 隔離・養生 | 飛散防止のためのシート養生、負圧機の設置、出入口の二重化 | 作業基準の遵守・掲示 |
| 湿潤化 | 散水で粉じん抑制、撤去材の湿潤保持、袋詰密封 | 粉じん対策・飛散防止 |
| 周辺環境配慮 | 防音・防塵シート、騒音・振動の管理、作業時間の遵守 | 騒音規制法・振動規制法・自治体要綱 |
| 近隣コミュニケーション | 着工前挨拶、工程・連絡先の周知、苦情即応の体制 | トラブル未然防止 |
| 作業員安全 | 保護具着用、洗浄設備、区域外持出し防止、教育の実施 | 労働安全衛生関係法令 |
火災現場特有の臭気や煤塵は近隣苦情につながりやすいため、散水・消臭・運搬車両のシート掛け・タイヤ洗浄・ルート選定を徹底します。石綿含有が疑われる建材(化粧スレート、成形板、吹付け材など)は「疑わしきは分析確認」を原則に、撤去方法と費用を事前に明確化してください。
7.3 産業廃棄物の分別運搬とマニフェスト管理
解体で発生する建設系産業廃棄物は現場内での分別が原則です。木くず、コンクリートがら、金属くず、ガラス・陶磁器くず、アスファルト・コンクリート、石膏ボード、断熱材、混合廃棄物などに分け、許可業者による収集運搬・処分を行います。発注者は、適正処理のための委託契約締結、許可証の確認、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存を確実に行います。
| 区分 | 代表例 | 処理の要点 |
|---|---|---|
| 木くず | 柱・梁・内装材 | 釘・金物の除去、再資源化ルートの活用 |
| コンクリートがら | 基礎・土間 | 金属分離、破砕・再生材化 |
| 金属くず | 鉄骨・配管・サッシ | 材質別選別、スクラップ搬出 |
| ガラス・陶磁器くず | サッシガラス・陶器 | 破砕飛散防止、別系統で搬出 |
| 石膏ボード | 内装ボード | 水濡れ防止、専用処理ルートへ |
| 混合廃棄物 | 分別困難な残渣 | 発生抑制、適正処分 |
| 特別管理 | 石綿含有廃棄物 等 | 基準に沿った梱包・表示・保管・運搬・処分 |
| マニフェスト管理ポイント | 実務の要点 | 発注者の確認 |
|---|---|---|
| 交付・回収 | 紙または電子(JWNET等)で交付、運搬・処分工程ごとに受領 | 最終処分完了の確認・保存(原則5年間) |
| 委託契約 | 収集運搬・処分それぞれと書面契約、許可範囲の適合確認 | 許可証写し・契約書・マニフェストの整合性 |
| 現場管理 | 保管場所の明示、飛散・流出・悪臭防止、積替え・保管の基準遵守 | 分別写真・搬出伝票の記録 |
解体費用の大半は「運搬・処分」に起因するため、分別精度の高さと処分先の透明性がコストと適法性を左右します。見積段階で廃棄物の種類ごとの単価と搬出先を明示してもらい、最終処分確認までの報告書(写真台帳・マニフェスト写し)の提出を契約条件に含めると安心です。
7.4 路上使用と道路占用の手続き
前面道路が狭い密集市街地や旗竿地では、仮囲い・養生足場・ダンプ待機・クレーン設置などで道路の利用が避けられない場合があります。このときは「道路使用許可(警察)」と「道路占用許可(道路管理者)」を適切に取得します。占用許可は道路上空や路面・地下に工作物等を設置する行為、使用許可は交通に影響する一時的使用(資材置き場、作業車両の停車、交通規制等)が対象です。
| 手続き | 所管 | 主な対象 | 主な提出資料 |
|---|---|---|---|
| 道路使用許可 | 所轄警察署 | 車両の長時間停車、資材仮置き、片側交互通行等 | 平面図・交通誘導計画・工程表・申請書 |
| 道路占用許可 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村) | 足場・防護棚・仮囲い・敷鉄板・仮設電柱等の設置 | 位置図・構造図・安全対策図・申請書 |
解体業者が代行するのが一般的ですが、許可取得前の着手は違反となるため、工程に十分な余裕を持ち、警備員(交通誘導員)の配置や通学路・生活道路への配慮を計画に織り込みます。周辺の月極駐車場や仮置きスペースの確保、搬出時間帯の調整、騒音・振動の抑制も合わせて検討します。
7.5 建設リサイクル法の届出が必要な規模の目安
一定規模以上の解体工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、市町村等を通じて都道府県知事等へ「分別解体等の計画等の届出」を行います。届出には工事概要、分別解体の方法、再資源化の計画、発注者・受注者の情報などを記載し、現場掲示や発注者への説明も行います。
| 工事種別 | 届出が必要となる主な規模要件 | 主な提出先 | 提出期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 建築物の解体工事 | 延べ床面積 80平方メートル以上 | 都道府県知事等(実務は市区町村窓口が多い) | 工事着手の7日前まで |
| 建築物の新築・増築 | 床面積 500平方メートル以上 | 都道府県知事等 | 工事着手の7日前まで |
| 建築物の修繕・模様替 | 請負代金 1億円以上 | 都道府県知事等 | 工事着手の7日前まで |
対象工事では、分別解体の実施、現場での掲示、再資源化の実績把握が求められます。解体業者に届出・掲示・説明の対応範囲を見積内訳に含めてもらい、工程(申請期間を含む)を逆算してスケジュールを組み立ててください。補助金は「事前手続完了前の着工」が不交付理由になり得るため、届出と関連法令の手続きを完了してから着工する段取りが不可欠です。
8. ケース別の対応とリスク管理

火災後の解体と補助金活用は、所有形態や場所、被害の態様で対応が大きく変わります。ここでは、失火と延焼、賃貸物件、分譲マンション、空き家、防火地域・準防火地域、付属建物という代表的なケースごとに、責任関係・手続・補助金上の留意点を整理します。
| ケース | 主な法令・基準 | 主な手続・関与主体 | 関連保険 | 補助金の留意点 | 解体の同意主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 失火・延焼がある場合 | 失火責任法、民法 | 消防本部の火災調査結果の取得、近隣と連絡、弁護士等への相談 | 火災保険、個人賠償責任保険 | 保険金充当分は補助対象経費から控除 | 所有者(共有なら共有者全員) |
| 借家(賃貸) | 借地借家法、民法 | 賃貸人・賃借人間での復旧/解体合意、原状回復範囲の確定 | 借家人賠償責任保険、家主保険 | 申請者は原則所有者。入居者の残置物撤去は対象外になりやすい | 所有者(物件オーナー) |
| 分譲マンション | 区分所有法、民法 | 管理組合の理事会・総会決議、共用部の復旧・除却の意思決定 | 共用部保険、専有部火災保険 | 共用部は管理組合申請、専有部は各所有者。重複申請不可 | 管理組合(共用部)、各区分所有者(専有部) |
| 空き家 | 空家等対策の推進に関する特別措置法、民法 | 所有者の特定・同意、相続関係整理、行政の助言・指導対応 | 火災保険(加入があれば) | 「特定空家等」の是正で補助対象になる自治体あり | 所有者(相続人を含む) |
| 防火地域・準防火地域 | 建築基準法、自治体の条例 | 仮囲い・養生等の防火措置、近隣説明、行政との事前協議 | 火災保険 | 付帯工事(養生・防塵等)の補助対象範囲に差 | 所有者(関係権利者の同意) |
| 付属建物(倉庫・納屋・車庫など) | 建築基準法、民法 | 主屋との一体判定、用途・面積の確認、廃棄物の分類 | 火災保険(付属建物特約等) | 主屋付随分のみ対象とする自治体が多い | 所有者 |
同一の解体費用に対して、補助金と保険金・賠償金を二重に充当することはできません(重複受給の禁止)。各ケースで資金の出所を整理し、申請前に自治体へ調整方針を確認してください。
8.1 失火で延焼被害がある場合の対応 失火責任法の基礎
失火責任法は、通常の過失による失火で隣家へ延焼した場合、失火者が隣家に対して損害賠償責任を負わないことを原則としています。重過失(著しい注意義務違反)がある場合や、契約上の義務違反がある場合はこの限りではありません。
延焼があるときは、まず消防本部の火災調査結果を取得し、原因と責任の有無を客観的に把握します。そのうえで、保険会社に事故連絡を行い、近隣とは感情的対立を避けるため、示談交渉は保険会社や弁護士を通じて進めます。
補助金活用では、自己の建物を解体する費用のうち、保険金で補填される部分は補助対象経費から控除されます。延焼先の解体・復旧費は原則として延焼先の所有者側の手続ですが、重過失が認定されて賠償となった場合には、賠償金と補助金の関係整理(控除)が必要です。
延焼の有無にかかわらず、現場の安全確保(立入禁止措置、倒壊防止の応急対応)と、周辺への粉じん・臭気対策を早期に講じることが二次被害防止とトラブル回避の要です。
8.2 借家や分譲マンションでの火災の対応
賃貸物件(借家・賃貸アパート)では、解体や原状回復の決定権者は原則として所有者(賃貸人)です。賃借人に過失があった場合の室内の原状回復義務は契約で定められ、保険は「借家人賠償責任保険」や個人賠償責任保険でカバーされることがあります。賃貸人の建物保険(家主保険)が共用部や構造部を補償しているケースもあります。
補助金は原則、所有者が申請主体です。賃借人の家財や残置物の処分費は対象外とする自治体が多く、賃貸借当事者間で費用分担を事前に合意しておくことが重要です。賃貸人・賃借人双方の事情を踏まえ、契約条項(善管注意義務、特約)と保険適用を照合して進めてください。
分譲マンションでは、専有部分の内装・設備の復旧・除却は各区分所有者、共用部分(外壁、躯体、配管等)は管理組合の所管です。大規模な被害で建替えや除却が議題となる場合、区分所有法に基づく特別多数による決議が必要になります(具体的な決議要件は法令に従います)。
マンションの補助金は、共用部は管理組合、専有部は各区分所有者がそれぞれ申請するのが原則で、同一工事を二重に申請しないことが必須です。理事会・総会での合意形成、見積の内訳分離、費用負担区分の明確化を徹底しましょう。
8.3 空き家で火事が起きた場合と空家法の適用
居住実態のない空き家が火災で危険状態になった場合、周辺への倒壊・落下のリスクが高いと行政が判断すれば、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく助言・指導・勧告・命令の対象となり得ます。措置命令に従わない場合、行政代執行で解体され、費用が所有者に徴収されることがあります。
補助金は、空家対策事業や老朽危険家屋除却で対象となる自治体がありますが、所有者(相続人を含む)の同意と申請が前提です。相続登記未了や所有者不明の場合は、まず権利関係の整理が必要です。火災による危険性が高い場合は、応急安全措置を講じつつ、自治体の担当課(空家対策、建築指導、危機管理等)に早期相談しましょう。
空き家は家財・残置物が多く、可燃物・危険物の混在で処分費が増えやすい傾向があります。分別方針と処理ルート(産業廃棄物・一般廃棄物の区分)を事前に解体業者と共有し、補助対象経費の線引きを確認してください。
8.4 防火地域や準防火地域での解体の留意点
防火地域・準防火地域は市街地の延焼遮断を目的としたエリアで、解体・工事中の火気・粉じん・飛散リスクの管理が重視されます。現場では、防炎シートや散水、仮囲い、養生計画、作業時間帯の調整など、近隣への影響を抑える対策を徹底します。狭あい道路や木密市街地では、交通誘導や重機搬入計画の精緻化が不可欠です。
補助金上は、養生・仮設・近隣対策の費用の扱いに自治体差があります。見積では仮設工事・養生費・運搬経路対策を明確に区分し、対象経費と対象外の線引きを事前確認しましょう。地域の建築指導課と事前協議を行うと、必要な手続や注意点の漏れを防げます。
密集市街地では、騒音・振動・粉じんの苦情が補助金の審査や近隣合意に影響することがあります。工事計画書と近隣説明の記録を残し、トラブルの未然防止に努めてください。
8.5 倉庫 納屋 車庫など付属建物の扱い
付属建物(倉庫・納屋・車庫・物置など)は、主屋に付随する用途か、単独利用かで補助対象の可否が分かれることがあります。主屋と一体で危険性が高い場合や、同一敷地・同一所有であることが要件になる自治体が一般的です。登記の有無は直ちに可否を決めるものではなく、現況での危険度と用途が重視されます。
費用面では、付属建物内の残置物(農機具、塗料、オイル等)や土間コンクリートの撤去、基礎・地中障害の処理が増額要因です。見積では主屋と付属建物の数量と単価を分離し、補助対象部分と対象外(舗装・整地・残置物処分などになりやすい)の項目を明確化します。
付属建物のみを先行解体する場合、後の再建計画や敷地条件(隣地後退・建ぺい率・防火規制)に影響する可能性があるため、建築士や行政窓口と整合を取って進めることが重要です。
いずれのケースでも、解体完了後は建物滅失登記の申請を速やかに行い、課税や補助金の実績報告で必要となる書類(契約書・請求書・マニフェスト・写真・領収書)を適切に保管してください。補助金は着工前申請・交付決定後着工が原則であるため、スケジュールに余裕を持ち、関係者の同意と証憑の整備を先行させることがリスク低減につながります。
9. 申請でつまずかないチェックリスト
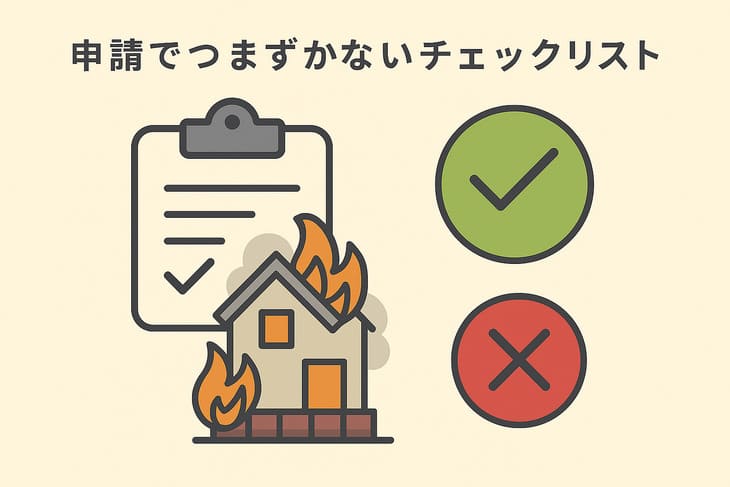
補助金の申請は、交付要綱の要件・期限・証憑の整合性が揃わないと不交付や減額の原因になります。特に、交付決定前の契約・着工は原則対象外、同一経費の二重受給は不可、対象経費は内訳書と証拠資料で裏づけるという3原則を常に意識し、事前相談→申請→交付決定→契約・着工→実績報告→精算の各段階で抜け漏れを防ぎましょう。
9.1 補助対象と対象経費の自己チェック
対象になる建物・工事・費用の線引きを、募集要領・交付要綱・様式集で確認したうえで、見積書は工種別に数量・単価・小計を明細化し、図面・写真・証憑とひも付けます。アスベスト事前調査・飛散防止養生・仮設足場・産業廃棄物の収集運搬・中間処理費・付帯工作物の撤去などの扱いは制度ごとに定義が異なるため、要綱の「補助対象経費」「対象外経費」の定義を必ず書面で確認してください。なお、建物の解体に伴って発生する廃棄物は産業廃棄物として扱われ、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で管理します。
| 項目 | チェック観点 | 参考書類 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 申請対象の建物 | 所在地・家屋番号・構造・延床面積が申請書、見積書、課税情報で一致しているか | 固定資産税課税明細書、登記事項証明書、平面図 | 地目や家屋の用途が制度要件に適合しているかを確認 |
| 所有者要件 | 申請者が所有者本人か、代理の場合は適切な委任があるか/共有の場合は全員の同意があるか | 同意書、委任状、本人確認書類の写し | 申請者名と登記名義・口座名義のズレは審査に影響 |
| 被害の事実 | 罹災証明書の区分(被害の程度)と発生日が申請内容と整合しているか | 罹災証明書、現況写真(着工前) | 区分変更や再調査が必要な場合は早めに手続き |
| 解体範囲の明確化 | 建物本体・付帯物(ブロック塀・倉庫・車庫等)・残置物の範囲が明細化されているか | 見積内訳書、配置図、現況写真 | 付帯工作物の撤去は対象外になる場合があるため要綱を確認 |
| 対象経費の線引き | 仮設・養生・飛散防止・収集運搬・処分・アスベスト除去・事前調査費の扱いを明確化 | 見積内訳書(工種別)、仕様書 | 原状回復を超える工事(新設外構、舗装、造成等)は対象外となることがある |
| 法定手続の計上 | 建設リサイクル法・大気汚染防止法に基づく事前手続の費用計上の可否を確認 | 各届出書の写し、調査報告書 | 届出は必須手続。費用の補助対象化は制度ごとに異なる |
| 見積の取得方法 | 相見積の要否・社数・様式の指定があるか | 相見積書、内訳比較資料 | 相見積が要件の場合は仕様統一と同一条件での積算が必須 |
| 施工業者の資格 | 解体工事業登録または建設業許可、石綿関連の有資格者配置 | 許可証・登録通知書の写し、技能講習修了証 | 資格要件を満たさない業者の経費は不認定のリスク |
9.2 申請期限とスケジュール管理
工程は「事前相談→(現地確認)→交付申請→審査→交付決定→契約・着工→工事→実績報告→交付請求・入金」です。交付決定前の契約・着工は原則補助対象外のため、締切日と審査期間、法定届出の期限を逆算して工程表を作成します。建設リサイクル法と大気汚染防止法の事前手続(石綿事前調査・届出)も同時並行で準備してください。
| 里程標 | やること | 法令・運用上の制約 | 実務の注意点 |
|---|---|---|---|
| 事前相談 | 窓口で制度要件・様式・必要書類・締切・現地確認の要否を確認 | 募集要領・交付要綱の指示に従う | 質疑は記録化。不明点は書面回答をもらい証跡化 |
| 罹災証明の取得 | 市区町村で罹災証明書を申請・取得 | 申請期限・再調査手続の定めあり | 区分・発生日が申請内容・見積と一致しているか確認 |
| 交付申請 | 申請書・添付書類一式を提出 | 申請期限厳守/補正期限あり | 不足書類は早期補正。工程表・写真撮影計画も添付 |
| 建設リサイクル法 | 対象規模の解体は事前届出 | 延床80㎡以上の解体は工事着手の7日前までに届出 | 届出後に変更が生じた場合は変更届 |
| 石綿(アスベスト) | 事前調査の実施と結果の届出 | 大気汚染防止法に基づき、工事開始前に調査義務/一定の場合は工事開始の14日前までに届出 | 調査報告書・掲示・飛散防止措置・作業記録を整備 |
| 道路占用・使用 | 足場・重機・養生で道路を使う場合の許可取得 | 道路法・道路交通法に基づく許可 | 警察署・道路管理者の両方の手続が必要な場合あり |
| 交付決定 | 交付決定通知を受領 | 決定額・対象経費・条件を確認 | 通知受領後に契約締結・着工/内容変更は事前に変更申請 |
| 実績報告 | 完了後に報告書・証憑を提出 | 報告期限・様式・必須添付の指定あり | 工事写真(着工前・施工中・完了)、マニフェスト、請求書・領収書・通帳の写しを整備 |
| 交付請求・入金 | 交付請求書を提出し精算 | 請求期限・振込口座の名義要件 | 入金予定日を確認し、返還・減額の有無もチェック |
スケジュールがタイトな場合でも「交付決定前の着工禁止」と「法定届出の期限」は厳守してください。やむを得ない工程変更は、着工前に必ず所管課へ変更相談を行い、指示された手続きを書面で残します。
9.3 重複受給 名義 口座の確認
補助金は、同一の費用を複数の制度や保険金で重ねて補填することはできません。同一経費の補填額の合計が実際の支出を超えないこと、申請者の名義・契約者・振込口座の名義が一致していること、共有不動産は関係者全員の同意があることを事前に確認します。相続・代理申請・住所変更が絡む場合は、証明書類を追加で求められることがあります。
| 項目 | チェック内容 | 必要資料 | NG例・リスク |
|---|---|---|---|
| 申請者(所有者) | 登記名義人と申請者が一致しているか | 登記事項証明書、本人確認書類 | 名義不一致で差戻し・不交付 |
| 共有物件 | 共有者全員の同意があるか | 同意書(共有者全員分) | 同意欠如で審査保留 |
| 相続が発生 | 代表相続人の特定と相続関係の証明 | 戸籍関係書類、遺産分割協議書の写し等 | 相続未整理で手続が進まず期限切れ |
| 代理申請 | 適切な委任と代理権限の明示 | 委任状、代理人身分証 | 委任不備で無効 |
| 振込口座 | 申請者本人名義か(法人なら法人名義) | 通帳の写し(名義・支店・口座番号) | 別名義口座で振込不可 |
| 火災保険・共済 | 受取の有無・金額・対象費目を申告 | 保険金支払通知書の写し | 未申告は後日判明で返還・減額 |
| 他制度との併用 | 同一経費の重複受給がないか | 他補助の交付決定通知の写し等 | 重複で不正受給・返還・加算金の対象 |
9.4 税務の基礎 雑損控除 固定資産税の取り扱い
税務では、火災による損失について所得税の雑損控除の適用可能性を検討します。控除額の計算では、保険金・共済金・補助金など損失の補填に充てられる金額は損失額から差し引く点に注意し、罹災証明書・支出の領収書・保険金支払通知書などの証拠資料を確定申告まで保存します。詳細は税務署または税理士に確認してください。
固定資産税では、住宅が滅失すると翌年度から住宅用地特例の適用が外れるため、土地の税負担が変動します。家屋を取り壊した場合、建物滅失登記は原因発生日から原則1か月以内に申請する必要があります(法務局で手続)。
| 項目 | 要点 | 相談先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 | 災害による損失を対象に、補填金額を差し引いた損失額を基に控除を検討 | 所轄税務署、税理士 | 罹災証明書、領収書、保険金通知の保存 |
| 固定資産税 | 建物滅失で翌年度から住宅用地特例が外れる | 市区町村税務課 | 減免の有無・要件は自治体で確認 |
| 建物滅失登記 | 取り壊し後に登記申請(原則1か月以内) | 法務局 | 解体業者の取壊し証明、工事写真の用意 |
税務・登記は補助金の審査と並行して準備し、控除・減免・登記の手続時期が補助金の実績報告と矛盾しないように記録を統一してください。証憑は原本を保管し、提出は写しに統一すると後工程の整合性が保てます。
10. 参考資料と相談窓口

火事で家屋を解体し補助金を利用する際は、根拠となる公的資料の参照と、所管窓口への早期相談が不可欠です。ここでは、国土交通省(国交省)を中心とした手引き・通知・ガイドラインの確認ポイントと、都道府県および市区町村の相談窓口の探し方を整理します。
10.1 国土交通省の手引き 通知 ガイドラインの確認ポイント
国交省は、空家等対策、被災危険家屋の解体、建設リサイクル法に基づく届出、解体工事に伴う基準整備などを所管しています。自治体が実施する補助制度や公費解体は、国交省の交付金・通知・ガイドラインを参照して設計されるのが一般的です。年度ごとに更新や運用の見直しが行われるため、最新の資料を確認してください。
| 資料カテゴリ | 主な内容 | 所管 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 被災危険家屋等解体撤去事業 関連資料 | 大規模災害時の公費解体の枠組み、危険度判定の活用、自治体実施の流れ、費用負担の考え方 | 国土交通省(住宅・建築分野) | 対象建物の範囲、判定の要件、実施主体が市区町村であること、補助の上限や自己負担の有無が自治体要綱で決まる点 |
| 空家等対策の推進に関する特別措置法・交付金 関連資料 | 空家等対策推進交付金の位置づけ、老朽危険家屋の除却支援メニュー、自治体の事業設計の考え方 | 国土交通省(住宅局等) | 除却補助の財源スキーム、対象基準(危険度・老朽度等)、募集期間や予算枠により申請できる時期・件数が制限される点 |
| 建設リサイクル法 解体工事の届出・分別解体 | 発注者・元請の責務、届出の対象工事規模、標準様式、分別解体・再資源化のルール | 国土交通省 | 届出が必要となる規模の目安、提出先(都道府県・政令市等)、補助金の要件として適正な届出・分別解体が求められること |
| 大気汚染防止法(石綿) 事前調査・届出 | 石綿含有建材の事前調査義務、調査結果の報告・届出、作業基準・標識掲示 | 環境省(制度)/自治体(所管窓口) | 解体前の事前調査と必要な届出は義務、調査結果の保存・説明責任、補助対象経費に調査費が含まれるかは自治体要綱で確認 |
| 被災建築物の応急危険度判定 | 災害後の建築物の危険度評価、立入制限・解体判断の基準の考え方 | 国土交通省 | 判定結果が公費解体や補助制度の前提となる場合があるため、評価の有無・記録の扱いを確認 |
実務での読み方のコツは、国の資料で「制度の枠組み」と「一般原則」を押さえたうえで、最終的には市区町村の要綱・要領・募集要項・申請様式で運用を必ず確認することです。補助率・上限額・対象経費・申請期限・着工制限は自治体ごとに異なり、年度で改定されます。
また、見積取得・写真撮影・図面準備・罹災証明書の提出時期など、実務の細部は自治体の手引きに準拠します。国のガイドラインと自治体運用に相違が見られる場合は、自治体の担当課に確認し、指示書・メール等でエビデンスを残しておくと安全です。
10.2 都道府県と市区町村の窓口の探し方
補助金や公費解体の一次窓口は原則として市区町村です。解体に関する届出や環境規制は、都道府県や政令指定都市・中核市が所管する場合があります。以下を目安に、最初の相談先を選びましょう。
| 相談・手続の目的 | 一次窓口(目安) | 担当部局の例 | 必要資料・持参物の例 |
|---|---|---|---|
| 火災による解体費の補助(老朽危険家屋除却・空家等対策) | 市区町村 | 建築指導課/住宅政策課/都市整備課/空家対策室 | 申請書様式、見積書、対象家屋の写真・図面、所有者確認書類、罹災証明書 |
| 大規模災害時の公費解体(被災危険家屋等解体撤去事業) | 市区町村 | 災害対策本部/危機管理課/建設・都市整備部門 | 危険度判定結果、現地確認記録、同意書、本人確認書類 |
| 火災ごみ・残置物の搬出・処分費助成 | 市区町村 | 環境部/清掃事務所/廃棄物対策課 | 発生状況の写真、数量・品目の内訳、見積書、搬出ルートの計画 |
| 建設リサイクル法の届出(分別解体・再資源化) | 都道府県 または 政令市・中核市 | 建築指導課/土木事務所/建設リサイクル担当 | 工事概要書、分別解体計画、対象規模の確認資料、標準様式 |
| 大気汚染防止法(石綿) 事前調査・届出 | 都道府県 または 政令市 | 環境保全課/大気保全課/公害対策課 | 事前調査結果、分析結果(必要時)、作業計画、標識掲示計画 |
| 道路使用許可・道路占用(養生・足場・搬出) | 警察署/道路管理者 | 警察署(道路使用)/市区町村の道路管理課・都道府県土木事務所(道路占用) | 施工計画図、交通誘導計画、占用箇所図、期間・時間帯の計画 |
| 産業廃棄物の処理に関する相談 | 都道府県 | 廃棄物対策課/環境政策課 | 排出予定物の品目・数量、委託契約書案、マニフェスト運用計画 |
| 税務(雑損控除・固定資産税の減免等)の確認 | 税務署/市区町村 | 所轄税務署(所得税)/市区町村税務課(固定資産税) | 罹災証明書、費用領収書、保険金支払通知、確定申告関連資料 |
窓口の探し方は、自治体公式サイトで「解体 補助」「老朽危険家屋 除却」「空家等対策」「罹災証明」「建設リサイクル法 届出」「石綿 事前調査 届出」などの語で検索し、担当課ページの「要綱」「実施要領」「募集要項」「様式(申請書・実績報告書)」を確認するのが近道です。電話で問い合わせる場合は、家屋の所在地・構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)・延床面積・被害程度(全焼・半焼・部分焼)・解体予定時期・見積取得状況・保険金の見込み・罹災証明の有無を伝えるとスムーズです。
補助金は「着工前の事前申請」が原則です。交付決定前に契約・着工すると対象外となる自治体が多いため、必ず募集要項の「着工制限」「対象経費」「スケジュール(申請期限・実績報告期限・交付請求期限)」を確認してから動きましょう。要件の解釈に迷う場合は、担当課にメール等で確認し、回答の記録を残すと申請でつまずきません。
最後に、自治体の制度の有無・対象・上限額・補助率は地域と年度で異なる点に注意してください。同じ「火事 解体 補助金」でも、老朽危険家屋除却補助で火災案件が対象となるか、公費解体の適用の可否、火災ごみ助成の内容は自治体ごとに異なります。最新の要綱・手引き・通知を必ず確認し、疑問点は一次窓口へ相談しましょう。
11. まとめ

結論:火事で家を解体する補助は、個別火災と大規模災害で制度が分かれ、自治体の実施・火災保険の有無で適用と上限が変わる。根拠は国土交通省の被災危険家屋等解体撤去事業と空家等対策特別措置法の枠組み。まず罹災証明書(または被災証明書)を取得し、見積書・写真を整えて窓口へ事前相談しましょう。
多くの自治体で交付決定前着工は対象外。解体本体や養生・残置物撤去は対象になり得る一方、整地や更地管理は除外されやすい傾向です。金額には上限があり自己負担が生じやすく火災保険・共済とは重複受給不可または減額調整が一般的です。工事は建設リサイクル法の届出規模を確認し、大気汚染防止法に基づく石綿事前調査・届出と近隣対策を徹底しましょう。
申請と工事の流れは「罹災証明→事前申請→交付決定→契約・工事→実績報告→精算」。東京都や横浜市でも運用は区市町村で異なるため、最新の要綱を必ず確認が必要です。相見積もりで費用妥当性を担保し、書類・期限・名義をチェックすれば、補助金の取り逃しとトラブルを避けられます。





