東京で火事後の家屋を解体する必要が生じた方向けに、2025年最新のルールと実務を、初動チェックリストから費用削減まで一気通貫で示します。読み終えると、費用相場の考え方、消防・保険会社・解体業者の連絡順と連絡先、火災保険と助成金の併用、罹災証明書の取得、建設リサイクル法の電子届出とアスベスト事前調査の電子申請、騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例への対応、不燃化特区や木密地域の除却補助・空き家対策の探し方が分かります。見積書の内訳(本体解体費、付帯工事費、産業廃棄物処分費・運搬費、諸経費)の読み解き方、相見積もりと工程分割、道路使用許可や近隣挨拶、仮囲い・防炎・防じん・防音、誘導員、解体後の滅失登記と固定資産税の減免、防火地域での再建計画まで具体化。初めての方でも迷わないよう、必要書類と提出の流れ、連絡先の整理まで最低限の判断材料をまとめました。内容は東京23区・多摩エリアの実務に即しています。結論:火事直後は証拠保全と安全確保を最優先に、アスベスト調査を早期実施し、電子届出を前倒し、相見積もりと補助金・火災保険を最大活用することが、費用・期間・近隣トラブルを最小化する近道です。
Contents
想定読者とこの記事で分かること

こんな方に読んでほしい(想定読者)
本記事は、東京(23区・多摩地域)で火災被害を受け、住家・店舗・事務所・賃貸物件などの解体を検討する方に向けて書かれています。全焼・半焼・一部焼損の別や、構造(木造・軽量鉄骨・RC)を問わず、初動から解体・手続きまでの実務を「東京都のルールに合わせて」確実に進めたい方を対象とします。
また、所有者本人だけでなく、親族・管理会社・相続予定者・弁護士や司法書士・不動産会社・建築士など、代理人や支援者として動く立場の方にも役立つよう、見積もり・契約・工程管理で注意すべき要点を整理しています。火災保険(例:東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上、こくみん共済coop〈全労済〉等)や共済の活用、罹災証明書の取得、東京都・区市町村の補助制度の検討を視野に入れて読み進められます。
| 読者タイプ | 直面する状況 | 代表的な悩み |
|---|---|---|
| 個人の所有者(持家・空き家) | 火災後の養生・近隣対応・罹災証明書の取得・火災保険の申請・解体の要否判断 | 費用総額と内訳、助成金の有無、アスベスト調査の必要性、いつまでに何をするか |
| 賃貸オーナー・中小事業者 | テナント・入居者対応、事業継続、原状回復、産業廃棄物管理、工程短縮の要請 | 相見積もりの取り方、契約・変更合意、道路使用許可と近隣調整、工期・騒音配慮 |
| 代理人・支援者 | 証拠保全、保険会社・鑑定人対応、役所手続きの代行、見積書の査読・精査 | 数量根拠の取り方、内訳の標準化、必要書類一式、工程と安全・品質の管理要点 |
個人の所有者
都内の持家・実家・空き家が火災に遭い、倒壊や延焼の不安、臭気や粉じんによる近隣クレーム、固定資産税や再建計画の悩みを抱える方を想定しています。罹災証明書の取得から、火災保険金の申請、解体見積もりの比較、アスベスト事前調査の段取りまで、初めてでも迷わない道筋が分かります。
事業者・オーナー
賃貸住宅・共同住宅・店舗併用住宅・小規模オフィス・倉庫などの所有者で、テナント・入居者対応と事業継続を両立しつつ解体を進めたい方に向け、産業廃棄物のマニフェスト管理、騒音・振動対策、道路使用許可や交通誘導員の手配の考え方を把握できます。
代理人・支援者
家族・管理会社・士業・不動産事業者・建築士など、所有者に代わって動く方が、証拠保全(写真・動画・被害状況の記録)から見積精査・契約・変更管理までを漏れなく進めるためのチェックポイントを整理して理解できます。
この記事でわかること(到達点)
本記事を読み終えると、東京都で火事後に解体を進めるための判断基準と実務の流れが、今日から自力で動ける水準で整理できます。
特に、費用相場の読み解き方、手続き・届出の順番、支援制度の探し方、相見積もり・契約の勘所、現場の安全・近隣配慮、解体後の登記・税務まで、意思決定に直結する情報を網羅的に把握できます。
| トピック | 要点 | 得られること |
|---|---|---|
| 費用相場の考え方と内訳 | 本体解体費・付帯工事・産業廃棄物処分・運搬・諸経費の構成と数量根拠 | 見積もりの妥当性を判断し、無駄な費用を避ける視点が身につく |
| 初動対応と安全配慮 | 二次災害防止、現場の養生・仮囲い、証拠保全、近隣連絡の基本 | トラブル・リスクを最小化し、保険・補助の手続きに必要な記録を確保できる |
| 手続きの全体像 | 建設リサイクル法の届出、アスベスト事前調査・結果報告、騒音・振動への配慮 | 東京都で必要となる届出・申請の種類と順序を把握し、抜け漏れを防げる |
| 支援制度の探し方 | 不燃化特区・木密地域の除却補助、老朽・危険家屋、空き家対策の枠組み | 自分の物件が対象となり得る制度の方向性を自力で特定できる |
| 見積もり・契約の実務 | 数量根拠の取り方、内訳項目の標準、契約・変更合意のルール | 相見積もりの比較軸が明確になり、契約後の追加費用を抑制できる |
| 工程・近隣対応 | 近隣挨拶、粉じん・騒音対策、防炎シート・散水、道路使用許可と誘導員 | 密集市街地でもクレームや中断を避け、工程を安定させられる |
| 解体後の手続き | 滅失登記、固定資産税の減免、再建計画と防火地域等の制限 | 税・登記・再建の見通しを持ち、次のステップに円滑に移れる |
検索意図への対応
「火事 解体 東京」という検索意図に対し、費用・手続き・助成・業者選定・工程管理・近隣対応・法令遵守という意思決定に必要な要素を、東京都の実務に沿って一気通貫で把握できる構成にしています。
特に、アスベスト事前調査や建設リサイクル法の届出、産業廃棄物のマニフェスト、罹災証明書、道路使用許可など、東京都内の解体で共起しやすい要件・用語を平易に整理し、読み進めながら不明点を解消できます。
読む前に知っておきたい前提条件
本記事は、2025年時点の東京都および区市町村で一般的に求められる手続き・運用を前提にしています。個別案件では、立地条件(前面道路幅、路上駐車の可否、隣地との離隔、電線やガス・水道の状況)、建物用途・構造、焼損の程度、残置物の量、アスベスト含有の有無によって、費用・工程・必要手続きが変わります。
対象エリアと時点
対象は東京都内(23区・多摩地域)です。制度・運用は改定されることがあるため、最終的な要件は所管(東京都・区市町村・警察署・東京消防庁・法務局・保険会社等)で確認してください。
対象とする建物・工事
住宅、共同住宅、店舗、事務所、倉庫などの建築物の解体を想定しています。仮設物や外構(門扉・塀・カーポート・樹木・地中障害)も、状況により工事範囲に含まれます。
費用・相場の表現について
相場は個別条件で大きく変動します。本記事では、数値の断定ではなく「内訳の見方」「数量根拠の取り方」「コストを左右する要因」を重視して解説します。
用語の簡易定義
本文で頻出する用語を先に定義します。詳細は各章で実務に沿って解説します。
| 用語 | 意味 | 主な窓口・関係先 |
|---|---|---|
| 罹災証明書 | 火災による被害の程度を公的に証明する書類 | 工事場所の区役所・市役所(防災担当等) |
| 建設リサイクル法の届出 | 一定規模以上の解体で必要となる工事届出 | 工事場所の区市町村 |
| アスベスト事前調査・結果報告 | 解体前に実施する石綿の有無の調査と報告 | 東京都(都道府県等への報告) |
| 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 廃棄物の適正処理を管理するための伝票 | 排出事業者・処理業者間で交付・管理 |
| 道路使用許可 | 工事で道路を一時的に使用する際の許可 | 所轄の警察署 |
| 滅失登記 | 建物を取り壊した後に行う登記手続き | 法務局(東京法務局等) |
| 不燃化特区・木密地域 | 延焼リスクの高い密集市街地の整備・除却促進の枠組み | 東京都・各区 |
本記事の活用方法
緊急性の高い方は、初動の優先順位と、費用・工程を左右する要因だけを先に押さえ、並行して見積もりと手続きを進めるのが効率的です。時間に余裕があれば、支援制度や契約・工程管理の章まで読み込み、全体最適で計画を立てると、費用・工期・リスクのバランスが良くなります。
最短で判断したい場合
必要な記録(被害写真・動画・被害範囲のメモ)を確保し、所有者情報と保険証券、図面・登記情報等を手元に集めたうえで、費用の内訳の見方と届出の順序を掴みます。次に、現場条件(前面道路、残置物、アスベストの可能性)を整理して相見積もりを依頼し、同条件で比較できるよう数量根拠と工程を揃えてもらいます。
じっくり準備する場合
区市町村の支援制度の対象可否、解体業者の許可・登録(解体工事業登録や建設業許可の有無)、近隣条件(学校・病院・高齢者施設の有無など)を事前調査し、契約条項(変更合意、追加費用、産廃の処理方法、現場管理)を精査します。これにより、見積の透明性と現場の安全・品質・近隣配慮を高い水準で確保できます。
すぐ動くチェックリスト 火事直後から解体まで
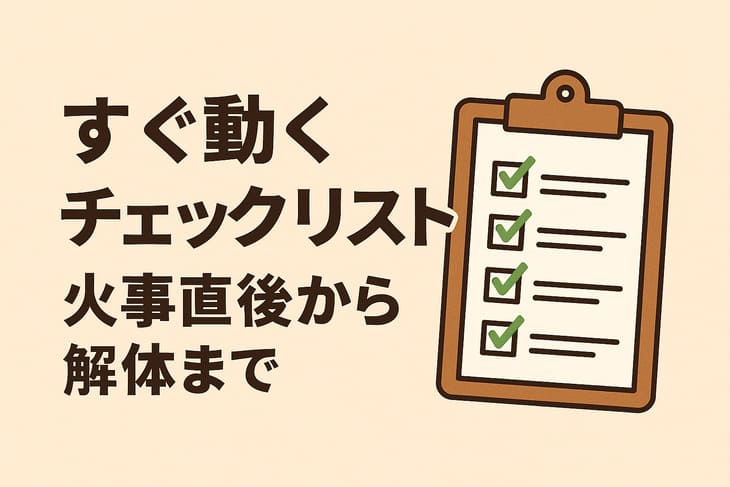
火災直後は命の安全と現場の保全が最優先です。そのうえで、火災保険の査定、罹災証明書、解体工事(東京エリアの手続きや助成制度の活用)につながる記録と連絡を、時系列で確実に進めます。以下は、鎮火直後から解体着手までの実務チェックリストです。
| フェーズ(目安) | 目的 | 主担当 | 主な行動 | ゴール |
|---|---|---|---|---|
| 0〜24時間 | 人命・現場安全の確保、二次災害の防止 | 所有者・居住者、消防 | 立入制限、電気・ガスの遮断依頼、倒壊・感電の回避、簡易バリケード | 現場が安定し、再燃・感電・転落・盗難のリスクを最小化 |
| 1〜3日 | 証拠保全、保険・罹災手続きの準備 | 所有者、保険会社 | 写真・動画・寸法の記録、家財リスト化、保険会社へ事故連絡 | 査定に耐える記録一式が整理できている |
| 3〜7日 | 解体の初期検討と相見積もり準備 | 所有者、解体業者 | 現地確認依頼、アスベスト事前調査の段取り、仮囲い・養生の相談 | 費用・工程の大枠と安全仮設の方針が固まる |
| 1〜2週間 | 契約前の詰めと近隣配慮 | 所有者、解体業者 | 内訳明細の確認、残置物の取り扱い方針、近隣へ説明の準備 | 解体発注の可否判断ができる |
| 着手前日まで | 着工条件の整備 | 解体業者、インフラ事業者 | インフラ撤去立会い、仮囲い・足場計画、搬出経路の確定 | 安全かつ合法に着工できる状態 |
安全確保と二次災害防止
鎮火後でも再燃・倒壊・感電の危険は続きます。消防・警察の指示に反する立入りや片付けは行わないでください。
- 立入制限と現場の目印付け:危険箇所(軒・梁のたわみ、ひび、スレート・瓦の落下、階段の焼損)を確認し、コーン・バリケード・ロープで範囲を明示。夜間は簡易照明で可視化。
- 電気・ガス・水道の安全確保:電気は東京電力パワーグリッド、ガスは東京ガス、水道は東京都水道局へ停止・点検を依頼。ブレーカーやメーターには触れず、事業者の指示に従う。
- 感電・有害粉じん対策:立入が必要な場合は、絶縁靴・ヘルメット・皮手袋・保護メガネ・防じんマスク(DS2・N95相当)を装着。濡れた屋内は感電・転倒のリスクが高く、単独行動は避ける。
- 危険物の一時対応:LPガスボンベ、灯油缶、スプレー缶、リチウムイオン電池、可燃性塗料は動かさず、消防・事業者に処置を相談。
- 再燃・延焼の予防:焦げた断熱材・木部・家具は内在熱で再燃の恐れ。水濡れ家財の自然発熱にも注意。異常な熱や煙・においを感知したら再度119番。
- 防犯と近隣配慮:窓・開口部は合板やブルーシートで仮塞ぎ。貴重品・重要書類は可能な範囲で回収し、戸締り。飛散物は回収し、隣地や道路の安全を確保。
| 主なリスク | 兆候 | 推奨初動 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 倒壊 | 梁・柱の焼損、壁の膨らみ、基礎ひび | 立入禁止範囲の拡大、専門家(解体業者・建築士)へ相談 | 余震・強風・積雪でリスク上昇。居住者の自主補強は行わない。 |
| 感電 | 濡れた床・露出配線・ブレーカー焼損 | 通電停止の確認、感電防止具を装着 | 素手で金属部に触れない。通電再開は事業者判断に従う。 |
| 粉じん/アスベスト | スレート板・ケイ酸カルシウム板・吹付材の破砕 | 散水で飛散抑制、作業者は防じんマスク着用 | 破片の破砕・掻き出し禁止。専門調査・処理を待つ。 |
| 再燃 | くすぶり、焦げ臭、白煙 | 消防へ通報、接近禁止 | 水かけやかき出しで酸素供給しない。 |
証拠保全と記録
片付けや搬出の前に「全てを撮る・残す」。この順番が火災保険の支払い、罹災証明書、解体費用の補助金活用の可否に直結します。
- 全景から細部へ撮影:建物四隅から外観、屋根、外構、隣地との境界、前面道路、電柱・メーター位置。内部は各室の入口→天井→壁→床→設備→家財の順で。
- 方位・時刻・スケールを明記:写真には日付、方位(北矢印)、サイズ比較がわかる物差し・メジャーを映す。可能なら動画で室内一筆書きの記録も。
- 家財のリスト化:主要家電・家具は品名・型番・購入時期・概算価格・損害状況をメモ。領収書・保証書・取扱説明書があれば確保。
- 寸法の簡易採取:延床面積、各室の間口×奥行、高さ、開口部サイズ、外周長さ。図面が焼失していても、見積やアスベスト調査の精度向上に有効。
- 現況の保持:罹災調査・保険鑑定・アスベスト事前調査が済むまで、原状を大きく変えない。濡れた書類は写真を撮ってから乾燥・保管。
- データの二重化:スマートフォンの写真・動画はクラウドと外部メディアにバックアップ。ファイル名に「日付_場所_対象」を付与。
| 撮影ショット | ポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 外観全景(四方向) | 隣地・道路・電線との位置関係、傾き、屋根の損傷 | 前面道路幅員や電柱位置は重機・搬出計画に必須 |
| 室内各室 | 入口→天井→壁→床→設備→家財の順に俯瞰と寄り | ススの高さや焼け止まり位置は延焼範囲の判断材料 |
| 設備・メーター | 電気・ガス・水道メーター、分電盤、給湯器 | 撤去や復旧費の算定に影響 |
| 外構・付帯物 | 門扉、カーポート、ブロック塀、物置、樹木 | 解体見積の「付帯工事」項目の根拠 |
| アスベスト疑い箇所 | 古いスレート屋根、ケイカル板、ビニル床タイル等 | 採取・破砕はせず、位置と状態のみ記録 |
- やってはいけないこと:焼けた壁や天井の剝がし、断熱材の掻き出し、家財の一括廃棄、瓦礫の破砕。飛散と証拠喪失の原因になります。
- 残置物の扱い:保険鑑定の完了前は原則現状維持。廃棄は「数量・写真・搬出先の記録」を残して実施。
連絡先の一覧 消防 保険 解体業者
緊急度と目的ごとに、誰に何を伝えるかを整理します。電話時は「住所・氏名・連絡先・被害状況・安全上の懸念・立会い可能時間」を準備し、会話の要点と担当者名をメモします。
| 目的 | 窓口 | 伝える内容 | 緊急度 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|
| 再燃・危険通報 | 東京消防庁(119)・管轄消防署 | 住所、再燃の兆候、危険物有無、立入困難箇所 | 至急 | 安全確保、到着まで立入禁止 |
| 電気の停止・安全確認 | 東京電力パワーグリッド | 住所、メーター位置、焼損状況、立会い可否 | 高 | 通電停止後に室内確認。復旧は指示に従う。 |
| ガスの停止・漏えい確認 | 東京ガス | 住所、器具・配管の損傷、臭気の有無 | 高 | バルブ操作は自己判断で行わない。 |
| 水道の止水・漏水確認 | 東京都水道局 | 住所、メーター位置、漏水の状況 | 中 | 止水やメーター撤去の段取り確認 |
| 保険の事故連絡 | 加入中の火災保険(保険会社・代理店) | 保険証券番号、発生日時、被害の概要、写真提出方法 | 高 | 鑑定日程の調整、必要書類の確認 |
| 罹災証明の申請相談 | 区役所・市役所・町村役場(市区町村) | 住所、被害状況、立会い可能日、必要書類 | 中 | 現地調査の立会い準備、写真・身分証の用意 |
| 解体の初期相談・現地確認 | 東京都内の解体工事業者(複数社) | 住所、建物規模、前面道路幅員、隣地状況、残置物の有無 | 中 | 相見積もりの依頼、アスベスト事前調査の段取り |
連絡は「安全→保険→行政→解体」の順で重複なく進めると、査定や届出、解体スケジュールが滞りにくくなります。
- メモに残すべき項目:通話日・担当部署・担当者名・要請内容・約束日時・持参書類・指示事項。
- 解体業者へ事前共有:撮影データ、概略寸法、ライフライン状況、前面道路条件(幅員・一方通行・時間規制)、近隣の学校・病院など配慮施設。
火事 解体 東京の費用を抑える五つの戦略

都内の火災後解体は、木造密集地域や狭小地、前面道路の幅員制限、周辺の生活道路・通学路の兼用など、工事条件が費用に直結します。費用増の典型要因を先読みし、制度活用と工程設計を戦略的に行うことで、総額を抑えつつ安全・法令順守を両立できます。
| 要因 | よくあるコスト増の原因 | 削減の考え方 |
|---|---|---|
| 保険・補助 | 補償範囲の見落とし、補助の事前申請漏れ | 約款確認と早期相談、補助は交付決定後に契約・着工 |
| 残置物 | 混載・未分別、搬出動線の不足 | 分別方針と仮置き計画、家電リサイクル対象の切り分け |
| アスベスト | 着工直前の調査で工程停止 | 有資格者による早期調査で見積精度を上げる |
| 見積・工程 | 内訳不足で追加精算、過剰仕様 | 数量根拠付きの相見積もり、工程分割の適用 |
| 道路・仮囲い | 大型車進入不可、過剰な養生変更 | 前面道路の改善、必要十分な仮囲い設計 |
火災保険と助成金の最大活用
火災保険と区市町村の除却補助は、自己負担を大きく左右します。補助金は交付決定前の契約・着工で対象外となる運用が一般的なため、工程は「申請→交付決定→契約→着工」の順を厳守します。保険は契約内容(特約)により、解体・残存物取片付・損害防止費用などが対象となる場合があります。
火災保険のチェックポイント
契約中の保険会社に事故連絡後、損害調査の結果に基づき支払可否が判断されます。見積書・現場写真・罹災証明書(区市町村で発行)などの提出が求められるのが通常です。保険で相談すべき費用項目の範囲を早期に確認し、見積内訳と整合させることで、差戻しや再見積もりによる遅延と余計な費用を防げます。
| 費用項目 | 保険担当へ確認したい点 |
|---|---|
| 解体費 | 焼損部分の解体が対象となるか、全解体時の扱い、見積根拠の形式 |
| 残存物取片付 | 片付け費用の補償有無、家財・建材の区分方法 |
| 損害防止費用 | 応急養生・仮囲い・飛散防止の範囲 |
| 臨時費用等 | 特約の上限・支払条件、必要書類 |
区市町村等の補助の探し方
都内では、密集市街地の不燃化や老朽危険建築物、空家等の除却支援など、地域の施策に基づく補助制度が設けられている場合があります。対象や上限は自治体により異なるため、対象地域・建物の要件・申請時期・交付決定のタイミングを担当課に事前確認します。罹災証明書や見積書、位置図・写真、所有者確認書類などが求められるのが一般的です。
申請から着工までの段取り
保険は「事故連絡→調査→必要書類提出→支払可否判定」の流れ、補助は「事前相談→申請→交付決定→契約・着工→実績報告→交付」の流れが基本です。これに工期を合わせると、資金繰りと工程が安定します。
残置物の分別と搬出計画
火災現場は家財・焼却残渣・建材が混在しやすく、混載のまま搬出すると処分費が嵩みます。分別の方針・仮置きスペース・搬出動線を先に決め、解体と残置物処理を矛盾なく組み立てることが、処分費と小運搬費の圧縮に有効です。
分別の基本方針
解体と一体で撤去する残置物は、契約により産業廃棄物として処理されるのが一般的です(自治体運用により異なる場合があるため、搬出前に処理区分を業者と確認)。家電リサイクル法対象品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)は別ルートでの処理が必要です。金属類は鉄・非鉄で分けると処分費の抑制につながることがあります。
| カテゴリー | 処理の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 家電リサイクル対象 | 指定ルートでの回収・持込 | リサイクル券の手配、型番写真を記録 |
| 金属くず | 鉄・非鉄で分別 | 危険物混入防止、マニフェストの品目整合 |
| 木くず・廃プラ・紙 | 分別解体と併行して集積 | 含水で重量増に注意、飛散防止の養生 |
| 危険物(スプレー缶等) | 内容物確認の上、適正処理 | 爆発・再燃リスク、現場内分離保管 |
| 重要書類・貴金属 | 施主確認後に保管・返却 | 個人情報保護、取り違え防止の封印 |
搬出動線と仮置き計画
前面道路が狭い場合は、小型車リレーや手運搬距離の短縮が鍵です。門扉・カーポートの一時撤去や樹木の伐採で車両進入性を高めると、搬出回数と待機時間を減らせます。粉じん対策として散水設備を確保し、近隣に向けた飛散防止を徹底します。
写真と数量根拠の整備
残置物の山ごとの写真・動画、概算容積(立米)と材料別の内訳を記録し、見積書の数量根拠と一致させます。数量根拠が明確だと追加精算を抑制でき、処分費の予見性が高まるため、結果的に総額を抑えられます。
アスベスト調査の早期実施
アスベスト(石綿)は、調査と必要な届出・除去工程が追加されると日当・仮設費が増えます。有資格者による事前調査を早めに行い、結果を見積と工程に反映させることで、着工後の中断や仕様変更を避けられます。
早期実施のメリット
早期にアスベストの有無・範囲・区分が判明すると、養生仕様・負圧集じん・処分区分などが確定し、見積精度が向上します。周辺住民への説明も具体化でき、クレームによる停止リスクを下げられます。
調査の進め方
図面・改修履歴の確認、現地での目視・採取、必要に応じた分析を行い、調査結果報告書・写真・分析成績書等で裏付けます。建築年だけで判断せず、実物確認を徹底します。
調査対象になりやすい建材の例
| 建材分類 | 部位例 | 備考 |
|---|---|---|
| 吹付け材 | 梁・天井裏の吹付け | 劣化・損傷部は飛散リスクが高く注意 |
| 成形板 | スレート波板・ケイカル板 | 見た目での判別は困難、分析で確認 |
| 内装材 | ビニル床タイル・目地材 | 一部年代で含有例があるため調査対象 |
| 屋根・外壁 | スレート屋根・窯業系サイディングの一部 | 製品・年代により差があるため要確認 |
見積・工程への反映
結果に応じて、隔離養生や集じん機、専用袋での封じ込め、適正な区分での運搬・処分といった追加費用の有無・範囲を確定します。調査前提を曖昧にした見積もりは、後日の追加発注につながりやすいため、工程と費用を事前に固めます。
相見積もりと工程分割
東京の解体は現場条件による費用差が大きく、相見積もりの比較軸を揃えないと判断を誤ります。「工法・養生仕様・搬出条件・分別レベル・アスベスト対応・残置物の範囲」を共通前提にして比較することが基本です。
比較の観点と確認ポイント
| 比較観点 | 確認ポイント |
|---|---|
| 工法・機械 | 手壊しと重機の使い分け、重機サイズ、仮設足場の要否 |
| 養生仕様 | 防炎シート・防音パネルの仕様、高さ、近隣側の増強 |
| 搬出条件 | 前面道路幅・車両サイズ・積替え回数・誘導員の配置 |
| 分別レベル | 分別解体の範囲、木くず・がれき・金属の仕分け方針 |
| アスベスト対応 | 事前調査の実施状況、除去・処分の含み、届出の役割分担 |
| 残置物の範囲 | 家財撤去の有無、数量根拠、家電リサイクルの取扱い |
| 外構・地中 | 塀・土間・樹木、地中障害の扱い(見つかった場合の単価) |
| 証憑・管理 | マニフェストの発行、写真提出、近隣対応の範囲 |
現地調査時に伝えるべき条件
前面道路の幅員・交通量・学校や病院の有無、電線高さ、隣接建物の構造と離れ、既存門扉やカーポート、井戸・浄化槽・擁壁、ガスメーター・電気引込の状況など、費用に影響する情報を事前共有します。業者間で前提条件が一致しているほど、見積比較が正確になるため、写真・寸法・図面を揃えましょう。
工程分割の活用
「残置物撤去→アスベスト除去→本体解体→外構撤去→整地」と工程を分けると、専門性と段取りが明確になり、リスクの切り分けができます。一方で仮囲いの再設置や重複搬入が発生することもあるため、分割する場合は範囲・引渡条件・写真記録の責任分担を契約で明文化します。
道路条件の改善と仮囲い計画
都内は前面道路の制約が工期・費用に直結します。「進入性の改善」と「必要十分な仮囲い」の両輪で、待機時間と過剰仮設を減らすのがコスト最適化の基本です。
道路条件の事前整備
門扉・フェンス・カーポート・樹木など私有物の一時撤去で、車両の進入幅と旋回余地を確保します。歩行者動線と資材搬出動線を分ける計画とし、工事車両の待機場所・ルートを明示して近隣トラブルを未然に防ぎます。
道路使用の最適化
搬出時間帯の選定、誘導員の最小必要人数・配置、積込回数の平準化で、車両の滞留と人件費のロスを抑えます。必要に応じて時間帯を分け、学校の登下校時間を避けると作業停止のリスクを下げられます。
仮囲い・養生の最適化
防炎性能を有する養生シートや防音パネルを、周辺環境に応じた「必要十分」な仕様で計画します。隣地が近接し風が抜けにくい場所では、シートのたわみ・外れを防ぐ固定方法を選び、粉じん抑制の散水と併用します。
| 課題 | 費用への影響 | 具体策 |
|---|---|---|
| 前面道路が狭い | 小運搬・待機費用が増加 | 私有物の一時撤去、小型車リレー、積込位置の固定化 |
| 交通量が多い | 誘導員増・作業中断のリスク | 時間帯調整、作業範囲の明示、掲示強化 |
| 近隣が至近 | 養生仕様の増強・クレーム対応 | 防炎シート・防音パネルの適用、散水・清掃の頻度管理 |
道路条件と仮囲いは着工後の変更が大きなコスト増要因です。計画段階で現地実測・写真記録を行い、見積書の前提条件に反映させておくと追加費の発生を抑えられます。
2025年最新ルール 東京の解体手続き

2025年時点で東京都内で火事後に建物を解体する場合、最低限おさえるべき事務手続きは「建設リサイクル法の届出」「石綿(アスベスト)関連の事前調査・報告・作業届」「騒音・振動関係の特定建設作業届」の三本柱です。火災が原因の解体であっても、これらの届出や電子申請は原則として免除されません。着工の前に期限・提出先・義務者(発注者か元請か)を正確に押さえ、重複のない計画で進めることが、費用や工期のロスを防ぐ最大の防御になります。
建設リサイクル法の電子届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法、いわゆる建リ法)は、解体工事で発生するコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材などの特定建設資材について、分別解体・再資源化を義務づける法律です。東京都内の建物解体では、延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、着工7日前までに届出が必要となります。
届出書は工事場所を所管する区市町村に提出します。東京都および多くの区市町村は電子申請(オンライン)に対応しており、必要書類のPDF添付・押印省略に対応する窓口も増えています。電子申請の可否・添付要件は区市町村で異なるため、実際の提出先(工事場所の区役所・市役所・町村役場)の様式・入力項目に合わせて準備してください。
| 観点 | 内容(東京都内の解体工事) |
|---|---|
| 届出対象 | 延べ床面積80㎡以上の建築物の解体工事(火災で損傷した建築物も含む)。 |
| 届出者 | 発注者(建築主・所有者等)。元請業者へ委任して代理提出可(委任状を添付)。 |
| 提出先 | 工事場所の区市町村(東京都特別区・市・町村)。 |
| 提出期限 | 工事着手の7日前まで。 |
| 主な添付・記載 | 分別解体等の計画書、工程表、付近見取図・配置図・平面図、再資源化の実施方法、元請の建設業許可または解体工事業登録の写し、委任状(代理時)。 |
| 電子化 | 多くの区市町村で電子申請に対応。受理通知・補正依頼の連絡は電子で返送される場合あり。 |
| 現場義務 | 標識の掲示、分別解体の徹底、再資源化先の確保、再資源化が困難な場合の合理的理由の整理。 |
| 監督・違反時 | 指導・勧告・命令・公表等の監督処分あり。契約書・届出書の不備や分別未実施は是正対象。 |
併せて、発生した産業廃棄物については廃棄物処理法に基づくマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存が必要です。石綿含有廃棄物などの特別管理産業廃棄物は取扱いが厳格で、収集運搬・処分の許可業者への委託、マニフェストの適切な運用(電子マニフェストの活用を含む)が不可欠です。
なお、解体工事を請け負う業者は、建設業法の「解体工事業」の許可または東京都の解体工事業登録が必要です。契約前に許可・登録の有無を確認し、届出書の添付資料に反映させると手戻りを防げます。
アスベスト事前調査報告の電子申請
大気汚染防止法の改正により、2023年10月以降、解体・改修工事では石綿(アスベスト)含有建材の有無にかかわらず、事前調査とその結果の電子報告が原則必須となりました。東京都内でも同様で、火災後の解体であっても事前調査・報告が必要です。
事前調査は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者など)が設計図書・現地確認・分析結果に基づき実施します。元請業者は電子報告システムを用い、着工前に調査結果を所管へ報告します。報告後に石綿の存在が判明した場合は、速やかに計画を見直し再報告します。
| 観点 | 内容(東京都内の解体工事) |
|---|---|
| 対象工事 | すべての解体工事(規模を問わず)。 |
| 調査者 | 有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)が実施。 |
| 報告者 | 元請業者(発注者ではなく元請が義務者)。 |
| 提出先 | 東京都知事(所管窓口:東京都または工事場所の区市町村)。 |
| 提出期限 | 工事着手前に電子報告(システムへの入力・添付)。 |
| 主な記載・添付 | 調査方法・範囲、確認資料、分析結果、石綿等の有無・種類・含有率、掲示内容、発注者・元請の情報。 |
| 現場掲示 | 石綿の有無、工法、期間、責任者・連絡先等の掲示義務。 |
| 違反時 | 報告未実施・虚偽報告・飛散防止措置違反は、行政処分や罰則の対象。 |
石綿含有建材がある場合は、別途の手続きが加わります。第一に、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出(少なくとも14日前)を行います。第二に、労働安全衛生法・石綿障害予防規則に基づき、除去等の作業計画の届出(おおむね14日前、所轄の労働基準監督署)を提出します。作業では、隔離養生、負圧集じん機の設置、湿潤化、二重梱包・区分保管、許可業者による収集運搬・処分など、法令で定める飛散防止措置を実施します。
廃棄段階では、特別管理産業廃棄物(石綿含有廃棄物)の基準に従い、容器・表示・保管・運搬・最終処分までトレーサビリティを確保します。マニフェストは適切に交付・回収し、関係書類を保存してください。
騒音規制法 振動規制法 東京都の環境確保条例
解体工事はブレーカやコンクリート圧砕機などの使用により大きな騒音・振動を伴います。東京都内でこれらの機械を用いて行う工事は、多くが「騒音規制法」「振動規制法」における特定建設作業に該当し、工事着手の7日前までに特定建設作業実施届出を工事場所の区市町村へ提出します。東京都環境確保条例は上乗せ・横出しの基準を設けており、作業時間帯の制限、日曜・祝日の原則作業自粛、現場標識の掲示、苦情対応窓口の明示、粉じん飛散防止などの要求が加わることがあります。
| 観点 | 内容(東京都内の解体工事) |
|---|---|
| 対象 | ブレーカ、杭抜き機、コンクリート破砕機などを用いる特定建設作業。 |
| 届出者 | 元請業者。 |
| 提出先・方法 | 工事場所の区市町村。多くの自治体が電子申請に対応。 |
| 提出期限 | 工事着手の7日前まで。 |
| 主な記載 | 機械の種類・台数、使用期間・時間帯、作業工程、騒音・振動低減措置、連絡責任者。 |
| 現場義務 | 標識掲示、近隣周知、散水・養生などの粉じん対策、必要に応じ騒音・振動の測定。 |
| 条例での上乗せ | 時間帯の制限や周知方法などの具体要件は区市町村で異なる。計画段階で所管に確認。 |
| 違反時 | 改善命令、勧告、公表等の行政措置。重大な違反では罰則の対象。 |
火災後の解体は近隣が敏感になっていることが多く、届出の適正化に加え、周知書配布・掲示・苦情窓口の一本化・作業時間の順守を徹底することが、トラブル回避と工期短縮の鍵になります。騒音・振動・粉じんの抑制策は届出書面に記載した計画と現場運用を一致させ、是正指導を受けないように管理しましょう。
区市町村の支援制度を探す

東京都内で火事後に解体を検討する際は、まずお住まいの区市町村が行う「除却(解体)費用の補助」や「空き家対策の支援」を確認します。制度名称や助成率・上限額、受付時期は自治体ごとに異なるため、住所地の役所での事前相談が出発点です。ほぼすべての補助は交付決定前の着工が不可(着工=契約・工事開始)なので、見積もり取得および申請→交付決定→契約・着工の順序を厳守してください。
以下は東京都内で実施例の多い支援類型の全体像です。対象や必要書類には共通点がある一方、区域指定(不燃化特区など)や建物の状態(老朽・危険度・空き家認定)で適用制度が分かれます。
| 制度類型 | 主な対象ケース | 管轄の例 | 主な要件・根拠資料 | 支援の形 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不燃化特区の除却補助 | 木造密集市街地(木密)の指定区域内で老朽・狭小・路地奥などの建物を解体 | 各区の都市整備部・防災まちづくり担当 | 対象区域の確認、建物の老朽度・危険性、所有者確認、現況写真 | 解体費の一部補助(標準単価方式または実費の一定割合) | 区域外は対象外。セットバックや建替え方針の確認が重要 |
| 老朽危険家屋の除却補助 | 倒壊や延焼拡大のおそれがある老朽家屋の解体(火事で損傷した建物を含む場合あり) | 各区市町村の建築指導課・住宅課 | 危険度評価(職員現地確認等)、建物図面・写真、所有者同意 | 解体費の一部補助 | 危険度の基準や補助率は自治体ごとに異なる |
| 空き家対策の解体補助 | 長期未利用・管理不全の空き家、特定空家等への移行を予防する除却 | 各区市町村の空家対策担当(都市整備部・生活環境部など) | 空き家の実態確認、管理状況、相続関係書類、近隣への影響 | 解体費の一部補助、事前相談・助言 | 相続未登記は同意・権利関係整理が必要 |
| 大規模災害時の公費解体 | 地震・台風等の大規模災害で自治体が実施する公費解体 | 区市町村(災害対策本部設置時) | 罹災証明書(災害区分)、被害認定 | 公費での解体(所有者負担なし) | 単独の火災は通常対象外 |
共通して、申請に添付する見積書は「建設業許可」または「解体工事業登録」がある解体業者のものが求められ、アスベスト事前調査・建設リサイクル法の届出等の適法性がチェックされます。年度予算の枠があるため、募集開始(原則4月)直後に相談→仮申請・予約が安全です。
不燃化特区 木密地域の除却補助
東京都と区が連携する「不燃化特区」は、木造密集市街地(木密)で延焼・避難の危険性を下げるための重点整備制度です。区域内で老朽家屋を除却して防災性を高める場合、解体費の補助を受けられる可能性があります。火事で損傷した建物でも、区域・要件に合致すれば対象になり得ます。
対象区域は住所と地番で確認します。各区の都市整備部(防災まちづくり・市街地整備・不燃化担当など)が最新の区域図や運用要綱を案内します。路地状敷地や接道条件が悪い場所では、セットバック(道路後退)や空地化による延焼遮断に資することが評価される運用が一般的です。
| 確認事項 | 具体例 | 提出書類の例 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 区域指定 | 不燃化特区・重点整備方針内か | 区域図の写し、担当課確認記録 | 境界付近は筆界・地番の確認を厳密に |
| 建物の状態 | 老朽・傾き・火災損傷の有無 | 現況写真、簡易診断結果、消防の焼損記録 | 危険度の判断基準に適合しているか |
| 所有・権利関係 | 単独所有・共有・借地 | 登記事項証明書、同意書、賃借関係書類 | 共有者や底地権者の同意が必要 |
| 工事の適法性 | 解体工事業登録、各種届出 | 業者登録写し、アスベスト事前調査書、建設リサイクル法届出 | 届出の電子申請期限を逆算して工程に組み込む |
| 費用の範囲 | 本体解体・付帯撤去・産廃処分 | 内訳明細付き見積書、数量根拠 | 新築準備費や設計費は対象外になりやすい |
申請の流れは概ね、事前相談→現地確認→申請(見積書・写真・図面等)→交付決定→契約・着工→完了検査→実績報告→補助金交付です。交付決定通知前に契約・着工した場合、補助対象外になるのが通例です。募集は年度ごと・先着順の運用が多いため、火災直後でもまずは区域要件の可否を早めに確認しましょう。
老朽危険家屋 空き家対策の補助
不燃化特区の外でも、区市町村は「老朽化した危険家屋の除却」や「空き家対策」による解体費補助を設けています。火事で損傷した建物が倒壊等のおそれを生じた場合、危険度判定の結果により補助対象となることがあります。長期未利用の空き家については、管理不全の深刻化を予防する観点から除却費の一部が支援される例が多数あります。
| 制度 | 主な対象 | 必要書類の例 | 採択のポイント | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 老朽危険家屋除却補助 | 倒壊・延焼の危険がある既存建物(火災により危険度が増したケースを含む) | 現況写真、危険度評価資料、登記事項証明書、所有者本人確認書類 | 危険度基準への適合、近隣安全への寄与 | 自治体ごとに評価基準や対象費目が異なる |
| 空き家解体(管理不全・特定空家等対策) | 長期未利用・適切な管理が行われていない空き家 | 空き家であることの疎明資料、管理状況申出書、相続関係書類(場合により) | 周辺の生活環境の改善効果、所有者の管理・改善意思 | 相続未登記・共有は合意形成に時間がかかるため早期に整理 |
いずれの制度でも、補助対象となる費用は「本体解体」「付帯撤去(門塀・樹木・小屋・地中障害の撤去など)」「産業廃棄物の処分・運搬」が中心です。アスベスト含有建材が見込まれる場合は、事前調査報告と適正な分別・処理費を見積りに反映して申請してください。複数見積りの提出や、自治体が示す標準単価に基づく上限設定が用いられることがあります。
申請に先立ち、次の事項を整理してから相談すると審査がスムーズです。
- 建物の所在地・地番・延床面積・構造(木造・鉄骨造など)
- 火災の発生日時・損傷状況・消防による焼損記録の有無
- 所有者・共有者・借地権者の一覧と連絡先(同意の見込み)
- 解体後の活用方針(更地化、再建、駐車場化など)
- 解体業者の登録状況(建設業許可・解体工事業登録)と見積内訳(数量根拠・写真)
市税・都税の滞納があると補助の対象外となる取扱いが多いため、未納があれば納付計画を早めに整えると確実です。募集期間・予算枠・併用可否(例:他の除却補助や再建補助との重複)は自治体で異なるため、担当課の指示に従ってください。
相談窓口 都庁と各区役所
東京都内で火事後の解体に関する補助・手続の相談先は次のとおりです。初回は電話または窓口で「住所・地番」「火災の状況」「解体の予定時期」を伝え、対象制度の有無と申請順序、必要書類を確認すると確実です。
| 相談先 | 主な相談内容 | 用意するとよい情報 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 各区市町村役所(都市整備部・建築指導課・空家対策担当) | 除却補助の制度案内、区域指定の確認、申請方法・スケジュール | 住所・地番、建物概要、現況写真、概算見積、所有者情報 | 不燃化特区か否か、老朽・空き家制度の対象可否を同時に確認 |
| 各区市町村の税務担当(資産税課 等) | 解体後の土地課税の取扱い、家屋滅失に伴う手続の案内 | 家屋番号、登記事項証明書、解体予定日 | 補助金と税の手続は別ルート。時系列を整理して相談 |
| 東京消防庁(所管消防署) | 火災に関する罹災証明書の申請・発行 | 火災発生日時・場所、被害状況、本人確認書類 | 火災の罹災証明は消防署が窓口。補助申請で提出を求められることがある |
| 東京都(都市整備局・環境局 等) | 不燃化に関する都の方針・区域の考え方、アスベスト事前調査報告の手続 | 工事規模、構造、想定する工期、調査結果(判定表) | 石綿事前調査・大気汚染防止法の報告は都または区市町村の所管に従う |
相談時は、担当課から示される「申請書式」「記載例」「提出期限」を必ず入手し、工程表に落とし込んでください。郵送・電子申請が利用できる自治体も増えていますが、現地確認(立会い)や写真の撮影条件などは自治体指定に合わせる必要があるため、事前連絡のうえで進めるとトラブルを避けられます。
最後に、補助は「公共性(延焼危険の低減・避難路の確保)」が重視されます。路地奥や狭隘道路沿いの敷地では、解体後の空地化・セットバック・再建計画の整合を含めて提案すると採択可能性が高まる傾向があります。申請は所有者本人が行うのが原則ですが、解体業者や行政書士に委任できる手続もあるため、作業分担を決めてスケジュール管理を徹底しましょう。
見積もりと契約の実務

火災後の解体でトラブルやムダなコストを避ける鍵は、「数量の根拠を可視化し、内訳を標準化し、契約と変更合意を必ず書面で残す」ことです。この章では、東京での解体工事を前提に、見積書作成に必要な写真・図面・数量の取り方、内訳項目のそろえ方、そして契約・変更手続きの実務までを一気通貫で解説します。
数量根拠 写真 図面の取り方
見積の精度は「現況の把握」と「記録の質」で決まります。火災現場は構造体の損傷や残置物、すす・消火水による重量増など不確定要素が多いため、現地調査の段階で客観的な根拠資料を整えましょう。
まずは、以下の撮影チェックリストを参考に、第三者が見ても数量と施工制約が判断できるレベルまで写真を撮ります。
| 撮影部位 | 目的 | 撮り方のポイント | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 外観四方向(遠景・近景) | 建物規模・高さ・隣地状況の把握 | 敷地全景→各面の立面が分かる角度で | 越境物・共有塀・隣地窓の位置を必ず入れる |
| 前面道路・間口 | 車両進入・道路使用の要否判断 | 幅員表示・道路標識・曲がり角のRを含める | 電柱・消火栓・街路樹など支障物の距離を測る |
| 電線・引込・メーター類 | 仮設・撤去手配と安全計画 | 電気・ガス・水道・通信の位置と状態を近接撮影 | 封印の有無・残圧の注意喚起を記録 |
| 内部各室・天井裏・床下 | 焼損度合いと手壊し範囲の把握 | 梁・柱の炭化状況、床の抜けや沈下を撮影 | 立入危険箇所は望遠で。安全帯・ヘルメット必須 |
| 仕上材の拡大 | アスベスト含有の可能性確認 | サイディング裏印字、屋根スレート端部、保温材断面 | 石綿含有建材調査の参考。破砕は行わない |
| 残置物 | 分別・搬出計画と数量化 | 室ごとに山の体積が分かる角度で複数枚 | 危険物(スプレー缶・バッテリー等)は別撮影 |
| 外構・敷地 | 付帯工事範囲の特定 | ブロック塀・土間・庭石・樹木の全体と寸法 | 境界標・越境樹木の有無を明示 |
図面は「正確な測量図」まで求めずとも、見積に必要な寸法が読み取れれば十分です。以下の要領で簡易図面を用意します。
- 配置図(必須):敷地寸法、建物外形、前面道路幅員、方位、間口、搬入ルート。
- 平面略図(各階):外寸、主要間仕切り、階段位置、増改築の有無、バルコニーや下屋の寸法。
- 立面・高さ情報:軒高・最高部、基礎天端、擁壁・高低差。
数量算定で用いる代表的な単位と根拠は次のとおりです。
| 工種 | 主な数量単位 | 数量の根拠資料 |
|---|---|---|
| 本体解体(建物) | m²(延床面積)、坪 | 登記事項、確認申請図、現地実測 |
| 基礎・土間 | m³(体積)、m² | 基礎形状スケッチ、立上り・スラブ厚の実測 |
| ブロック塀・擁壁 | m²(見付け)、m | 高さ・厚み・長さの実測 |
| 残置物 | m³(体積) | 室別の山の幅×奥行×高さ |
| 樹木 | 本数、胸高直径(cm)、根鉢径 | 幹径実測、位置図 |
| 運搬・処分 | t(重量)、m³ | 搬出計画、処理場の受入単位 |
アスベスト事前調査は、調査結果報告書(石綿含有建材調査者による)を見積根拠に反映させます。火災で材質が判別しづらい場合は、現地試料採取(安全確保の上)や竣工図・仕様書で裏付けを取り、結果が確定するまで該当部を「別途・保留」と明記します。
数量・写真・図面は「見積書に添付」してセットで提出してもらうと、内訳の比較が容易になり、後日の追加精算トラブルを大幅に減らせます。
内訳項目の標準
解体の見積は業者ごとに表記が異なりがちです。比較可能性を高めるため、下記の標準区分に沿って内訳をそろえ、各項目に「単位・数量の根拠・含む/含まない」を明記してもらいましょう。
| 区分 | 代表的な項目 | 単位例 | 主な含まれないもの |
|---|---|---|---|
| 仮設・養生 | 仮囲い、防炎・防音シート、足場、散水設備、粉じん対策 | m、m²、式 | 道路使用料、近隣借地代 |
| 本体解体 | 構造体解体、内装解体、屋根・外装撤去 | 坪、m²、式 | アスベスト除去、基礎撤去 |
| 付帯解体 | 基礎・土間、ブロック塀、カーポート、物置、庭石、樹木 | m³、m²、m、本、式 | 地中障害(未知物)、井戸・浄化槽の埋戻し処理 |
| 運搬・処分 | 分別積込、搬出、処分費、積替保管 | t、m³、式 | 特別管理産業廃棄物の特別処理 |
| 調査・届出 | アスベスト事前調査、建設リサイクル法届出、近隣説明資料 | 式 | 官公庁手数料、道路使用・占用の申請手数料 |
| 道路・警備 | 道路使用・占用関連、交通誘導員、保安資機材 | 日、式 | 警察協議に伴う追加待機・延長 |
| 原状回復 | 整地、砕石敷、残土搬出、仮囲い撤去 | m²、m³、式 | 地盤改良、汚染土壌対策 |
| 諸経費 | 現場管理費、一般管理費、保険料 | 式 | 不可抗力による損害の補填 |
本体解体費 坪単価
本体解体費は便宜上「坪単価」で示されることが多いものの、実際の手間は構造・階数・焼損度合い・手壊し割合・重機搬入の可否・前面道路条件などで大きく変動します。坪単価はあくまで目安とし、数量と条件を必ず明記します。
| 構造 | 主な解体方法 | 数量の取り方 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 重機併用の分別解体、狭小は手壊し増 | 延床m²(坪)+下屋・バルコニー | 焼損で炭化・脆弱化。散水・飛散防止を強化 |
| 軽量鉄骨造 | 鉄骨切断+パネル分別 | 延床m²(坪) | 外装材の含有調査(石綿の可能性)を反映 |
| 鉄骨造 | 柱梁切断・転倒防止計画 | 延床m²(坪)+構造部重量感 | 高所作業・ガス切断の安全管理を強化 |
| RC造 | ブレーカ・クラッシャによる破砕 | 延床m²(坪)+壁・スラブ厚 | 騒音・振動規制に合わせ時間帯と工法を調整 |
坪単価に「含まれる/含まれない」の代表例は次のとおりです。含む例:躯体・屋根・内装の撤去、簡易散水、一次分別。含まれない例:アスベスト除去、外構・付帯、基礎撤去、残置物処理、地中障害、長距離手運び、夜間作業、道路使用・警備。
坪単価だけで比較せず、前提条件(手壊し割合・搬入車種・作業時間帯・分別レベル)を書面化した上で比較するのが重要です。
付帯工事費 外構 樹木 地中障害
付帯工事は敷地条件で差が出やすい領域です。項目ごとに単位と数量根拠を揃え、未知の地中障害は「別途精算(単価契約)」にしておくのが実務的です。
| 項目 | 単位 | 数量根拠 | リスク・備考 |
|---|---|---|---|
| 基礎・土間コンクリート | m³、m² | 厚さ×面積、立上り長×高さ×厚 | 配筋量・杭の有無で手間が変動 |
| ブロック塀・擁壁 | m²、m | 高さ・厚み・延長 | 控え壁・基礎の深さを試掘で確認 |
| カーポート・物置 | 式 | サイズ・基礎有無 | メーカー品はボルト結合・分解の手間を考慮 |
| 庭石・景石 | 式、t | 概寸から重量概算 | クレーン有無、搬出経路の養生が必要 |
| 樹木伐採・伐根 | 本、胸高直径 | 幹径、根鉢径 | 越境枝・電線近接は追加養生・高所作業 |
| 井戸・浄化槽 | 式 | 位置・口径・深さ | 埋戻し材・衛生配慮が必要 |
| 地中障害撤去 | t、m³、式 | 現地発見都度の実測・試掘結果 | 未知物は単価契約・写真根拠で別途精算 |
地中障害は契約前に「試掘(数か所)」を見積に含め、発見時の精算単価と承認フローを特約で明記しておくと、工期・費用のブレを抑えられます。
産業廃棄物処分費 運搬費
処分費は分別レベル・搬出条件・受入先によって構成が変わります。見積では「廃材区分ごとの単位(tまたはm³)」と「運搬の条件(車種・距離・直搬/積替保管)」を具体化してください。
| 廃材区分 | 代表例 | 主な単位 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| コンクリートがら | 基礎・土間・擁壁 | t、m³ | 鉄筋分離、受入場のサイズ制限 |
| 木くず | 構造材・内装材 | t、m³ | 含水率増(消火水)で重量増加に注意 |
| 金属くず | 鉄骨・サッシ・配管 | t | 分別回収で混合廃棄物を削減 |
| ガラス・陶磁器くず | サッシガラス・衛生機器 | t、m³ | 飛散防止養生を徹底 |
| 廃プラスチック類 | 外装材・断熱材 | t、m³ | 発じん・臭気対策、焼損材の扱いに注意 |
| 石膏ボード | 内装下地 | t、m³ | 専用分別。水濡れで重量増・処理条件変化 |
| 石綿含有建材等 | 成形板・スレート等 | t、m³、式 | 調査結果に応じ法区分と処理方法を契約書で特定 |
| 混合廃棄物 | 分別困難な混合物 | t、m³ | 分別比率・発生最小化の方針を明記 |
運搬費は「車種(2t/4t/大型)」「回数」「積込方法(手積み/機械積み)」「待機・迂回の有無」で構成します。道路条件が厳しい都内では、車種制限・一方通行・時間帯規制を見積条件に反映させましょう。
処分については、処分場・運搬業者との産業廃棄物処理委託契約、収集運搬・処分の許可証の写し、産業廃棄物管理票(マニフェスト:紙または電子)を見積・契約段階で確認します。電子マニフェスト(JWNET等)を利用する場合は、運用方法(発行・確認手順)も合意しておくと管理がスムーズです。
火災現場では「水濡れ・すす付着」により重量が増えがちです。処分費は重量精算のルール(計量票の提出、単価、上限額の有無)を特約で明記しておくと安心です。
諸経費 現場管理費
諸経費はブラックボックス化しやすい項目です。内訳と根拠を明示してもらい、内容の妥当性を確認しましょう。代表的な構成は次の通りです。
- 現場管理:現場監督人件費、工程・品質・安全管理、近隣対応。
- 共通仮設:仮設水道・電気、仮設トイレ、保安資機材、清掃費。
- 保険・補償:請負業者賠償責任保険、建設工事保険(解体対象の範囲)、労災関係。
- 一般管理費・利益:本社経費、経理・法務、見積・調達コスト等。
「諸経費一式」ではなく、少なくとも「現場管理」「共通仮設」「保険」「一般管理費・利益」に区分して提示してもらうと、内容の過不足が見えます。
契約書 変更合意のルール
工事請負契約は必ず書面(電子契約可)で締結し、火災後特有の不確定要素(原因調査の完了時期、アスベストの結果待ち、地中障害)に備えた特約を入れておきます。以下のチェックリストで主要条項を確認しましょう。
| 条項 | 内容の要点 | チェック書類・根拠 |
|---|---|---|
| 工事名称・場所・範囲 | 解体範囲の特定(本体・付帯・整地の線引き) | 現況図・写真、範囲図 |
| 工期・作業時間 | 開始条件(原因調査完了・保険会社承認等)と終了条件(更地引渡) | 工程表、関係機関の通知 |
| 請負代金・支払条件 | 着手・中間・完了の出来高と検収書類 | 検収基準、請求書様式 |
| 分別解体・処分 | 分別方針、受入先、マニフェスト運用 | 許可証写し、委託契約、受入条件 |
| アスベスト対応 | 事前調査結果、除去工事の区分と費用扱い | 調査報告書、届出控え |
| 行政届出 | 建設リサイクル法、石綿事前調査報告等の届出・報告体制 | 届出書控え、提出スケジュール |
| 道路・近隣対応 | 道路使用・占用、交通誘導員、事前周知の範囲 | 申請資料、近隣配布文 |
| 安全衛生 | 危険作業の手順、保護具、緊急時対応 | 安全計画、KY資料 |
| 引渡・検査基準 | 更地の定義、ガラ残・杭頭の扱い、写真提出 | 完成写真、試掘確認記録 |
| 保険・賠償 | 第三者賠償・施設損壊の補償枠 | 保険証券写し |
| 変更・中止 | 追加・減額の手順、単価・歩掛、待機費の扱い | 変更見積、単価表、協議記録 |
| 下請・再委託 | 再委託の可否・条件、現場常駐体制 | 体制表、作業員名簿 |
| 反社・秘密保持・紛争解決 | 基本条項の明記と準拠法・管轄 | 各条項の条文化 |
口頭合意は原則不可。追加・変更は「理由・範囲・数量・単価・影響工期」を記した見積と写真根拠を添え、書面(電子含む)で承認してから着手します。
変更合意(バリエーション)の実務フロー
- 発見・発生:地中障害、追加要望、調査結果の確定など。
- 安全確保・一時停止:影響範囲の立入禁止、仮設の見直し。
- 記録:写真・動画・実測、位置図・数量のスケッチ。
- 見積:既存の単価表を優先、なければ歩掛根拠を提示。
- 承認:メールまたは電子契約で相互承認(差戻し履歴を保存)。
- 施工・検収:出来高写真、計量票・マニフェスト、日報で照合。
追加・変更の精算を円滑にするため、あらかじめ「単価表(レートカード)」を契約書別紙に入れておくと便利です。
| 工種 | 単位 | 単価設定の考え方 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人力搬出(室内) | m³ | 階段搬出の距離・階数を考慮 | エレベーター不可時は係数適用 |
| 交通誘導員 | 人日 | 時間帯・延長・土日祝の割増ルール | 規制図の変更有無で調整 |
| 地中コンクリート撤去 | t、m³ | 厚み・鉄筋量・破砕難易度 | 試掘結果を根拠にする |
| 混合廃棄物処分 | t | 含水率・含有物の制限 | 計量票で精算 |
| 仮設養生追加 | m²、式 | 材料・架設・撤去の三位一体 | 期間延長の扱いも明記 |
検収・引渡では、撤去前後写真、出来高内訳、マニフェスト控え、計量票、取壊し証明書を取りまとめ、滅失登記に使える形で受領します。支払いは出来高・検収書類連動とし、精算条件(締日・支払日・差異調整)を契約書に明記します。
契約は紙・電子いずれでも構いません。電子契約の場合法的有効性を担保できる方式(電子署名等)とし、変更合意も同一プラットフォームに集約して保存します。これにより、助成金や火災保険の審査で求められる根拠提示にも迅速に対応できます。
工程と現場管理

東京での火事後の解体は、密集市街地や狭小道路が多いという地域特性のため、工程(スケジュール)と現場管理(安全・品質・周辺対策)を事前に統合して設計することが重要です。現場条件の把握、近隣合意形成、許認可の期日管理、粉じん・騒音の抑制、交通導線の確保を同時並行で進めると、工期短縮とトラブル回避が両立します。
実務上、本体解体の着手は「消防による原因調査・危険確認」「保険会社の損害調査」「アスベスト事前調査と届出」の完了を前提とし、関係書類をそろえたうえで行います。また、東京都の環境確保条例や各区市の指導要綱に基づき、作業時間帯や粉じん・騒音の抑制措置を計画段階から織り込みます。
以下は、火災後解体の標準的な流れを、現場管理の観点で要点化したものです。現場の規模・構造・道路条件により入れ替えや並行実施が生じます。
| フェーズ | 主な内容 | 主担当 | 主要書類・許認可 | 安全・品質の要点 |
|---|---|---|---|---|
| 事前準備 | 現地調査、施工計画書・工程表、仮設計画、搬出ルートと待機場所の設計 | 現場代理人・主任技術者 | 建設リサイクル法の届出控、アスベスト事前調査報告控、近隣案内文 | 焼損部の倒壊リスク評価、支保工の要否、資機材の搬入条件を確認 |
| 近隣合意形成 | 戸別挨拶・文書配布、工事説明、問い合わせ窓口の明示 | 発注者・解体業者 | 工事概要看板、緊急連絡先掲示 | 作業時間帯・散水・清掃頻度・駐停車計画を共有 |
| 仮設・養生 | 防音パネルや防炎シート設置、仮囲い、ゲート、粉じん対策設備 | 解体業者 | 道路使用許可(必要時)、道路占用許可(越境時) | 隙間目地のテーピング、転倒防止、歩行者分離と誘導計画 |
| ライフライン対応 | 電気・ガス・水道・通信の停止と撤去立会い | 発注者・供給事業者 | 停止申請控・立会い記録 | 感電・ガス漏えいの防止、メーター撤去の確認 |
| 有害物対応 | アスベスト除去・調整、焼損材の分別と管理 | 石綿作業主任者・専門業者 | アスベスト関係書類、作業計画・作業記録 | 負圧養生・集じん・清掃、非関係者立入禁止の徹底 |
| 内装分別・手壊し | 残置物搬出、内装材の分別解体、手ばらしでの上屋軽量化 | 解体業者 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 散水で粉じん抑制、落下防止、釘・破片対策と清掃 |
| 本体解体 | 重機・小割機による解体、構造材の分別、積込み | 解体業者 | 道路使用許可(積込時)、運搬許可(許可車両) | 低騒音型機械の選定、散水・防音、防振マットの活用 |
| 運搬・処分 | 積込み・搬出、適正処分・再資源化 | 運搬・処分業者 | マニフェスト、受入・処分証明 | 飛散・落下物防止、タイヤ洗浄、路面清掃 |
| 地中確認・整地 | 基礎撤去、埋設物・地中障害の確認、転圧・整地 | 解体業者 | 発見時の協議記録・変更合意書 | 想定外障害物の安全な撤去手順、追加費用の合意 |
| 仮設撤去・引渡し | 仮囲い撤去、最終清掃、整地確認、写真引渡し | 解体業者・発注者 | 工事記録写真、完了書、マニフェスト最終控 | 近隣の点検同行、苦情の最終確認と是正 |
道路占用・道路使用を伴う作業(重機搬入、積込みのピーク日、仮設材搬入など)は工程のクリティカルパスになりやすいため、許可期間と警備配置、車両手配を「日単位」で前倒し管理します。
近隣挨拶と掲示
火災後の解体は心理的な負担や臭気・粉じんの不安が大きく、東京の密集地では隣接建物の管理組合や商店、学校・保育園など利害関係者も多岐にわたります。着工前に余裕をもって戸別訪問し、工期・作業時間帯・散水や清掃の頻度・道路利用計画・緊急連絡先を丁寧に説明しましょう。発注者と施工者の窓口を明確にし、苦情の一次受付から是正までの流れを共有しておくと、対応が迅速になります。
案内文には、工事名称、場所、工期、標準作業時間帯(各区市の指導要綱に合わせる)、休工日、想定される騒音・振動のピーク工程、粉じん抑制(散水・ミスト)、路面清掃の時間帯、道路使用の有無、発注者・施工者名、現場代理人名、24時間の緊急連絡先、許可・届出の概要を記載します。屋外には工事概要看板と緊急連絡先、関係票類を掲示し、進捗や工程変更が生じた場合は掲示と回覧で更新します。
| 掲示物 | 掲示場所 | 目的・根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 工事概要看板(工期・時間帯・連絡先) | 出入口ゲート外側・見通しの良い位置 | 近隣への周知・問い合わせ対応の明確化 | 工程変更時に日付と内容を更新 |
| 解体工事業者登録票 | 出入口付近 | 施工者の適格性表示 | 見やすい高さ・文字サイズで掲示 |
| 建設業の許可票(該当時) | 出入口付近 | 請負体制の透明性 | 元請表示の整合性を確認 |
| 労災保険関係成立票 | 現場内掲示板 | 労働安全衛生の確認 | 有効期間の表示 |
| 道路使用許可書(写) | 路上作業時に現場携行・掲示 | 警察官からの提示要請に対応 | 期間・場所・作業内容の適合を確認 |
| 作業主任者名(石綿・足場等) | 作業場所の入口 | 労働安全衛生上の責任者明示 | 資格の有効性を確認 |
| 粉じん抑制方法の案内 | ゲート付近 | 散水・ミスト・清掃計画の可視化 | 洗濯物配慮の呼びかけを併記 |
| 緊急連絡先(24時間) | ゲート・掲示板 | 夜間・休日の対応窓口 | 担当者の交代時も即時更新 |
挨拶の優先順は、敷地に隣接する両隣・裏・向かい・斜向かいを先に、その後、同一街区、商店会や管理組合、学校・保育園・高齢者施設と範囲を広げます。におい・粉じんが気になりやすい窓面が近い住宅には、養生強化と清掃時間の事前周知を約束すると安心感が高まります。「誰に・いつ連絡すればすぐ対応してくれるか」を明示することが、苦情の長期化を防ぐ最も実効的な施策です。
安全対策と防炎 防じん 防音
火災で炭化・変形した構造は局所的に強度が低下しており、通常の解体よりも倒壊リスクが高い場合があります。初動で危険部の支保工や手壊し範囲を決め、重機の進入順序・旋回範囲を定義した施工計画を作成します。現場では、現場代理人・安全衛生責任者・各作業主任者(例:石綿、足場)の役割を明確にし、朝礼とKY活動、立入管理、作業許可、作業後点検を日課化します。
防炎は、火花作業(鉄骨の切断など)が生じる場合の火気管理、周辺可燃物の除去、消火器の複数配置、防炎シート・防炎メッシュの使用が柱です。防じんは、解体・積込・搬出の全工程での散水、ミスト噴霧、集じん機の併用、養生シートの目地処理、車両タイヤの洗浄と路面清掃を組み合わせます。防音は、防音パネルの仮囲い、低騒音型重機・小割機の採用、作業時間帯の順守、騒音ピーク工程の近隣周知で対応し、測定器でのモニタリングを記録に残します。アスベストの除去・封じ込めが未完了の部位に対して本体解体を進めないことは、作業員と地域の安全を守る絶対条件です。
| 主要リスク | 兆候・条件 | 重点対策 | 現場記録(エビデンス) |
|---|---|---|---|
| 倒壊・崩落 | 焼損梁・柱、雨掛かりで軟化、偏荷重 | 手壊し先行、支保工、重機の離隔確保 | 施工計画図、日々の点検記録、リスクアセスメント |
| 粉じん飛散 | 乾燥時、風向きが近隣側、積込みピーク | 散水・ミスト、養生強化、タイヤ洗浄・路面清掃 | 散水記録、清掃写真、空気環境モニタの記録 |
| 騒音・振動 | 基礎撤去・小割、重機複数台稼働 | 低騒音機械、防音パネル、時間帯の順守 | 測定ログ、近隣周知文書、工程変更の掲示 |
| 火災・再燃 | 残存可燃物、火花作業、電源残置 | 可燃物除去、火気管理者、消火器常備 | 火気作業許可票、巡回記録 |
| アスベスト曝露 | 事前調査で含有判明、劣化・破砕の恐れ | 負圧養生、集じん・湿潤化、作業区域の封鎖 | 事前調査結果、作業記録、廃棄物管理票 |
| 交通事故 | 狭隘道路、通学時間帯、見通し不良 | 交通誘導員配置、車両誘導計画、時間帯分散 | 道路使用許可控、配置記録、ヒヤリハット記録 |
| 落下・転落 | 高所作業、開口部、足場移動 | 養生手すり、墜落制止用器具、特別教育 | 点検表、是正記録、教育履歴 |
産業廃棄物は分別解体を徹底し、マニフェストで搬出から最終処分まで追跡します。積込み時は飛散防止ネットを使用し、道路への泥はねや破片落下を防ぐため、出入口に洗浄マットや仮設排水処理を設けます。粉じん・騒音・交通の対策は「やっている」だけでなく、記録に残して可視化することが、近隣説明と監督官庁対応の両方で効果を発揮します。
道路使用許可の期間管理と誘導員
東京では前面道路が狭く、工事車両の停車や仮囲いの越境が避けられない現場が多くあります。路上での積込み・重機搬入・資材仮置きなど一時的に道路を使用する場合は警察署の道路使用許可、上空越境や歩道占用・仮設ステージ等が必要な場合は道路管理者の道路占用許可が求められるのが一般的です。許可内容(期間・場所・時間帯・作業方法)を工程表に落とし込み、更新・延長が必要な日を事前に可視化します。
通学路やバス路線、幹線道路沿いの現場では、時間帯の制限や警備員の増員が求められることがあります。積込みの集中を避け、朝夕の通行量の多い時間を外して搬出便を分散するほか、車両待機場所を現場外で確保して渋滞や苦情を未然に防ぎます。
| 場面 | 典型作業 | 主な許可・確認 | 保安機材 | 交通誘導計画の要点 |
|---|---|---|---|---|
| 足場・仮囲いの設置 | 防音パネル、防炎シート、ゲートの組立 | 道路使用/占用(越境時) | コーン、バリケード、保安灯、標識 | 歩行者動線の分離、見通し確保、夜間反射具 |
| 重機の搬入・搬出 | 回送車の停車、重機の乗り入れ | 道路使用、誘導計画の事前協議 | 誘導棒、注意喚起サイン | 左右両端での誘導、通学時間帯の回避 |
| 産廃の積込み | ダンプへの積込み、ラッシング | 道路使用、マニフェスト携行 | 飛散防止ネット、清掃用具 | 片側交互時は両端に警備員、路面清掃の即時実施 |
| クレーン・高所作業車 | 梁・大割材の吊り、資材仮置き | 道路使用/占用(張出時) | アウトリガー保護材、立入禁止柵 | 吊り荷下の通行止め、無線連絡の統一 |
| 片側交互通行 | 狭幅員での積込み・搬入 | 道路使用 | 誘導灯、仮設信号(必要時) | 見通しの悪いカーブ前後に配置、隊列管理 |
| 道路上養生 | 鉄板・ゴムマット・養生板の敷設 | 道路占用(必要時) | 段差解消材、すべり防止材 | 歩行者動線の確保、夜間の滑り・転倒対策 |
交通誘導警備員は、出入口・路上作業両端・見通しの悪いポイントに配置し、近隣の生活動線(通学路・自転車レーン・商店街の搬出入時間)と干渉しないよう運用します。現場では、誘導計画図・配置簿・日々の運用記録を備え付け、警察や道路管理者からの指摘に即応できる状態にします。許可期間の延長・変更は「期限の数日前」には申請し、工程変更が生じたら近隣と掲示で即日共有するのが鉄則です。
最後に、路面や排水側溝の清掃を毎日終業時に行い、路上占用を伴った日には特に念入りに確認します。粉じん・騒音・交通の三点を「計画・実施・記録・周知」で一体管理することが、東京の火事後解体を安全・円滑に進める最大のコツです。
解体後の手続き

解体が完了したら、まずは不動産登記と税務の手続きを正しく行い、そのうえで再建計画に進みます。東京では管轄官庁が明確に分かれており、申請期限や添付書類を外さないことが重要です。特に「建物滅失登記」は法定期限があり、固定資産税の減免は申請しなければ適用されないため、スピードと正確さが結果的にコストを下げます。
滅失登記 固定資産税の減免
「建物滅失登記」は、火事による焼失や解体で建物がなくなった事実を登記簿に反映させる手続きです。解体・焼失の日から1か月以内に、建物の所在地を管轄する法務局(東京法務局本局・各出張所)へ申請します。申請者は登記名義人(所有者)が原則ですが、委任により代理人でも可能です。
| 手続き | 提出先 | 期限 | 主な必要書類 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建物滅失登記 | 東京法務局(管轄登記所) | 滅失の事実発生日から1か月以内 | 建物滅失登記申請書、登記原因証明情報(解体証明書または罹災証明書)、委任状(代理申請時) | 登録免許税は非課税 | 窓口またはオンライン申請可。家屋番号の確認が必須。 |
| 固定資産税等の減免申請 | 区役所・市役所(資産税担当) | 各自治体の条例に基づく期間内(原則、納期限まで) | 申請書、罹災証明書、解体証明書、本人確認書類 | 手数料不要 | 家屋の被害状況・滅失日を確認できる資料が必要。 |
| 家屋滅失の届出(任意・推奨) | 区役所・市役所(資産税担当) | 解体後できるだけ速やかに | 家屋滅失届、解体証明書の写し | 手数料不要 | 課税台帳の反映を早める効果がある。 |
滅失登記の添付資料(登記原因証明情報)は、解体の場合は解体工事業者が発行する「解体証明書」が一般的です。火事で焼失し、原形をとどめない場合は、区市町村が交付する「罹災証明書」を用います。いずれも滅失の原因(取壊し・焼失)と日付が特定できることが重要です。
| 状況 | 主な添付書類 | ポイント |
|---|---|---|
| 解体工事で除却 | 解体証明書(業者発行) | 所在地・家屋番号・構造・床面積・工期・滅失日を明記。業者の名称・押印(署名)を含める。 |
| 火事で焼失(全焼・大部分焼失) | 罹災証明書(区市町村発行) | 滅失日・被害程度が分かるものを用意。写真記録も保管。 |
| 登記名義人が死亡 | 相続人による申請+相続を証する書面(相続関係説明図等) | 相続登記の前でも、相続人申請で滅失登記は可能。代表相続人の選任と書類整備を。 |
| 家屋番号が不明 | 固定資産税納税通知書、評価証明書等で確認 | 住居表示(番地・号)と「家屋番号」は別物。登記所で事前照会して誤記を防ぐ。 |
固定資産税(都市計画税を含む)は毎年1月1日の現況に基づいて課税されます。当年中に解体しても、当年度の家屋分の税は原則として発生しますが、火災等の事情がある場合は各区市町村の条例に基づく減免制度が利用できます(申請制)。また、更地になると翌年度の「住宅用地の特例」(課税標準の軽減)が外れる場合があるため、再建のスケジュールと税負担の見込みを早めに試算しましょう。
- 減免に使う主な資料:罹災証明書、解体証明書、写真(被害状況・滅失後)、納税通知書等
- 申請窓口:23区は各区の資産税課、多摩地域は市役所の資産税担当
- 注意点:申請期限を過ぎると当年度の減免を受けられないことがあります。
滅失登記と税の減免は「連動」しません。登記をしただけでは税の減免は自動適用されないため、両方を別々に完了させる必要があります。
再建計画と防火地域の制限
再建に着手する前に、敷地の法的条件(都市計画・建築基準)を精査します。東京では「防火地域・準防火地域」の指定が広範に及ぶほか、用途地域や建ぺい率・容積率、高度地区、日影規制、地区計画、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接することが原則)、2項道路のセットバックなど、複数の規制が重なります。
| 規制・確認項目 | 主な確認先 | 主なポイント | 再建への影響 |
|---|---|---|---|
| 防火地域 | 区市の建築指導課・確認検査機関 | 原則すべて耐火建築物が必要 | 構造・工法・コストに直結。木造は基本的に不可(耐火仕様が必要)。 |
| 準防火地域 | 区市の建築指導課・確認検査機関 | 規模や用途に応じて準耐火等の制限 | 外壁・開口部の仕様、階数・延床面積の計画に影響。 |
| 用途地域・建ぺい率・容積率 | 都市計画担当・建築指導課 | 用途の可否と最大ボリュームの上限 | 建物規模・間取り・駐車場計画を規定。 |
| 接道義務・2項道路 | 道路管理者・建築指導課 | 幅員4m未満の道路はセットバックが必要 | 有効敷地が縮小し、建ぺい率・配置に影響。 |
| 高度地区・日影規制 | 都市計画担当・建築指導課 | 高さ・斜線制限の適用 | 屋根形状・階数計画の調整が必要。 |
| 地区計画・景観 | 都市計画担当 | 外観・素材・工作物の基準 | ファサード・塀・看板等の仕様に影響。 |
省エネ関連では、建築物省エネ法により新築住宅の省エネ基準適合が求められます(確認申請時に適合性の確認)。東京都内では、一定の新築住宅について太陽光発電設備の設置を推進する制度等が運用されています。対象や要件は建築主や販売事業者の区分、規模等で異なるため、最新の運用を設計者・確認検査機関とともに確認してください。
- 敷地調査:用途地域・地区指定、防火(準防火)区域、建ぺい率・容積率、接道状況、インフラ(上下水・ガス・電気)を確認。
- 事前協議:区市の建築指導課で接道・セットバック、敷地境界、計画の適合性を事前確認。
- 基本計画:規制内でのボリューム検討(高さ・斜線・日影・防火仕様)。耐火・準耐火の仕様とコストを見積。
- 建築確認申請:特定行政庁(区市)または指定確認検査機関へ。省エネ適合・構造・防火仕様の整合を図る。
- 近隣対応:解体に続いて新築工事でも騒音・振動・道路使用の管理計画を提示し、合意形成を進める。
- 税務の見通し:更地期間の税負担(住宅用地特例の不適用リスク)と再建時期を調整。
防火地域では耐火建築物が原則となるため、工法・材料・設備の選択がコストと工期に大きく影響します。準防火地域でも開口部・外壁の防火仕様が求められるため、早期の仕様確定とサプライチェーンの確保が、再建のスピードと予算管理に直結します。
よくある質問
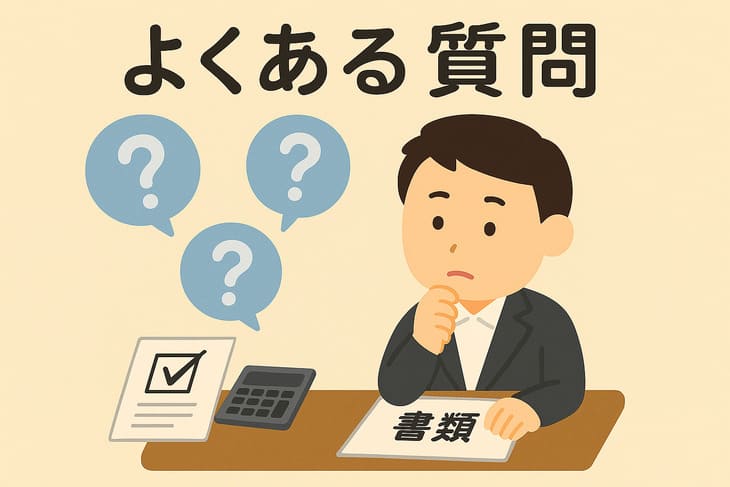
一部焼損でも全解体が必要か
結論から言えば、火事で「一部焼損」の場合でも必ずしも全解体が必要になるわけではありません。判断は、構造安全性・衛生面(臭気や煤の残留)・法令適合・費用対効果・再建計画(防火地域の制限や不燃化方針)といった複数の観点を総合して行います。東京都内では木造・鉄骨造・RC造が混在し、敷地や道路条件も大きく異なるため、同程度の焼損でも最適解が変わる点に注意が必要です。
| 判断の視点 | 確認の要点 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 構造安全性 | 木造は柱・梁・耐力壁への炭化浸食、鉄骨造は高温による変形や座屈、RC造は爆裂(表面剥離)や鉄筋露出の有無を確認。主要構造部に達する損傷は「大規模な修繕」や建替え検討のサイン。 | 一級建築士(構造診断)、解体工事業者 |
| 衛生・居住性 | 広範な煙損や消火水による含水、断熱材・下地への臭気浸透は、クリーニングや下地交換の費用が膨らみがち。カビ・腐朽の二次被害の可能性も評価。 | リフォーム会社、環境計測事業者 |
| 法令適合 | 主要構造部に及ぶ「大規模の修繕」に該当する場合は建築確認が必要になることがあります。防火地域・準防火地域では再建の仕様制限も要確認。 | 設計事務所、区市町村の建築相談窓口 |
| 費用対効果 | 部分解体+修繕+臭気対策の総額と、全解体+新築(または更地)の総額を比較。仮設費・養生費・道路使用関連費は工事分割で重複しやすい。 | 解体工事業者、工務店、保険会社 |
| 補助制度の要件 | 老朽危険家屋の除却や木密地域の不燃化支援は「建物の除却(原則全体)」を要件とする制度が多い一方、部分改修は対象外となる場合があります。 | 区市町村の住宅・防災部局 |
| 保険・原因調査 | 火災保険の鑑定や消防の調査結果が未了の段階で撤去・改変を行うと、補償範囲の認定に影響することがあります。 | 保険会社(鑑定人)、消防署 |
保険会社の査定および消防の調査が完了する前に、焼けた部材や残置物を撤去・処分しないことが鉄則です。証拠保全のための写真・動画・焼損範囲の実測は着手前に済ませましょう。
部分解体や修繕で復旧する場合は、アスベスト事前調査(法定)を先行し、必要な届出・報告を終えた上で、臭気対策(下地交換・密閉塗装など)の工程を見積内に明確化します。全解体が妥当な場合は、東京都内の道路条件や隣地状況に応じた養生・搬出計画を詰めることで、期間短縮とコスト最適化が図れます。
罹災証明書はどこで発行されるか
東京都内で火事に遭った建物の証明は、一般に被災建物が所在する区市町村(区役所・市役所・町村役場)の窓口で発行されます。火災の場合は自治体により名称が「罹災届出証明書(火災)」や「り災証明(火災)」となることがあり、台風・地震などの自然災害で用いられる「罹災証明書」と名称・用途が分かれている自治体があります。申請時は本人確認書類、建物の所在地が分かるもの、手数料(必要な場合)、代理申請なら委任状を用意します。
| 証明の名称 | 主な対象・用途 | 発行主体 | 取得のポイント |
|---|---|---|---|
| 罹災届出証明書(火災) | 火災による被害の事実証明。火災保険請求、固定資産税の減免申請、各種支援制度の申請等で求められることがあります。 | 被災地の区市町村 | 消防の火災調査結果等に基づき発行。本人または代理人(委任状)が申請。交付までの期間・手数料は自治体ごとの運用。 |
| 罹災証明書(自然災害) | 台風・地震・水害等の被害認定。火災ではなく自然災害時に用いられます。 | 被災地の区市町村 | 火災のケースでは対象外となる自治体が多く、火災は前記の「罹災届出証明書」等で代替。 |
| 火災に関する証明・調査書(写し) | 火災発生や調査に関する事実関係の資料として、保険会社等から求められることがあります。 | 所轄消防署(発行の可否・名称は消防本部の運用による) | 自治体発行の証明と併せて提出を求められる場合に取得。取り扱いと必要書類は所轄消防署に確認。 |
なお、証明の種類や名称、必要書類は自治体で異なります。「火災=罹災証明書」と限らないため、被災地の区市町村で火災用の証明名称と申請手順を必ず確認してください。解体や滅失登記、税の減免、保険金請求の時期に影響するため、早めの申請をおすすめします。
申請や届出は業者に任せられるか
多くの手続きは、施主(所有者)が委任することで解体業者や元請業者が代行可能です。ただし、法令上の義務主体や名義人は変わらず、最終的な責任は施主と元請(請負人)それぞれの法的立場に帰属します。委任状の要否・電子申請のアカウント要件・提出期限は手続きごとに異なるため、見積・契約段階で「誰が・いつまでに・何を」行うかを合意・明記しましょう。
| 手続き | 法令・区分 | 主な提出先 | 原則の申請者 | 業者代行 | 実務ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設リサイクル法の届出(分別解体等) | 工事種別・規模が対象となる場合に必要 | 建物所在地を所管する都道府県・区市町村 | 発注者(施主) | 可(委任状で元請・解体業者が実務を担うのが一般的) | 電子届出の運用が広がっています。工事着手前に期限あり。設計図・写真・工程の根拠を添付。 |
| 石綿(アスベスト)事前調査の実施・結果報告 | 大気汚染防止法等に基づく義務 | 都道府県等(電子報告) | 元請業者(報告義務者) | 元請が実施・報告(所有者の委任は不要だが情報提供が必要) | 着工前に報告。除去等が伴う場合は別途の届出期限が設定されることがあります。 |
| 騒音・振動に関する工事届 | 騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例 | 区市町村 | 施工者(元請) | 元請が提出 | 工程・作業時間帯・防音防じん対策を明記。近隣説明と掲示は着工前に実施。 |
| 道路使用許可 | 道路交通法 | 所轄警察署(交通課) | 道路を使用する者(通常は施工者) | 元請・解体業者が申請 | 期間管理が重要。誘導員・保安施設計画、搬出ルートを明確化。 |
| 道路占用許可(仮囲い・足場等) | 道路法・東京都の要綱 | 道路管理者(区市町村・東京都等) | 占用者(施工者または施主) | 元請が代表して申請可(委任状が必要な場合あり) | 占用物の仕様・位置図・期間を提示。占用料の発生に留意。 |
| 産業廃棄物管理票(マニフェスト) | 廃棄物処理法(建設系) | (提出先ではなく)交付・管理は元請の義務 | 排出事業者=元請業者 | 元請が交付・管理 | 電子・紙の別を契約で明記。最終処分までの写し保管・完了報告を徹底。 |
| 火災に関する証明(罹災届出証明書 等) | 行政手続(証明書交付) | 被災地の区市町村 | 所有者等 | 可(委任状が必要) | 保険請求・税の減免・支援制度で必要。交付時期が工程に影響するため早めに手配。 |
| 解体補助金・除却助成の申請 | 区市町村の制度 | 区市町村 | 原則として所有者 | 可(制度により代理申請の可否が明記される) | 事前申請が条件の制度が多い。契約・着工前に要件を確認。 |
| 建物滅失登記 | 不動産登記法 | 法務局 | 所有者 | 司法書士への委任が一般的 | 解体完了から一定期間内に申請。完了証明(解体証明書等)を添付。 |
「誰が申請者か」「委任状が要るか」「電子申請のアカウントは誰名義か」「提出期限はいつか」をそれぞれ確認し、見積書・契約書・工程表に反映させることがトラブル防止につながります。原本・控え・受付票(受付番号)は施主側でも必ず保管しましょう。
まとめ

火事後の解体は、まず安全確保と二次災害の防止、現場写真等の証拠保全、消防署・保険会社・解体業者への連絡を同時並行で進めることが最短です。費用を抑える核心は、火災保険・罹災証明に基づく公的支援の活用、残置物の分別、早期のアスベスト事前調査、相見積もりと工程分割、道路条件と仮囲いの事前計画にあります。手続きは建設リサイクル法の届出や大気汚染防止法に基づくアスベスト報告、騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例の遵守が要点です。
不燃化特区や木造密集地域の除却補助、老朽危険家屋・空き家対策の制度は区市町村で内容が異なるため、東京都と各区役所の窓口で最新情報を確認しましょう。見積書は数量根拠と内訳を明確にし、契約書は変更合意のルールを事前に定めることが紛争予防になります。近隣挨拶、安全対策、道路使用許可と誘導員の配置を管理し、完了後は滅失登記と固定資産税の減免等の手続きを速やかに。再建時は建築基準法の地域指定(防火地域等)の制限を確認することが結論です。
届出や申請はオンライン化が進み、業者へ委任できる手続もありますが、発注者の確認や承認・同意が必要になるため、スケジュールと責任分担を事前に明文化しましょう。段取りと記録、法令順守、支援制度の活用が、東京での火事後解体を速く安全に適正費用で進める鍵です。





