火事で家を「解体しない」と違法なのか――本記事は、東京消防庁と国土交通省の基準、建築基準法・消防法・空家等対策特別措置法の要点を横断し、2025年時点の実務で何がOK/NGか、費用と手続きまで一気に把握できるガイドです。結論、解体しないこと自体は原則違法ではありません。ただし倒壊や延焼のおそれ、衛生・防犯上の支障があれば是正命令や使用制限、特定空家等の勧告、行政代執行、固定資産税の住宅用地特例の失効、近隣への損害賠償リスクが生じ得ます。り災証明書の取得、火災保険(残存物片付け費用等)の請求、仮囲い・養生・立入禁止の初動、修繕再使用の条件(建築士の安全性調査・確認申請・電気ガス水道再開)、解体相場2025(構造別・すす/臭気/消火水対策・アスベスト・残置物処分)、建設リサイクル法80平方メートル・大気汚染防止法の石綿事前調査・産業廃棄物マニフェスト、東京都内の相談窓口まで網羅します。また、再出火防止や近隣連絡、足場・防音シート、臭気・すす・灰の清掃、害虫・害獣対策、見回りや監視カメラなど管理の実務、各区の建築指導課・空家対策担当、東京消防庁の相談窓口、建築士・弁護士・保険代理店への相談先も具体的に示します。
Contents
結論:火事の後に解体しないこと自体は原則違法ではない

2025年時点で、火事の発生後に建物を直ちに解体しなければならないと定める全国一律の法律は存在しません。所有者が危険箇所を適切に管理し、公衆に危害や迷惑を及ぼさないよう安全対策を講じている限り、修繕や再使用の可否を見極めるため一定期間「解体しない」という選択は一般に認められています。
結論として、火事の後にただちに解体しないこと自体は原則違法ではありませんが、危険状態や不衛生な状態を放置すると、行政からの指導・命令や民事上の賠償責任の対象となり得ます。
「焼失から〇日以内に必ず解体」という固定的な期限が法令で決まっているわけではなく、違法性が問題になるのは、倒壊・落下の恐れ、再出火の恐れ、衛生・環境悪化、占用物の散乱、防犯上の無管理といった具体的な危険や不具合の放置がある場合です。所有者としての管理責任(維持保全)を果たしつつ、解体・修繕・保全のいずれを選ぶかを関係機関や専門家と相談して決めることが重要です。
実務上の判断軸は次の3点に集約されます。
- 安全性の確保(倒壊・落下・再出火の防止)
- 衛生・環境配慮(灰・すすの飛散、悪臭、害虫の抑制)
- 適切な管理(立入防止、施錠・仮囲い、近隣への情報提供)
上記の管理ができていれば「解体しない=直ちに違法」にはなりません。反対に、管理が不十分だと行政指導や是正命令の対象になり得ます。
違法となり得る条件と放置リスク
「解体しない」ことが問題化するのは、危険や迷惑の発生源となる状態を放置したときです。代表的な場面とリスクを整理します(実際の適用は用途・場所・構造・自治体運用により異なります)。
| 状態 | 想定される法的リスク | 行政の主な対応例 | 早急に求められる対策の例 |
|---|---|---|---|
| 倒壊や外壁・屋根材の落下の危険を放置 | 建築物の維持保全義務に反する状態として是正の対象となる可能性 | 現地調査→指導→是正命令→従わない場合の行政代執行(自治体の運用による) | 仮囲い・立入禁止、飛散・落下防止の養生、危険部材の撤去、専門家点検 |
| 電気設備の損傷放置・通電継続、残り火、油類の漏えい | 消防上の危険状態として使用制限や指導の対象 | 立入検査、口頭・文書指導、用途により是正命令 | 通電停止、再出火の確認、保安機関・電気工事士の点検 |
| 瓦礫・焼却残渣が道路や隣地に散乱、灰やすすの飛散 | 生活環境の阻害や占用状態として是正指導の対象 | 清掃・撤去の指導、必要に応じて措置命令(条例等の運用) | 清掃・回収、飛散防止の養生、適正保管と処分の手配 |
| 悪臭・汚水・害虫の発生を放置 | 衛生・環境上の問題として改善指導の対象 | 衛生部局等による指導、改善計画の要請 | 消臭・清掃、排水処理、害虫・害獣対策 |
| 無施錠・無管理で侵入容易、放火・盗難の危険 | 防犯・防火上の管理不全として指導の対象 | 巡回・注意喚起・指導(地域の運用による) | 施錠、仮囲い・バリケード、立入禁止の掲示、定期見回り |
| 落下物やすす飛散で隣家・歩行者等に損害発生 | 民事上の損害賠償責任を問われる可能性 | 行政手続とは別に当事者間の民事対応 | 危険箇所の即時除去・養生、賠償保険の確認・連絡 |
多くの自治体では「助言・指導」が先行し、命令・代執行は最終手段ですが、切迫した危険がある場合は即時の是正を求められることがあります。
放置による実務上のデメリットも重大です。時間の経過とともに構造材の腐朽・爆裂やカビの発生、臭気の染み込み、金属部の腐食が進み、修繕・解体のいずれにしても費用が膨らみやすくなります。さらに、無人化・無管理状態は不法侵入や盗難、再出火リスクを高め、近隣トラブルや通報の増加につながります。保険の査定にも影響し得るため、証拠保全や事前連絡を含む適切な初動が重要です。
すぐにやるべき初動対応 り災証明書・保険・近隣連絡
「解体しない」選択を検討するかどうかにかかわらず、火災直後の数日間で押さえるべき初動は共通です。安全・証拠保全・連絡・手続の4本柱で進めます。
| 目的 | 主な行動 | 関係先・担当 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 安全確保 | 消防・警察の立入許可を確認し、倒壊・落下の危険箇所を把握 | 消防署、警察署 | 許可前の立入や無断の片付けは避ける |
| 再出火防止 | 電気の通電停止、残り火の有無確認、ガス・水道の遮断 | 電力会社、ガス会社、水道局、消防署 | 有資格者の点検・復旧手順に従う |
| 証拠保全 | 片付け前に被害状況を写真・動画で記録、家財の品目・型番を控える | 所有者(家族)、保険代理店の指示 | 無理に動かさず、危険箇所には近づかない |
| り災証明書の申請 | 市区町村(東京都なら各区役所)で手続を行い現地調査に対応 | 区市町村役所 | 住家は「り災証明書(罹災証明書)」が原則。非住家は取扱いが異なる場合あり |
| 保険会社への連絡 | 火災保険・共済に事故連絡、査定前の大規模な撤去は控える | 加入保険の保険会社・代理店 | 契約により「残存物片付け費用」「臨時費用」「借家人賠償責任」等の補償を確認 |
| 近隣・関係者への説明 | 隣接地、管理組合・町内会、賃貸なら家主・管理会社へ状況と今後の方針を連絡 | 近隣住民、管理組合、家主・管理会社 | 臭気・搬出・作業時間帯などの配慮事項を共有 |
| 緊急の仮養生 | 立入禁止の掲示、簡易の仮囲い・ブルーシートで飛散・落下を抑制 | 専門業者(解体・工務店等) | 安全第一で最低限の対策にとどめ、恒久対応は後日検討 |
消防・警察の許可が出る前の搬出や片付け、そして保険会社の確認前の大規模な撤去は、原因調査や保険査定に不利に働くおそれがあるため慎重に進めてください。
り災証明書(罹災証明書)は、市区町村が被害の事実と程度を確認して交付する公的な証明書で、保険金請求や各種支援の基礎資料になります。申請先・必要書類・調査方法は自治体で異なるため、居住地の窓口で最新の案内に従ってください。
火災保険・共済は契約により補償範囲や手続が大きく異なります。残存物片付け費用や臨時費用、家財・建物の再調達費など、対象と支払条件を必ず確認し、査定担当者の指示に合わせて片付け・養生の順番を決めましょう。
近隣や管理組合には、臭気・すすの飛散・車両搬入などで一時的に迷惑が生じ得ることを前提に、予定や対策を先回りして共有するとトラブルを避けやすくなります。緊急度の高い養生は専門業者に依頼し、危険の低減と周辺への配慮を両立させることが大切です。
国の基準と建築基準法の要点
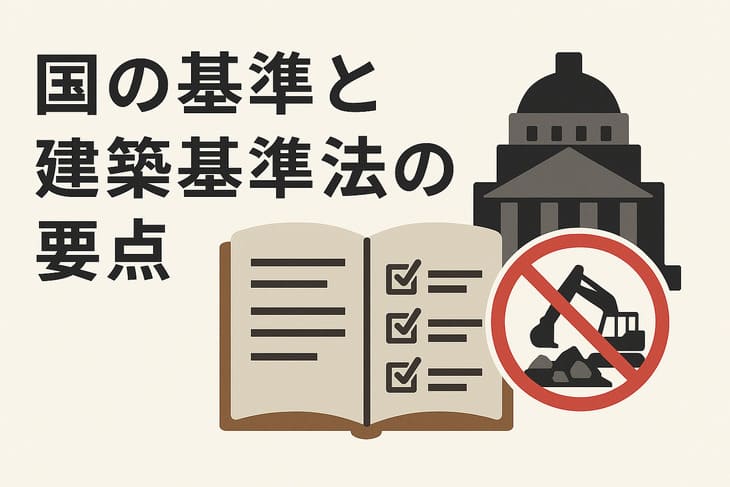
火災後に建物をすぐに解体しない判断それ自体は直ちに違法ではありません。しかし、建築物の最低限の安全・衛生を定める国の技術基準(所管:国土交通省)と建築基準法の枠組みでは、所有者等に「維持保全」の責務が課され、第三者に危険が及ぶ状態や著しい不適合が放置されれば、指導・命令・行政代執行といった是正プロセスの対象となります。
火事の「解体の有無」よりも、建物を社会的に安全な状態へ保つ「維持保全」と「危険の除去」を直ちに果たせているかが、国の基準で最重視されるポイントです。
国土交通省の基準と維持保全義務
国土交通省は、建築物の構造、耐火・防火、避難安全、設備等に関する全国一律の技術基準を定めています。建築基準法に基づき、建築物の所有者・管理者・占有者は、建物・敷地・付属工作物を常に安全な状態に維持する責務があり、火災で性能が低下した部分(構造耐力、防火区画、外壁の落下防止など)は、解体せずに保存する場合であっても、補修・補強・使用制限などで安全を確保する必要があります。
なお、過去に適法に建てられ、その後の基準改正で適合しなくなっただけの「既存不適格建築物」は、直ちに違反とはされません。一方で、火災により安全性能が損なわれ、現行の最低基準を満たさない危険な状態を放置すると「違反状態」と評価され得るため、早期の点検・措置が不可欠です。
| 関係主体 | 主な役割・権限 | 火災後の主なアクション |
|---|---|---|
| 所有者・管理者・占有者 | 維持保全の実施、第三者被害の防止、必要な工事の手配 | 危険箇所の仮設防護・立入制限、建築士の調査依頼、修繕や使用制限の決定・実施 |
| 特定行政庁(建築主事・建築指導部局) | 立入検査、行政指導、是正命令、行政代執行 | 現地確認・技術的助言、使用禁止・修繕・除去等の命令、履行確認と未履行時の措置 |
| 指定確認検査機関 | 確認審査(大規模な修繕・模様替等) | 必要な工事計画についての適合性審査(違反是正の命令権限は持たない) |
維持保全の焦点は「構造安全」「防火性能」「避難安全」「外部落下物の防止」「設備の安全停止・復旧」にあります。特に道路・隣地に面する外壁・屋根・バルコニー・門塀などは第三者リスクが高く、優先的に措置されます。
| 着眼点 | 基準の趣旨 | 火災後に問題化しやすい点 | 初期対応の例 |
|---|---|---|---|
| 構造安全 | 倒壊防止・耐力の確保 | 梁・柱の炭化、鋼材の熱変形、RCの爆裂・露筋 | 建築士の緊急点検、支保工・サポートの設置、危険室の閉鎖 |
| 防火性能 | 延焼防止・区画の保持 | 防火戸の変形、区画壁の破損、貫通部の防火処理喪失 | 開口部の仮閉鎖、不燃材での補修計画、可燃物の撤去 |
| 避難安全 | 避難経路・出入口の確保 | 階段・廊下の煤汚損や部材脱落、非常用照明の不作動 | 避難動線の復旧、落下物除去、非常用設備の点検 |
| 外部落下防止 | 通行人・隣地の安全 | 外壁仕上げ・タイル・屋根材の剥離 | 防護ネット・仮囲い、通行規制の検討、危険部材の撤去 |
| 設備安全 | 漏電・漏水・ガス漏れ防止 | 配線の絶縁劣化、配管の熱損傷 | 電気・ガス・水道の停止と専門業者点検、再開基準の確認 |
建築基準法の是正命令 行政代執行の流れ
特定行政庁は、火災後の建物が危険な状態にある、または基準に適合しない状態が放置されていると判断すると、建築基準法に基づき、現地の立入検査を行い、技術的な指導を経て、必要に応じて命令を発します。命令は通常、文書で対象・内容・履行期限を明示し、所有者等に履行を求めます。
命令の種類は、使用の制限・禁止、危険部分の除去、修繕・補強、立入禁止や仮設防護の措置などが中心です。履行が確認できない場合は、行政代執行が選択肢となり、自治体が代わって措置を行い、その費用は所有者等に求償されます。命令違反の放置は、罰則や過料の対象となることがあり、結果的に費用負担と社会的リスクが大きくなるため、早期の自主是正が最善策です。
| 是正措置 | 適用されやすい場面 | 所有者の主な対応 | 履行確認 |
|---|---|---|---|
| 修繕・補強命令 | 構造部や防火区画の性能低下が限定的な場合 | 設計者の補修計画作成、施工会社手配、工事完了報告 | 完了写真・報告書・場合により現地確認 |
| 使用制限・使用禁止 | 倒壊・落下・火災拡大の危険が高い空間や設備 | 立入禁止の表示・施錠、避難計画の見直し | 標示・封鎖の確認、継続管理の記録 |
| 危険部分の除去 | 外壁仕上げ・庇・タイル・ガラス等の脱落の恐れ | 危険部材の撤去、仮設防護ネット・養生の設置 | 撤去範囲と安全措置の確認 |
| 行政代執行 | 命令不履行・緊急の危険により公衆の安全確保が必要 | 事前告知後に自治体が代替実施、費用は所有者に徴収 | 実施結果の通知・費用徴収手続 |
多くの自治体は、まず行政指導(任意の改善要請)により自主是正を促します。命令や代執行に至る前に、所有者側が計画・工程・仮設安全の方針を提示し、段階的にリスクを下げることが実務上の要諦です。
危険な建築物の判断と安全確保
火災後の危険性の判断は、第三者被害(倒壊・落下・延焼)の可能性と、建物の基本性能(構造耐力・防火・避難)の低下度合いを軸に行われます。特定行政庁の技術職員による目視確認に加え、建築士の調査報告や非破壊試験などが用いられることがあります。
判断では、木造の炭化深さや接合部の損傷、鉄骨の熱による座屈・延伸、鉄筋コンクリートの爆裂・かぶり欠損、外壁仕上げやタイルの剥離、ガラスの熱割れ等が重点的に確認されます。危険が高いと見なされれば、当該部分の使用禁止、仮囲い・防護ネット・支保工などの仮設措置を直ちにとることが求められます。
| 部位 | 状態の例 | 主なリスク | 推奨される安全措置 |
|---|---|---|---|
| 屋根・庇 | 焼損、垂れ下がり、下地材の炭化 | 落下・飛散 | 立入禁止区域の設定、防護ネット・仮設支持、危険部材の撤去 |
| 外壁・仕上げ(タイル・サイディング等) | 膨れ・剥離、留め付けの損傷 | 落下・通行人被害 | 仮囲い・歩行者離隔、防護ネット、部分除去・補修 |
| 構造フレーム(木造・鉄骨・RC) | 炭化・座屈・爆裂、著しいひび割れ | 局部・全体の倒壊 | 支保工設置、荷重制限、専門調査の上で補強または除却 |
| バルコニー・手すり | 熱変形、固定部の損傷 | 転落・落下 | 使用禁止・封鎖、補強または撤去 |
| 開口部・ガラス | 熱割れ、たわみ、枠の変形 | 飛散・落下 | 破損ガラスの撤去、飛散防止、仮設板での閉鎖 |
| 門塀・擁壁などの工作物 | 傾斜、基礎の浮き上がり | 転倒・道路側への倒壊 | 支保・控え設置、撤去、通行安全措置 |
| 電気・ガス・給排水設備 | 絶縁劣化、配管の熱損傷 | 漏電・漏水・ガス漏れ | 停止・封印、専門業者点検の上で安全な再開 |
危険が敷地外に及ぶ恐れがある場合、仮囲い・通行動線の確保・落下防止措置は、解体の有無にかかわらず最低限必要な安全確保です。費用は原則として所有者が負担し、措置の継続管理も求められます。
最終的に、修繕による再使用が可能か、部分除去で安全を保てるか、全体の除却が適切かは、建築士の技術的所見と特定行政庁の判断を踏まえて決定します。危険の除去と法令適合を段階的に達成するプロセスを、記録と報告を伴って進めることが重要です。なお、大規模な修繕・模様替等では、工事内容によって確認申請が必要になる場合があります。
消防の視点と東京消防庁の運用
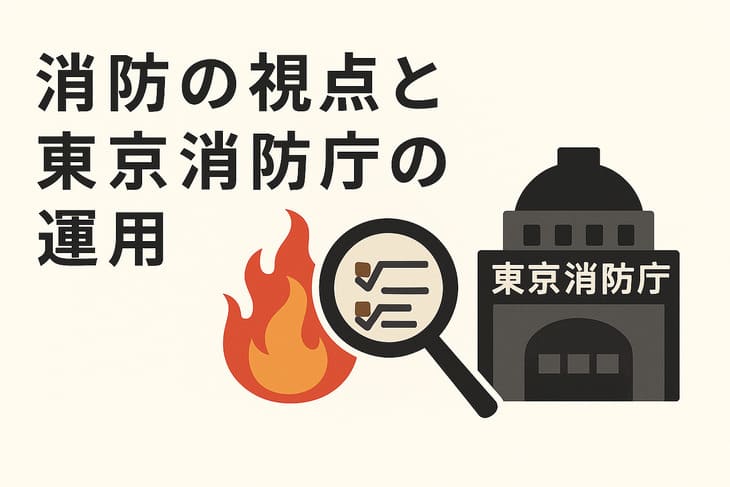
火災後に建物を「解体しない」選択をする場合でも、消防の立場では再出火の防止、火災原因調査、危険物や火気の管理、消防用設備等の機能回復という4点が最優先となります。東京消防庁の所管区域では、消防法および東京都火災予防条例に基づき、所有者・占有者・管理者(以下「関係者」)に対して必要な指導や是正要求が行われ、再使用の可否や範囲は「火災予防上の安全が確保されているか」で個別に判断されます。消防の指導・命令は解体そのものを直接求める性質ではなく、危険の除去と再出火・延焼の防止、避難・消火活動の確保に向けた使用の制限と改善を求めるものです。
消防法に基づく使用制限と指導
火災後、関係者には「火災の予防」と「消防活動・避難の妨げの除去」が求められます。東京消防庁は、立入検査や現場確認を通じて危険の有無を把握し、口頭・文書による指導、改善計画の提出要請、是正結果の報告徴収などを行います。危険物や火気設備に関わる違反、消防用設備等の機能喪失など、危険度が高い場合は所管法令に基づく措置(使用の停止や設備の改修・撤去等)を求められることがあります。正当な理由なく検査や指導に協力しないことは認められず、是正未完了のまま利用を再開することは強く制限されます。
| 対象となる主なリスク | 典型例 | 消防の指導・措置の例 | 所有者側の主な対応 | 再使用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃物・焼け残りの堆積 | 廃材・布団・紙類・家具内部のくすぶり | 撤去・隔離の指導、現場の可燃物管理の徹底 | 可燃物の搬出・保管区分の明確化、残り火の点検 | 可燃物が除去・管理され再燃の恐れが低い状態 |
| 消防用設備等の機能喪失 | 感知器・自動火災報知設備・消火器・屋内消火栓の損傷 | 復旧・点検・報告の指導、必要により使用の見合わせ | 専門業者による復旧と点検報告書の提出 | 作動確認と必要書類の整備が完了した後 |
| 危険物・ガスの残存 | LPガスボンベ、灯油、スプレー缶、溶剤 | 供給停止・撤去の指導、保管方法の是正 | 供給遮断・撤去、事業者への回収依頼 | 危険物の安全処理と周囲の火気管理が完了後 |
| 避難経路や出入口の支障 | 倒壊物の散乱、階段・通路の焼損 | 障害物除去、避難経路確保の指導 | 仮設通路・仮囲い等での安全確保 | 避難・進入ルートが確保されたと判断後 |
| 電気設備の焼損・漏電の疑い | 分電盤・配線の焼損、機器の水濡れ | 通電再開の禁止指導、安全点検の要請 | 有資格者による絶縁・機能の点検 | 安全確認が書面等で確認できた後 |
| 不特定多数が利用する用途 | 飲食店・物販・宿泊施設など | 再開前の査察・違反是正の徹底 | 是正計画の提出・完了報告の提出 | 指摘事項の是正・確認が完了後 |
指導はリスクに応じて段階的に行われます。まずは口頭指導と現場での是正、その後必要に応じて文書での改善要求、再確認という流れが一般的です。再使用の再開は、消防上の危険が解消し、消防用設備等が所要の機能を回復していることが前提で、用途や規模により再開前の査察・確認が行われることがあります。窓口は所管消防署(予防部門)となるため、解体しない方針を決めた時点で早期に相談し、是正事項と必要書類を明確化しておくと円滑です。
| 段階 | 消防の主な対応 | 所有者の主な行動 |
|---|---|---|
| 出火当日〜鎮火 | 消火・残火処理、危険確認、現場保存の開始 | 指示への協力、危険個所に近づかない |
| 鎮火後〜現場引渡し | 原因調査、再燃リスクの監視、立入範囲の設定 | 立入の調整、必要に応じ危険物の撤去相談 |
| 引渡し後の是正期間 | 指導事項の提示、進捗確認 | 是正計画の策定、復旧・点検の手配・報告 |
| 再使用前 | 必要に応じた査察・最終確認 | 確認結果の受領、再開に向けた管理体制の整備 |
火災調査 再出火防止 立入の注意
東京消防庁は、火災原因の究明と再発防止のために火災調査を行います。警察と連携して現場保存が図られ、調査が終了するまで関係者であっても立入が制限される場合があります。調査終了後、現場は関係者に引き渡されますが、焼損物や内部のくすぶり、高温部位が残っていることがあるため、初期段階の立入には十分な注意が必要です。なお、火災調査の結果は自治体の罹災証明の判断資料として用いられることがあります。
| タイミング | 留意点 | 具体的なポイント |
|---|---|---|
| 立入前 | 現場保存と安全確認 | 消防・警察の許可と指示を受ける、再燃の恐れがあれば立入を見合わせる |
| 立入時 | 人身安全と再燃防止 | ヘルメット・手袋・防塵マスク等を着用、単独で入らない、足元と頭上を常時確認、火気厳禁・通電禁止・ガス遮断を徹底、消火器を近くに準備 |
| 立入時(危険物・電気) | 二次災害の防止 | LPガスボンベ・可燃性液体・スプレー缶等は動かす前に安全を確認、電気設備は有資格者の点検まで操作しない |
| 立入後 | 異常の監視と通報 | 焦げ臭・白煙・熱気・音など異常を認めたら速やかに119番通報、長時間の滞在は避ける |
| 資料・証拠 | 証拠保全と記録 | 調査完了前は物品の移動を最小限にし、必要に応じ現況写真を時系列で記録 |
火災原因調査が終わるまでの現場保存中は、所有者であっても勝手に片付けや持ち出しを行わないことが重要です。調査完了の説明を受けた後は、消防から示された再出火防止上の留意点(可燃物の扱い、火気の使用禁止範囲、危険物の撤去順序など)を確実に守ってください。粉じんの吸入防止や破片による受傷防止の観点からも、保護具の準備と作業計画の共有を徹底しましょう。
近隣が異常な煙やにおいを感知した場合に備え、連絡体制を整え、異常時にはためらわずに119番通報します。再使用や片付け作業の開始時期・範囲は、所管消防署と事前に打ち合わせ、危険の除去と安全確保の手順を合意してから着手することが、再出火と二次災害の防止につながります。
空家等対策特別措置法と固定資産税の注意

火災後に建物を「解体しない」選択をした場合でも、適切に管理していれば直ちに違法ではありません。しかし、焼損したまま長期に放置すると、自治体の調査を経て「特定空家等」に該当し得ます。これは行政手続(助言・指導→勧告→命令→代執行)へ進展するだけでなく、土地の税制優遇である住宅用地特例が外れ、固定資産税・都市計画税の負担が大きく増える可能性があります。
特定空家等に指定される条件
空家等対策の推進に関する特別措置法は、「空家等」を適切な管理が行われていない建築物等とその敷地と定義し、そのうち周辺の生活環境の保全または安全性の観点から放置が不適切なものを「特定空家等」と位置づけています。火災後に解体しない場合でも、以下の状態が続くと特定空家等に該当し得ます。
| 区分 | 典型例(火災後に生じやすい状態) | 所有者に求められる対応の例 |
|---|---|---|
| 倒壊・落下等の保安上の危険 | 焼損により柱・梁・小屋組が炭化し傾斜、屋根材や外壁材・雨樋が脱落しかけている、コンクリートの爆裂で壁面が不安定、ブロック塀や門柱の倒壊リスク | 建築士等による緊急点検、立入禁止の仮囲い・養生、足場+防音・防炎シート、防火・防落下対策、必要に応じた部分除却や補修 |
| 衛生上有害 | すす・灰・消火水に起因する悪臭、汚泥の堆積、雨水滞留、害虫(ハエ・ゴキブリ)や害獣(ネズミ・ハクビシン)の繁殖、カビや腐敗臭 | 焼却残渣の適正清掃・消臭、消毒・防虫防鼠、排水の確保、残置物・ごみの撤去、定期的な見回り |
| 景観・生活環境の著しい阻害 | 黒焦げの外観で景観悪化、敷地内の雑草繁茂、廃材・廃家電の野積み、破損箇所からのガラス飛散、無秩序な掲示物 | 外観の応急補修・養生、雑草除去と美観維持、可燃物の搬出、周辺への配慮掲示 |
| 放置が不適切なその他の状態 | 不審火・再出火の懸念、無断立入・不法投棄、夜間の防犯不安、敷地境界を越える危険樹木・枝の張り出し | 防犯対策(施錠・防犯カメラ・巡回)、立入禁止・管理者表示、近隣への連絡、危険樹木の剪定・撤去 |
自治体は現地調査の結果に基づき、段階的に行政措置を行います。措置の進行や税制への影響は次のとおりです。
| 段階 | 行政の措置 | 代表的な要件・きっかけ | 税制への影響 | 罰則・費用負担 |
|---|---|---|---|---|
| 助言・指導 | 所有者への改善要請(通知・面談など) | 軽微な管理不全、近隣からの通報、現地確認 | なし | なし |
| 勧告 | 改善を求める正式な行政処分 | 助言・指導に応じない/危険・有害性が高い | 土地の住宅用地特例が適用除外となり、固定資産税・都市計画税の負担が増える | なし(不履行が続くと命令へ移行) |
| 命令 | 除却や修繕等を命ずる法的拘束力のある処分 | 勧告にも従わない、危険性が継続・増大 | 勧告時に既に特例除外(継続) | 不履行で50万円以下の過料 |
| 代執行 | 自治体が除却等を実施 | 命令に従わない、緊急の必要性 | ― | 費用は所有者に全額請求 |
「解体しない」場合は、倒壊・衛生・景観・防犯の各リスクを抑える適正管理を即時に講じることが、特定空家等の指定(勧告)と税負担増を回避するうえで最重要です。
住宅用地特例の失効と税負担増
住宅用地特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する制度です。区分と軽減内容は次のとおりです。
| 用地区分 | 固定資産税(課税標準の特例) | 都市計画税(課税標準の特例) |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
「特定空家等」への勧告を受けると、その敷地は住宅用地特例の適用対象外となり、課税標準の軽減が外れます。また、建物を解体して更地にすると住宅が存在しないため、同様に特例は適用されません。
火災後に解体しない場合であっても、建物が「住宅」と認められる状態で適正に管理されていれば、賦課期日(毎年1月1日)時点の状況に基づき住宅用地特例が適用されることがあります。一方、勧告を受けた場合は適用除外となるため、翌年度以降の税負担が増えるのが一般的です。具体的な取扱いや適用時期は自治体の課税課(資産税担当)に確認してください。
| 状況 | 住宅用地特例の適用 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|---|
| 火災後も家屋が存し適正管理(賦課期日基準で住宅認定) | 適用の可能性あり | 小規模部分は6分の1、一般部分は3分の1 | 小規模部分は3分の1、一般部分は3分の2 |
| 特定空家等の勧告を受けた | 適用なし(除外) | 評価額の全額(1倍) | 評価額の全額(1倍) |
| 解体済み(更地) | 適用なし | 評価額の全額(1倍) | 評価額の全額(1倍) |
| 一部損壊だが居住継続・適正管理 | 適用の可能性あり | 小規模部分は6分の1、一般部分は3分の1 | 小規模部分は3分の1、一般部分は3分の2 |
税負担の増加幅は評価額と税率により異なりますが、小規模住宅用地に限っていえば、固定資産税は課税標準が「6分の1→1倍」、都市計画税は「3分の1→1倍」となるため、税額ベースでも概ね固定資産税は最大約6倍、都市計画税は最大約3倍に拡大し得ます(税率や評価替えの有無により実額は変動)。
概算例(仮定):土地評価額2,000万円・面積150㎡・固定資産税率1.4%・都市計画税率0.3%の場合
| 税目 | 特例あり(小規模住宅用地) | 特例なし(勧告・更地等) |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 2,000万円×1/6×1.4% ≈ 約4.7万円 | 2,000万円×1×1.4% = 28.0万円 |
| 都市計画税 | 2,000万円×1/3×0.3% ≈ 約2.0万円 | 2,000万円×1×0.3% = 6.0万円 |
火災直後からの適正管理(危険除去・衛生対策・美観維持・防犯措置)を継続することが、特定空家等への指定と住宅用地特例の喪失を避け、税負担の急増を防ぐ最も確実な方法です。建物の滅失登記や解体時期、勧告の有無は翌年度の課税に直結するため、早めに自治体の空家対策担当・資産税担当と連絡を取り、方針(修繕・部分除却・全解体)と管理計画をすり合わせておきましょう。
事故や賠償の民事リスク

「火事のあと解体しない」選択自体は直ちに違法ではありませんが、危険を放置して第三者に人身・物的損害や生活被害が生じた場合、民法上の損害賠償責任(不法行為責任・工作物責任)を問われる可能性が高くなります。管理措置の有無や程度は、過失の有無・賠償範囲の判断に直結します。
倒壊 落下物 悪臭での損害賠償
火災で炭化・高温劣化した柱・梁・外壁・屋根材は強度が低下し、時間の経過や風雨・積雪・余震等で「突然の崩落」や「飛散」を起こしやすくなります。加えて、すす・臭気・汚泥の拡散は近隣の生活環境や営業に影響を与え、人格権侵害や営業損害として問題化します。
事故類型と典型シナリオ
想定される事故と民事責任の整理は次のとおりです。事例はあくまで典型であり、個別事情(管理状況・気象条件・被害拡大防止策の有無等)により判断は変わります。
| 事故・被害の例 | 典型的な法的構成 | 過失判断の主な要素 | 主な損害項目 | 立証資料の例 |
|---|---|---|---|---|
| 倒壊・一部崩落(外壁・軒・塀・看板・バルコニーの落下) | 民法717条の工作物責任/民法709条の不法行為 | 危険の予見可能性、補修・養生・立入規制の実施、警告表示、経年劣化・火災損傷の程度、気象の強度と不可抗力性 | 治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料、車両や建物の修理費、代替駐車・仮住まい費 | 現場写真・動画、被害品の見積・請求書、気象データ、点検・養生記録、警告掲示の有無 |
| 屋根材・ガラス片・外装材の飛散による通行人・隣地車両の損傷 | 民法717条/709条 | 緩み・亀裂の把握、飛散防止ネットや仮囲いの設置、歩道側の防護棚・誘導員の有無 | 人身損害一式、物損(修理・買替差額)、代車費・営業車の休車損 | 修理見積、診断書、交通経路・時間の記録、設置物の施工・管理記録 |
| 悪臭・煤煙・煤塵の拡散による居住・営業妨害(洗濯物の汚損、店舗の集客低下) | 民法709条(人格権侵害・受忍限度超過) | 臭気・粉じん濃度や頻度、除去・清掃・脱臭措置の実施、作業時間帯の配慮、近隣協議の有無 | クリーニング費、追加清掃費、売上減少による営業損害、慰謝料 | 臭気・粉じんの測定結果、売上推移・予約キャンセル記録、苦情受付記録、清掃・脱臭の作業記録 |
| 消火水・雨水に混じった汚泥の流出や排水詰まりによる隣地浸水 | 民法709条/717条 | 排水経路の把握・封鎖、仮設集水・沈砂措置、ポンプ搬出や回収の実施 | 室内家財の毀損、床・壁の修復費、営業中断による損害 | 床上・床下浸水の写真、家財リスト、修繕見積、作業日誌 |
法的根拠と責任の帰属
火災で損傷した建物・敷地設備は「工作物」に該当し得ます。民法717条は、工作物の設置・保存に瑕疵があり他人に損害が生じた場合は、原則として占有者(通常は現に管理している者)が責任を負い、占有者が相当の注意を尽くしたと立証できるときは所有者が責任を負うと定めています。これとは別に、民法709条の一般不法行為責任(故意・過失による権利侵害)による請求が問題となる場合もあります。
「解体しない」選択をした場合でも、危険箇所の除去・仮設防護・警告表示などの管理措置を尽くす義務は残ります。警告後の立入者の自招事故などでは過失相殺が考慮され得ますが、危険の程度が高いのに有効な遮断措置を講じていないと、所有者・占有者の過失が重く評価されやすくなります。
過失の判断ポイント
裁判・示談交渉で重視されやすいポイントは次のとおりです。
- 危険の予見可能性と結果回避可能性(専門家の指摘・近隣からの苦情・目視での破損の明白性)
- 講じた具体的措置(仮囲い・防護ネット・防護棚・立入禁止措置・警告掲示の内容と設置場所)
- 点検・巡回の頻度と記録(写真・日誌・業者報告書)
- 台風・大雪・地震など外力の規模と「不可抗力」性(想定可能な範囲の備えを超えるか)
- 是正勧告・苦情受領後の対応速度(初動の遅延は過失を基礎付けやすい)
損害項目と請求の流れ
人身では治療費・通院交通費・休業損害・後遺障害に伴う逸失利益・慰謝料、物損では修理・再取得費、臨時の仮住まい・代替施設費、事業者では営業損害・信用毀損対応費などが対象となり得ます。被害者は領収書・見積・売上資料等で損害額を立証するのが原則です。
一般的な流れは、事故発生・応急措置→事実関係と損害の記録化→相手方・保険会社への通知→示談交渉(必要に応じ専門家関与)→合意・支払、合意不成立の場合は調停・訴訟や仮処分申立て、となります。なお、損害賠償請求には消滅時効があるため、双方とも速やかな記録化と連絡が重要です。
差止・仮処分(是正の強制)
悪臭・粉じん・危険外壁などの継続的侵害が「受忍限度」を超えると判断される場合、被害者側は差止請求や仮処分により、危険箇所の撤去・仮囲いの設置・脱臭や清掃等の具体的な是正措置を求めることがあり得ます。是正命令に近い仮処分が出ると、短期間での対応が必要となり、結果的に費用負担が増えることもあります。
賃貸物件の所有者と入居者の責任分担
賃貸物件では、所有者(賃貸人)・入居者(賃借人)・管理会社・施工業者等の関与が交錯します。誰が占有者として管理していたか、契約上の修繕・管理の分担、起火原因の有無・過失の有無が賠償責任の帰属に影響します。
所有者(賃貸人)の責任範囲
建物の構造部分・外壁・屋根・塀・看板・共用部など、第三者に直接危険を及ぼし得る部分の管理は、基本的に所有者または所有者の委託を受けた管理会社の責務です。工作物責任の一次的な帰属先は管理占有者であり、相当の注意を尽くした立証ができない場合、所有者が責任を問われやすくなります。賃貸借においては、賃貸人の修繕義務(民法上の修繕義務)があるため、火災後の危険箇所の是正・養生・点検を怠ると過失が認定されやすい点に留意が必要です。
入居者(賃借人)の責任範囲
入居者が故意・過失で火災を発生させた場合には不法行為責任を負い得ます。一方、過失が認められない失火については、通常は賠償義務を負いません。火災後に解体せず保有するケースでも、入居者の残置物からの悪臭・害虫発生、窓ガラスの落下等、入居者の管理すべき範囲で危険・迷惑が生じたときは過失が問われ得ます。契約条項(特約)で入居者の負担範囲が拡張されていることもあるため、賃貸借契約書の確認が重要です。
管理会社・施工業者等の第三者の関与
管理受託者がべき措置(巡回・掲示・仮囲い・緊急補修)を怠った場合や、業者が危険な足場・養生を設置して事故を誘発した場合は、管理会社・施工業者が不法行為責任を負い、所有者等と共同不法行為として連帯責任を問われることがあります。委託内容・指示系統・報告記録は重要な判断資料になります。
実務対応と保険の確認ポイント
賃貸関係者が早期に確認すべきポイントは次のとおりです。争いを長期化させないため、通知と記録化を並行して進めます。
- 通知体制:所有者・入居者・管理会社・近隣への連絡窓口を一本化し、事故・苦情の記録を残す
- 是正措置:危険部の撤去・仮囲い・落下防止ネット・警告掲示・巡回強化を直ちに実施
- 証拠保全:被害拡大防止策の実施前後を写真・動画・日誌・作業報告で残す
- 保険の適用可能性:所有者の施設所有(管理)者賠償責任保険、入居者の借家人賠償責任特約・個人賠償責任保険などの付保状況と通知期限を確認
- 交渉方針:過失相殺や損益相殺の可能性を踏まえ、計測・見積に基づく合理的な提案を準備
| 関与主体 | 主な法的根拠 | 主な注意義務・管理範囲 | 想定される保険 | 事故例 |
|---|---|---|---|---|
| 所有者(賃貸人) | 民法717条・709条/賃貸借上の修繕義務 | 構造・外装・共用部・敷地工作物の安全確保、危険表示、是正の手配 | 施設所有(管理)者賠償責任保険、火災保険(残存物片付け費用等) | 外壁タイル落下、塀の転倒、看板の落下 |
| 入居者(賃借人) | 民法709条(過失がある場合) | 室内残置物・窓・ベランダ等の管理、臭気・害虫の防止、鍵管理 | 借家人賠償責任特約、個人賠償責任保険 | 残置物由来の悪臭拡散、窓ガラス破片の落下 |
| 管理会社・受託者 | 民法709条(受託者の過失) | 巡回・苦情対応・仮囲い・掲示・緊急是正の実施と記録化 | 受託者賠償責任保険 | 仮囲い不備による通行人の負傷 |
| 施工業者(解体・補修) | 民法709条(施工上の過失) | 足場・養生・飛散防止・粉じん抑制・近隣配慮 | 請負業者賠償責任保険 | 養生不良による粉じん・落下物事故 |
火災後に解体しない場合は、「誰が・どこまで・どの程度の管理をしたか」を明確にし、危険・迷惑の未然防止と被害拡大防止措置を継続することが、賠償リスクを最小化する最重要ポイントです。
火災後に解体しない場合の管理と応急措置

火災直後に建物を解体しない判断をした場合でも、所有者・管理者には安全確保と近隣への配慮、衛生・防犯の観点から適切な「仮管理」と「応急措置」を講じる責任があります。目的は次の3点に集約されます。すなわち、倒壊や落下物などの二次災害を未然に防ぐこと、粉じんや臭気・害虫の発生を抑制すること、そして無断侵入や放火等のリスクを低減することです。
危険箇所の自己判断は転落・感電・倒壊の恐れがあるため、初動の安全確認や仮設工事は専門業者の立会い・実施を基本とし、所有者・管理者は単独で室内に立ち入らないことが重要です。
| 優先目的 | 具体的な応急措置 | 実施のポイント |
|---|---|---|
| 人命・周辺の安全確保 | 敷地の仮囲い、危険範囲の明示、落下物の一次固定 | 立入禁止の明示、仮設材は防炎品・適正強度を選定 |
| 環境・衛生対策 | 粉じん抑制の養生、すす・灰の回収、乾燥・脱臭 | HEPA対応の集じん、濡れ拭き併用、十分な乾燥 |
| 防犯・再出火防止 | 施錠・封鎖、常夜灯・センサーライト、巡回 | 見回り記録の残置、可燃物の撤去、放火対策 |
仮囲い 足場 防音シートなどの養生
外周の仮囲いと足場・養生は、落下物・飛散物の抑制、粉じん・臭気の拡散抑制、そして第三者の立入り防止を目的とします。火災で強度が低下した部材は予想外に崩落しやすく、風雨でさらに劣化が進みます。仮囲い・足場・シートは「安全性」「防炎性」「耐候性」を満たす資材を選び、適正な施工で早急に整えることが肝要です。
現地の安全確保と一次固定
はじめに、外壁の浮き・庇や看板の落下、ひび割れたサッシやガラス片、倒れかけた塀など、外周の危険源を確認します。危険性が高い部位は接近禁止とし、専門業者が支持材やベルト、仮設支保工等で一次固定します。屋根開口や開放された窓は、雨養生と侵入防止を兼ねて板材や防炎シートで暫定塞ぎを行います。
仮囲い・足場・養生シートの選定と設置のポイント
仮囲いは、第三者の侵入防止・目隠し・作業空間の確保を目的にパネル型やメッシュ型を使い分けます。足場は耐荷重と安定性を優先し、転落・落下物対策として手すり・巾木・落下防止ネットを併設します。養生シートは防炎表示のある防音・防じんタイプを外周に二重がけするなど、現場条件に応じて透湿・遮音・遮蔽のバランスを取ります。いずれの仮設も、風荷重や排水経路を考慮し、近隣の通行・採光・通風に過度の影響を与えない配置計画とすることが大切です。
| 仮設資材 | 主な目的 | 設置上の留意点 |
|---|---|---|
| 仮囲い(パネル/メッシュ) | 第三者侵入防止・目隠し・飛散抑制 | 開口部は鍵付き、視認性と防犯の両立、風抜けと安定化ウェイト |
| 足場(手すり・巾木付) | 高所安全・作業床の確保 | 不陸地盤の安定化、荷重分散、通路幅の確保、墜落防止 |
| 防音・防じん・防炎シート | 騒音・粉じん拡散の抑制、遮蔽 | 防炎表示品、二重養生、隙間封止、風対策の増しばり |
| 飛散防止ネット | 小片の飛散抑止 | ネットのたるみ防止、重ね幅・固定ピッチの適正化 |
| 雨養生(板材・防水シート) | 雨水浸入と劣化進行の抑制 | 排水勾配の確保、たまり水防止、外壁取り合いの止水 |
騒音・粉じん・臭気の抑制
解体を行わず保全する期間も、炭化物の剥落や擦過で粉じんが継続的に発生します。防音シートとあわせて、防じんシートの二重張り、出入口の簡易エアロック、散水や湿式清掃の併用により拡散を抑えます。臭気は漏洩経路(開口・割れ目)を塞ぎ、活性炭等の吸着材や脱臭機を併用して室内負圧気味の換気を行うと効果的です。
雨養生と内部保護
雨水が入るとすす・灰が再溶出して悪臭・カビ・躯体劣化を招きます。屋根や壁の開口は板金や防水テープ、防水シートで一次止水し、屋内は濡れやすい箇所の床上げ・養生、残置物の撤去で乾燥しやすい環境を確保します。排水経路の詰まりは外部流出や臭気増幅の原因となるため、樋やドレン周りの点検・清掃も合わせて行います。
臭気すす灰の清掃と害虫害獣対策
火災後の臭気源は、炭化した建材、すす・灰、浸水で発生した汚泥、濡れた断熱材や内装材に染み込んだ有機成分など多岐にわたります。清掃・除去・乾燥・脱臭を段階的に実施し、再汚染を防ぐ工程設計が不可欠です。清掃時は粉じん吸入や皮膚刺激のリスクがあるため、防じんマスク等の保護具を必ず着用し、石綿含有の可能性がある建材は自己判断で破砕・剥離しないでください。
清掃・除去の基本手順
初期段階では、乾いたすすを空中に再飛散させないよう、HEPAフィルター対応の集じん機で吸引し、続いて微湿のウエスで拭き取りを行います。浸水した部位は、汚泥を回収後に中性〜弱アルカリ性の洗浄剤で洗浄し、清水でリンスしてから十分に乾燥させます。多孔質材(畳、石膏ボード、断熱材など)は臭気源になりやすく、再使用の可否を慎重に判断します。
| 保護具・機材 | 用途 | 使用上の要点 |
|---|---|---|
| 防じんマスク(DS2等) | すす・粉じんの吸入防止 | 顔面密着の確認、フィットチェック、フィルターの適時交換 |
| 保護メガネ/ゴーグル | 目の防護 | 粉じん侵入の少ない密閉型を選定 |
| ニトリル手袋・防護服 | 皮膚の保護 | 汚染が著しい場合は使い捨て品を使用し廃棄も密閉 |
| HEPA対応集じん機 | 微細すすの回収 | フィルターの破れ・目詰まり点検、排気の二次汚染防止 |
| 除湿機・送風機 | 乾燥促進 | 短絡風を避ける配置、結露・カビの抑制 |
乾燥と脱臭のポイント
清掃後は、湿度を下げて乾燥を優先します。除湿機と送風機を併用し、閉鎖空間では室内の吸気と排気のバランスを取り、臭気の再循環を避けます。脱臭は、洗浄と乾燥で臭気負荷を減らしたうえで、活性炭・消臭剤の併用や機械的な脱臭を段階的に実施します。オゾン脱臭などの機器を用いる場合は、無人環境・適切な濃度・曝露時間の管理が不可欠であり、専門業者による施工が安全です。
カビ・細菌対策
濡れたまま放置すると、カビや細菌が増殖して健康被害や臭気再発の原因になります。吸水した内装材は早期に乾燥・交換を検討し、表面は洗浄・拭き取り後に適切な消毒剤で処理します。再汚染を防ぐため、乾燥過程での結露を避け、換気経路にフィルターを設けて粉じんの再流入を抑えます。
害虫・害獣の防除と封じ込め
残渣や汚泥、破損箇所はネズミ・ハエ・ゴキブリなどの温床になります。餌・水・巣(3要素)を断つのが基本で、残置物や腐敗物は密閉回収し、破損した床下通気口や配管まわりの隙間は防鼠材や金網で封鎖します。粘着トラップやベイト剤は人やペットへの安全に配慮して設置し、被害が顕著な場合は防除の専門家に相談します。
防犯 立入禁止掲示 見回り
焼損建物は侵入・盗難・放火のリスクが高まります。仮囲い・施錠・照明・掲示による視覚的抑止と、巡回・記録による実質的な管理を両輪で行い、近隣からの通報体制も整えます。立入禁止の掲示と連絡先の明示、夜間の照明、危険範囲の物理的封鎖は、事故防止と防犯の双方に効果があります。
立入管理・掲示の設置
仮囲いの要所に「危険・立入禁止」「関係者以外立入禁止」等の掲示を取り付け、所有者または管理者の連絡先を明示します。搬出入口はチェーン錠や南京錠で施錠し、掲示は雨・風で損耗しない材質を選び、見やすい高さに設置します。夜間は常夜灯やセンサーライトで死角を減らします。
侵入・盗難対策
窓・勝手口・シャッター等はベニヤ板や鋼板で補強し、ビス・座金で脱着困難に固定します。屋外の可燃物(段ボール・木材端材・布類)や脚立・工具は敷地から撤去または施錠保管し、仮設電源は漏電遮断器付きで施錠箱に収納します。防犯カメラやカメラ付きセンサーは見える位置に設置し、記録媒体の保全も行います。
定期点検と記録
巡回は日中と夜間の時間帯を変えて実施し、施錠・仮囲いの破損・掲示の剥離・雨養生のはがれ・異臭や煙の有無を確認します。見回り結果は日誌に時刻・天候・異常の有無・対応内容を記録し、写真も保存します。異常があれば直ちに是正し、必要に応じて警察・消防・管理会社と情報共有します。
| 巡回タイミング | 重点チェック項目 | 初期対応の例 |
|---|---|---|
| 通常(毎日〜隔日) | 施錠・仮囲い・掲示・異臭・異音 | 緩みの締め直し、掲示の交換、異常の記録 |
| 降雨・強風の前後 | 雨養生の剥離、シートのばたつき、たまり水 | シートの増し固定、排水確保、濡れた残渣の回収 |
| 地震後 | ひび・傾き・落下物・足場の緩み | 危険範囲の拡張、専門業者による再点検の手配 |
| 臭気・害虫の苦情時 | 臭気漏洩経路、残置物、排水の停滞 | 封止の追加、清掃・回収、脱臭・乾燥の強化 |
悪天候時の対応
台風や前線通過が予想される際は、シート・ネットの緩みや破断箇所を事前に補修し、飛散しやすい資材・廃材は屋内保管または確実に固定します。排水経路を確認し、たまり水・漏水を発見した場合は速やかに排水・乾燥を実施します。強風時の高所作業は避け、視界不良・濡れた足場では無理な立入りを行わないでください。
これらの応急措置は「安全最優先・再汚染の回避・記録の徹底」を軸に、専門家の助言を得ながら段階的に実施することで、二次被害の抑制と近隣環境への影響最小化につながります。
解体ではなく修繕で再使用するための条件

「火事で建物が被災しても、解体しないで修繕・再使用できるか」は、構造安全性、衛生・環境面、ライフラインの安全、そして法令適合の4点を満たせるかで決まります。再使用を急ぐと重大事故や民事責任につながるため、建築士の調査を起点に、復旧計画と手続を段階的に進めることが重要です。
特に、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)や防火区画、避難経路、電気・ガス・水道設備に火熱や消火水の影響が及んでいる場合は、専門家の診断と工事が不可欠です。次項から、再使用の可否判断と実務のポイントを詳しく解説します。
建築士による構造安全性の調査
再使用の前提は「安全に立ち入れるか」「居住・使用に耐えるか」の二段階の安全性確認です。まず一級・二級・木造建築士(案件により構造設計一級建築士)の現地調査を実施し、被災状況を可視化した調査報告書と復旧方針案を作成します。調査では、炭化・変形・ひび割れ・含水・腐朽・シロアリ被害の有無と、耐力伝達系の連続性を重視します。
| 構造種別 | 主な確認項目 | 修繕・再使用の判断の目安 |
|---|---|---|
| 木造 | 柱・梁・筋かいの炭化や割れ、梁端部の焦げ・座屈、構造用合板の焦損、土台・基礎の含水と劣化、釘・ボルトの緩み、屋根垂木の損傷 | 耐力壁・柱・梁など主要構造部の健全性が保てる範囲で部材交換・補強が可能なら修繕可。構造骨組の広範損傷や座屈がある場合は要補強計画または建替検討。 |
| 鉄骨造(S造) | 梁・柱の変形・座屈、溶接部やボルト接合部の損傷、耐火被覆の剥離、塗装の焼失、床デッキのたわみ | 耐火被覆の復旧で所要耐火性能を確保でき、かつ断面性能の低下が軽微なら修繕可。フランジの座屈や大きな塑性変形が確認される場合は部材交換や補強設計が前提。 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | コンクリートの爆裂・はく落、ひび割れ、鉄筋露出・腐食、スラブのたわみ、かぶり不足化、柱頭・柱脚の損傷 | コンクリートの健全性回復(断面修復・防錆等)で耐力確保が見込めれば修繕可。爆裂が広範囲・柱梁接合部損傷が顕著な場合は詳細解析と補強を要し、場合により建替検討。 |
| 共通 | 基礎の沈下・不同沈下、屋根・外壁の防水欠損、開口部の歪み、避難経路の安全、臭気・スス・カビの拡散 | 構造の連続性・防水・防火・避難性能が復旧できる計画であれば再使用可。衛生上の障害(カビ・悪臭)が強い時は除去・乾燥・脱臭の工程を確保。 |
調査手順と記録のポイント
現地踏査では、写真・採寸・含水率・表面硬度などの記録を行い、必要に応じて非破壊検査や一部開口調査を併用します。調査結果は「被災状況図」「是正内容一覧」「工程表」「概算見積」に整理し、所有者の意思決定と保険会社・施工者・確認検査機関との共有に用います。
復旧設計は「元と同程度」ではなく、現行の法令適合と安全性の観点から同等以上を基本とし、耐震・防火・避難・防水・防腐防蟻など横断的に見直すことが重要です。
衛生・環境面の適合(臭気・スス・カビ)
火災由来の強い臭気やススは、表面清掃だけでは残留しやすく、下地材(石こうボード・断熱材・床下地)やダクト内部に蓄積することがあります。解体せずに再使用する場合でも、被災範囲の撤去・洗浄・乾燥・脱臭・防カビ処理を計画的に実施し、室内空気質の回復を確認します。消火水の浸入部は、含水状況の測定と十分な乾燥期間の確保が不可欠です。
電気 ガス 水道の再開条件
ライフラインは「安全確認」と「事業者の復旧手続」が揃って初めて再開できます。被災建物での再送電・開栓・開栓(水道)は、原則として設備の点検・修理・試験を経ないと行われません。次の観点を満たしてから各事業者に再開申請を行います。
| 区分 | 所有者側の主な確認・修理 | 再開に必要な手続 | 主な担当・根拠 |
|---|---|---|---|
| 電気 | 分電盤・配線・コンセントの焼損有無、絶縁抵抗の測定、漏電遮断器の作動確認、機器の交換 | 電気工事士による点検・修理後、送配電事業者へ再送電依頼 | 電気工事士、東京電力パワーグリッド等の送配電事業者 |
| 都市ガス | ガス栓・配管・給湯器・接続具の損傷確認、機器交換、気密試験 | ガス事業者の開栓作業(安全点検)を予約、必要に応じて指定工事店で修理 | 東京ガス等のガス事業者、指定工事店 |
| LPガス | 容器バルブ周り・調整器・屋内配管の点検、機器交換、気密試験 | LPガス販売事業者の供給再開時安全点検を実施 | LPガス販売事業者(保安機関) |
| 水道 | 給水装置・給排水管の漏水確認、圧力試験、貯湯・貯水タンクの衛生確認、トラップ・通気の機能確認 | 指定給水装置工事事業者による点検・修理、所管水道局に開栓申請 | 東京都水道局等、指定給水装置工事事業者 |
住宅用火災警報器・防災設備の復旧
居住部分には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災や消火水で感知器が作動・汚損した場合は、必ず新品に交換し、作動確認を行います。共同住宅や用途によっては、非常用照明・誘導灯・排煙設備・消火器などの設備も所要性能で復旧し、必要に応じて点検・報告を実施します。
消火水による二次被害の抑制
床下・壁内に浸入した水分は、カビ・腐朽・悪臭の原因となり、電気配線や断熱材の性能低下も招きます。解体せずに修繕する場合でも、部位ごとの乾燥・除去・防腐防蟻処理を徹底し、含水率の再測定で基準内に戻したことを確認します。
確認申請が必要となる工事の線引き
修繕で再使用する場合でも、工事の内容によっては建築基準法に基づく「建築確認申請」が必要です。特に、主要構造部に及ぶ工事や防火・避難・内装制限に関わる復旧は、事前に所管行政(建築主事)または指定確認検査機関へ相談し、要否を判定します。
| 工事項目 | 該当しやすいケース | 確認申請の要否の目安 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 大規模の修繕 | 主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の一種以上で過半にわたる修繕・取替 | 確認申請が必要となる場合がある | 建築基準法および施行令の定義に該当するかを建築士が判定し、事前協議を行う |
| 大規模の模様替 | 主要構造部の一種以上で過半にわたる模様替(耐力壁の位置変更、梁成変更など) | 確認申請が必要となる場合がある | 構造耐力・防火・避難性能に影響する変更は計算・図書の提出が前提 |
| 用途変更 | 住宅から店舗・倉庫などへ用途を変更し、一定規模以上の面積に及ぶ | 確認申請が必要となる場合がある | 内装制限・排煙・非常用設備・採光換気など、用途基準の適合が必要 |
| 防火・準防火地域の復旧 | 防火地域・準防火地域内の外壁・開口部・軒裏等の復旧 | 仕様により確認申請や仕様基準の適合確認が必要 | 防火設備(防火戸等)や外壁材は認定品等で同等以上に復旧 |
| 建築設備の復旧 | 排煙・換気・非常用照明・誘導灯などの更新 | 規模・用途により申請や届出が必要な場合がある | 性能確保と定期報告の対象有無を確認 |
| 内装の仕上げ更新 | 居室の天井・壁の仕上げ更新のみ | 通常は申請不要(構造・防火性能に影響しない範囲) | 内装制限がある用途部分は不燃・準不燃等の基準に適合 |
防火・避難性能を損なわない復旧
火災で損傷した防火区画、竪穴区画、貫通部のシーリング、区画貫通配管の防火措置は、性能同等以上での復旧が必須です。避難経路・有効幅員・段差・手すり・非常用照明・誘導表示も併せて点検し、使用再開後の安全を確保します。
事前協議と工程管理
確認申請が必要となる可能性がある場合は、計画段階で所管行政や指定確認検査機関に事前協議を行い、図面・仕様・工程の整合を図ります。申請が不要な軽微な修繕であっても、近隣への安全配慮・仮設計画・粉じん・騒音対策を明確にし、工程表に反映させます。
結論として、解体せずに修繕で再使用するには、建築士の構造・衛生診断と、ライフラインの安全復旧、そして工事内容に応じた法令適合(必要に応じた確認申請)が揃うことが条件です。上記を満たしたうえで、写真・試験記録・点検票など客観的資料を整備し、関係者と共有することで、安全かつスムーズな再使用が実現します。
解体費用の相場 2025年版

2025年時点での建物解体費は、構造・規模・立地条件・分別の手間・運搬距離などで大きく変動します。本章では、全国的な相場感と東京都内(特に23区)の目安、さらに火災後の現場に特有の追加費用やアスベスト関連費、残置物処分費までを体系的に整理します。金額はいずれも目安であり、現場調査後の見積書で確定することに留意してください。
火災後の解体は、すす・臭気・消火水や汚泥への対処、仮囲いの強化などが必要となるため、同規模の一般解体と比べて総額が上振れしやすい点が特徴です。
構造別の坪単価 木造・鉄骨造・RC造
以下は戸建てや小規模建築物を想定した構造別の坪単価目安です。1坪は約3.31平方メートルです。実勢は、前面道路幅員や重機の進入可否、建物の高さ、付帯物の有無(ブロック塀・土間コンクリート・カーポート・庭木等)により増減します。
| 構造 | 全国平均の坪単価目安(円/坪) | 東京都23区の坪単価目安(円/坪) | 30坪解体の概算(全国平均) |
|---|---|---|---|
| 木造(在来・2階建て想定) | 350,000〜550,000 | 450,000〜700,000 | 10,500,000〜16,500,000 |
| 鉄骨造(軽量鉄骨含む) | 450,000〜700,000 | 550,000〜850,000 | 13,500,000〜21,000,000 |
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 650,000〜1,000,000 | 800,000〜1,200,000 | 19,500,000〜30,000,000 |
上記は更地渡しまでの本体工事費ベースの目安です。一般に見積書には、仮設工事(養生足場・飛散防止シート)・重機回送・分別解体・積込運搬・処分費・現場管理費などが含まれますが、付帯工事や特殊条件は別途計上されることが多く、総額の差に直結します。
| 現場条件・付帯工事 | 追加費用の目安 | コメント |
|---|---|---|
| 前面道路が狭い(約2.5m未満)・重機進入不可 | 本体費の10〜30%増 | 手壊し・小運搬・小型ダンプ多回転で人工と時間が増加 |
| ブロック塀・土間コンクリート・カーポート | 50,000〜300,000 | 面積・厚み・鉄筋量で変動(独立基礎の有無も確認) |
| 庭木・庭石・物置撤去 | 30,000〜200,000 | 樹種・太さ・根鉢の大きさ・重量物の有無で変動 |
| 地中障害物(基礎杭・浄化槽・井戸・ガラ) | 50,000〜500,000 | 試掘で確定。撤去範囲と処分量に依存 |
| 騒音・粉じん対策強化(防音パネル等) | 30,000〜150,000 | 住宅密集地や学校・病院隣接で必要になる場合あり |
同じ坪数でも、道路条件・付帯物・分別の手間により見積総額が大きく動くため、現地調査に基づく内訳明細のある見積書で比較検討することが重要です。
火災特有の追加費用 すす・臭気・消火水・汚泥
火災後の現場では、煤(すす)や焼け焦げ材の分別強化、臭気対策、消火水や汚泥の回収・処理、仮囲いの増強、再出火防止の見回り等が必要となることが多く、一般解体に上乗せの費用が発生します。
| 追加作業 | 目安費用 | 主な理由・注意点 |
|---|---|---|
| すす・焼け焦げ材の分別強化 | 50,000〜200,000 | 臭気の強い可燃物を袋詰め・密閉し混合廃棄を抑制 |
| 臭気対策(消臭剤散布・散水・活性炭) | 50,000〜300,000 | 近隣苦情対策。作業前後の散布や資材更新が必要 |
| 消火水・汚泥の吸引回収・処理 | 50,000〜250,000 | 含水率上昇により重量増→運搬処分費が増える傾向 |
| 仮囲い・防炎メッシュシート増強 | 50,000〜150,000 | 煤の飛散抑制。養生範囲・期間で変動 |
| 再出火防止の見回り・養生延長 | 30,000〜100,000 | 調査完了までの待機・立入調整に伴う日数増加 |
上記の追加対応が入ると、トータルでは一般的な解体に比べておおむね10〜30%高くなる傾向があります。り災証明書や火災保険の「残存物片付け費用」等で一部カバーできる場合があるため、見積書の内訳と保険適用範囲を必ず照合してください。
アスベスト調査 除去費用の目安
大気汚染防止法の改正により、規模の大小にかかわらず解体工事では事前のアスベスト調査が義務化されています(東京都内でも同様の運用)。調査で石綿含有建材が無ければ除去費は発生しませんが、調査・分析・結果掲示は必要です。
| 区分 | 内容 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事前調査(書面・現地目視) | 図面・仕様確認、現地確認、報告書作成 | 30,000〜80,000 | 戸建て規模の一般的な範囲 |
| 分析(材料採取・試験) | サンプル採取と分析 | 1試料あたり 15,000〜30,000 | 採取点数に応じて増加(数点〜十数点) |
| 除去工事(レベル3:成形板等) | 隔離養生・集じん・分別梱包・適正処理 | 200,000〜1,200,000 | 面積・数量・階層で変動。戸建てで発生しやすい |
| 除去工事(レベル2:保温材等) | 同上(必要に応じ負圧養生等) | 500,000〜2,000,000 | 対象は限定的だが規模次第で高額 |
| 除去工事(レベル1:吹付け材等) | 厳格な養生・測定・適正処理 | 1,500,000〜4,000,000 | 戸建てでは稀。対象なら専門業者必須 |
調査結果の届出・掲示、作業基準遵守、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行など、事務費や法定費用が別途数万円単位で計上される場合があります。火災後は石膏ボードや内装材が破損・含水していることが多く、採取点数が増えがちなため、見積時に「調査の範囲と点数の想定」を確認しておくと安心です。
残置物処分 運搬処分費の相場
解体前の家財や建物内残置物の量は、総額に大きく影響します。一般廃棄物・産業廃棄物・リサイクル対象品目の区分に従い、分別・運搬・処分を行う必要があります。家電リサイクル法対象品(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)は指定のリサイクル料金と収集運搬費が別途発生します。
| 区分 | 目安費用 | 量の目安・備考 |
|---|---|---|
| 1tトラック積込・運搬・処分 | 30,000〜60,000/台 | 単身分の家財一部程度。小口の撤去向き |
| 2tトラック積込・運搬・処分 | 50,000〜90,000/台 | 1K〜1LDK相当の家財量の目安 |
| 4tトラック積込・運搬・処分 | 100,000〜180,000/台 | 戸建て1軒分に対応することが多い |
| 重量物(ピアノ・金庫等) | 別途見積(数万円〜) | 人員増・特殊機材・階段養生が必要 |
| 混合物の手選別・袋詰め強化 | 30,000〜150,000 | 火災現場では臭気対策を兼ね追加になりやすい |
「積み放題」をうたう格安サービスは、分別不十分やマニフェスト未交付など適正処理に不安が残る場合があります。見積書には、分別方針・運搬車両・処分先・マニフェスト発行の有無を明記してもらい、解体本体と併せて比較しましょう。
参考として、全国平均ベースの概算シミュレーションを示します(条件により大きく変動します)。
| 想定ケース | 基本解体費 | 火災特有の追加 | アスベスト(調査/除去) | 残置物処分 | 概算合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木造30坪・半焼・アスベスト無し | 10,500,000〜16,500,000 | 150,000〜450,000 | 調査・分析 70,000〜170,000 | 150,000〜300,000 | 14,200,000〜25,700,000 |
| 鉄骨造40坪・全焼に近い・アスベスト無し | 18,000,000〜28,000,000 | 200,000〜500,000 | 調査・分析 70,000〜170,000 | 200,000〜400,000 | 22,700,000〜32,100,000 |
| RC造50坪・局所的にレベル3除去あり | 32,500,000〜50,000,000 | 300,000〜700,000 | 調査・分析 80,000〜200,000+除去 500,000〜1,500,000 | 300,000〜600,000 | 44,300,000〜80,000,000 |
最終的な契約前に、3社以上の現地調査と内訳明細付きの相見積で「含まれる・含まれない」項目と追加発生条件を必ずすり合わせることが、火災後の解体費を適正化する最短ルートです。
必要な届出 手続きのチェックリスト
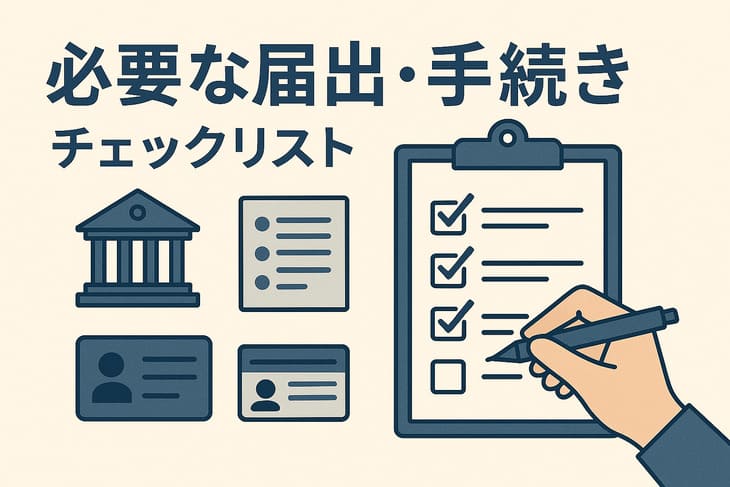
火災後に解体する・しないにかかわらず、手続きの抜け漏れは補償・減免・工事段取りに直結します。特に「り災証明書」「建設リサイクル法の届出」「大気汚染防止法(石綿)」「産業廃棄物マニフェスト」は相互に関係し、提出順序や期限が法律・条例で定められています。誰が・どこへ・いつまでに・何を出すのかを冒頭で確定し、写真や図面の準備、現場の保存を優先しましょう。
まず全体像として、以下の早見表で必要な届出・申請を俯瞰してください。
| 手続名 | 必要になる場面 | 主な申請先 | 期限・タイミング | 主な添付書類・ポイント |
|---|---|---|---|---|
| り災証明書の取得 | 保険請求・税の減免・各種支援の申請に必須 | 市区町村(被災建物の所在地の窓口) | できるだけ早期(現地確認前の片付けは控える) | 申請書、本人確認書類、被災写真、位置図 等。名称は自治体で「罹災証明書」等と表記ゆれあり |
| 建設リサイクル法の届出 | 解体工事(延べ床80㎡以上)等の着手前 | 都道府県知事等(実務は市区町村・特別区の担当課) | 工事着手の7日前まで | 届出書、分別解体計画、配置図・平面図、現況写真、工程表、委任状 等。発注者が届出義務者 |
| 大気汚染防止法(石綿)事前調査・届出 | 解体・改修・内装撤去等の着手前 | 都道府県・政令市・特別区(環境部局) | 事前調査は着工前、必要な場合は事前報告・除去作業の14日前届出 | 有資格者の調査報告書、図面・写真。石綿含有時は隔離・負圧養生等の計画書 |
| 産業廃棄物マニフェスト | 建設系廃棄物の運搬・処分委託時 | 排出事業者(元請)から許可業者へ交付 | 排出毎に交付、完了確認まで継続管理 | 委託契約書、許可証写し、(電子)マニフェスト。帳票・データの保存義務あり |
| (関連)道路使用・占用許可 | 足場・仮囲い・搬出入で歩道や車道を使う場合 | 所轄警察署(道路使用)・道路管理者(占用) | 着手前 | 平面図、交通誘導計画、期間・時間帯。標識・誘導員の配置計画 |
| (関連)ライフラインの停止・再開 | 安全確保・工事前後の切替 | 電気・ガス・水道の各事業者 | 工事・調査日程に合わせ事前調整 | 閉開栓・計器撤去の申込。ガスは復旧時の安全点検が必須 |
届出の責任主体は「発注者」か「元請業者」かで異なります。役割分担を契約書に明記し、電子申請のアカウント(代理申請の委任状を含む)も早期に準備すると滞りません。
り災証明書の取得と活用
対象と発行主体
「り災証明書」(多くの自治体では「罹災証明書」)は、火災等で建物・家財に被害が生じた事実と被害の程度を公的に証明する書面です。発行主体は、被災建物の所在地を所管する市区町村です。火災の場合、消防署の調査結果を基に市区町村が判定・発行するのが一般的です(名称や様式は自治体により異なります)。
申請先・期限・方法
申請先は市区町村の窓口(防災担当・税務担当等)で、原則として被災現場の所在地の自治体に申請します。申請期限は自治体ごとに定めがありますが、原則として早めの申請が推奨されます。窓口・郵送のほか、一部自治体ではオンライン申請に対応しています。
現地調査前の大規模な片付けは、被害認定に支障となるため避け、先に全景・各室・外構・家財の被害を時系列が分かる形で撮影し保存してください。
必要書類の例
申請書、本人確認書類、被災状況がわかる写真、建物の位置図・見取図、所有・占有を確認できる資料(登記事項証明書や賃貸借契約書等)、代理人申請時の委任状などが求められます。必要書類は自治体で異なるため、事前に最新の案内を確認してください。
活用できる主な場面
民間の火災保険の請求、固定資産税・都市計画税等の減免申請、各種手当・義援金の申請、公営住宅の一時入居、公共料金(上下水道・電気・ガス等)の減免申請などで活用されます。「り災証明書」が無いと手続きが進まないものが多いため、最優先で取得しましょう。
よくある不備と注意点
写真不足、所在地の特定ができない、所有関係の確認資料がない、代理申請の委任状不備などが典型です。判定区分(例:全焼・半焼・一部焼損 等)は自治体の基準で記載されます。内容に疑義がある場合は異議申立の手続が用意されていることがあります。
建設リサイクル法の届出 80平方メートル基準
対象工事と基準
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、以下の一定規模以上の工事で「分別解体等の計画等の届出」と再資源化の実施が義務付けられます。
主な対象は次のとおりです。建築物の解体工事は「延べ床面積80平方メートル以上」、建築物の新築・増築は「床面積の合計500平方メートル以上」、建築物の修繕・模様替等は「請負代金1億円以上」、工作物に関する工事は「請負代金500万円以上」が目安です。対象資材はコンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材です。
だれがいつまでに届出するか(発注者の義務)
届出義務者は原則として工事の発注者です。工事に着手する日の7日前までに、工事場所を所管する都道府県知事等(実務は市区町村・特別区の担当課)へ提出します。代理で元請業者が提出する場合は、発注者からの委任状を添付します。
提出書類と添付図書
分別解体等の計画書、工事概要書、工程表、現場案内図・配置図・平面図、現況写真、契約書(写)、委任状(代理申請時)などを整えます。提出図書は石綿事前調査報告や産業廃棄物の計画とも整合させ、後日の変更届が最小で済むように段取りしましょう。
工事現場での掲示・分別解体の実務
現場には工事概要や連絡先等の標識を掲示し、木材、コンクリート、アスファルト、金属等を分別して搬出します。再資源化が困難な場合(安全上・近隣環境上の支障など)は要件に沿った例外取扱いがあり、記録の保存が必要です。
注意点(未届・設計変更時の再届出など)
未届のまま着工すると行政指導や工事停止等の対象となり得ます。規模・工法・工期の重要な変更が生じた場合は、速やかに変更届で内容を更新してください。解体工事業者の許可・登録の有無、収集運搬・処分業者の許可確認も同時に行いましょう。
大気汚染防止法の石綿事前調査と届出
調査の義務と有資格者
すべての建築物の解体工事や、多くの改修・内装撤去工事では、着工前に「石綿(アスベスト)含有建材の有無」を調査する義務があります。調査は、所定の講習等を修了した有資格者(例:建築物石綿含有建材調査者 等)が実施するのが原則です。図面確認・現地目視・必要に応じた分析を踏まえ、調査結果報告書を作成します。
調査結果の報告(届出)の対象・期限
調査結果は、所管(都道府県・政令市・特別区)への報告が必要となる工事があり、解体工事は原則として着工前の報告が求められます。報告方法は電子システム等が用意され、元請業者が主体となって行うのが一般的です。「解体しないで一部修繕のみ」の場合でも、改修工事に該当すれば調査・報告が必要になることがあります。
石綿が見つかった場合の追加届出と作業基準
石綿含有建材が存在し、除去・封じ込め・囲い込み等の「特定粉じん排出等作業」を行うときは、着手の14日前までに所管へ届出が必要です。作業は隔離・負圧養生・湿潤化・集じん・廃棄物の二重袋詰め等の基準に従い、標識の掲示や作業区域の明確化、周辺の飛散防止対策を徹底します。石綿廃棄物は特別管理産業廃棄物として適正に容器梱包・表示し、許可業者に委託します。
併せて必要になり得る労働安全衛生法の手続
石綿等の除去等の作業では、労働安全衛生法令に基づき作業計画の作成・周知、作業主任者の選任、保護具の着用、特別教育等が求められます。必要な届出や記録の整備については、所轄の労働基準監督署の指導に従ってください。
近隣周知と掲示
石綿関連工事では、近隣住民への事前周知、現場掲示(工事内容・期間・連絡先・石綿有無等)が重要です。説明の不十分さは苦情・工事停止リスクにつながるため、配布資料や掲示物の内容・タイミングを現場計画に組み込んでおきましょう。
産業廃棄物マニフェストと適正処理
排出事業者の範囲と委託契約
解体・改修に伴う建設系廃棄物の排出事業者は、原則として工事の元請業者です。収集運搬・中間処理・最終処分は、それぞれの許可を有する業者に委託し、委託契約書で品目・数量・処理方法・料金・引渡条件等を明確にします。家屋所有者が直接産廃を処理業者に渡す運用は原則想定されていないため、元請経由で適正に管理しましょう。
マニフェストの種類と運用(電子・紙)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は電子(システム)または紙で交付します。交付番号の管理、運搬・処分各段階の受領確認、未着・遅延時の原因照会、最終処分までの完了確認を行い、関連帳票・データを法定期間保存します。電子マニフェストはリアルタイムに進捗が把握でき、誤記・返送漏れの防止に有効です。
許可の確認と保管義務
収集運搬業・処分業の許可証(品目・区域・有効期限)を確認し写しを保管します。工事写真(分別状況・積込・飛散防止)、計量票、処分証明書、再資源化報告等を体系的に保存し、建設リサイクル法の再資源化実績と整合させます。
火災特有の廃棄物の区分と前処理(臭気・すす・汚泥)
焼損材・煤(すす)・臭気付着物、消火活動で発生した含水廃材・汚泥は、飛散・流出・臭気対策(養生、密閉容器、脱臭資材の併用)が必要です。石綿含有の可能性がある吹付材・保温材・成形板等は分別・密封・表示を徹底し、特別管理産業廃棄物として扱います。生活ごみ・家財道具は原則「一般廃棄物」となり、市区町村の取扱いに従います(火災で性状が変化したものの扱いは自治体判断が分かれるため事前確認が必要)。
関連法令のチェック(フロン・PCB・家電リサイクル・一般廃棄物)
業務用エアコン等はフロン排出抑制法に基づく回収・証明書の取得、古い安定器・トランス等はPCB特別措置法に基づく確認・適正処理、家電リサイクル法対象機器の適正ルートでの処理が必要です。これらはマニフェストと併せて手続・証憑を整え、監査・行政確認に耐える記録管理を行ってください。
「届出→掲示→分別→運搬→処分→記録保存」という一連の流れを、元請・発注者・専門業者で共有し、工程表に落とし込むことが、事故・苦情・行政指導の回避につながります。
補助金 保険の活用法

火災後に「解体しない」方針を選ぶ場合でも、保険金の請求や自治体補助の活用次第で経済的負担を大きく抑えられます。ここでは、火災保険の主な支払い項目(特に残存物片付け費用)と、自治体の解体・空家対策系補助金を、申請の勘所と注意点まで含めて整理します。
保険・補助ともに名称や要件、対象経費は契約・自治体ごとに異なるため、約款・募集文書・実施要綱の原文確認と事前相談が必須です。
火災保険の支払い項目 残存物片付け費用
加入している契約(建物・家財・店舗総合など)と特約の有無により、請求できる項目は変わります。以下は多くの保険で採用される代表的な区分です(名称は保険会社により異なります)。
| 支払い項目 | 概要・主な対象費用 | 主な必要書類 | 注意点・よくある誤解 |
|---|---|---|---|
| 損害保険金(建物・家財) | 焼損・焦損・水損の復旧費用。部分修繕や美装清掃、すす除去、設備の交換など。 | 罹災(り災)証明書、被害写真(全景・近景・日付)、被害明細、見積書(内訳付)、請求書、約款に定める申告書類 | 原則「同等復旧」。グレードアップ・増築分は対象外になりやすい。 |
| 残存物片付け費用(残存物取片づけ費用) | 焼け残りの瓦礫・可燃物の撤去、分別、運搬、適正処分に要する費用。 | 片付け前後の写真、内訳明確な見積書・請求書、処分量の根拠(マニフェスト等)、被災状況の記録 | 解体費そのものとは別枠で支払われる場合があるが、契約により限度額や対象範囲が異なる。 工程・数量・処分単価の根拠が重要。 |
| 臨時費用保険金 | 復旧過程で生じる臨時支出に充当可能な費用保険金(詳細・割合は約款次第)。 | 損害額の確定資料、請求書類 | 用途制限や限度額あり。対象費用の重複請求は不可。 |
| 損害防止費用等 | 延焼・二次被害を防ぐための応急措置費用(養生・仮囲い・緊急清掃など)を約款が認める範囲で補填。 | 措置の必要性が分かる記録、実施写真、領収書 | 「危険除去の必要性」「相当性」の説明が求められる。 |
| 失火見舞費用保険金 | 近隣への見舞金相当を定額・上限内で補填(付帯の有無・額は契約次第)。 | 事故状況の説明資料、支払証憑 | 賠償金とは別枠の「見舞い」扱い。支払い条件は要件確認。 |
| 借家人賠償責任・類焼損害特約等 | 賃貸入居者の法的賠償責任(借家人賠償)や隣家延焼に関する補償(類焼損害)などの特約。 | 事故状況、法的責任の有無が分かる資料、相手方見積・請求資料等 | 失火責任法の考え方や特約の付帯状況により支払い可否が変動。 |
| 地震火災費用保険金 | 地震に伴う火災に関する費用保険金が付帯される場合がある(取扱いは保険会社により異なる)。 | 地震起因の立証資料、被害写真等 | 付帯の有無・支払条件は契約で大きく異なるため事前確認が必須。 |
請求の基本ステップは、事故受付→安全確保と応急処置→被害の記録化→見積・必要書類の収集→鑑定・協定→支払いです。被害箇所の原状・数量・仕様が分かる写真と、分別・運搬・処分の数量根拠が審査の要です。
「交渉のために水増しした見積」「名義貸しやマニフェスト不備」「現金割戻しの提案」などは不正受給の疑いを招くため厳禁です。 見積内訳は、撤去(人件費・機械損料)、分別、積込、運搬距離、処分単価、仮設・養生、安全対策、アスベスト関連の調査・分析・除去の有無まで明示しましょう。
解体しない場合は、残存物の撤去・清掃・消臭・害虫対策など「再使用に向けた衛生・安全確保」の費用が、損害保険金や費用保険金の対象となり得ます。どこまでが修繕、どこからが解体に該当するかは工事内容・数量で判断されるため、建築士や保険鑑定人と整合を取って工程を決めると審査が円滑です。
対象外になりやすい例として、経年劣化や虫食い・腐朽の補修、契約上の除外危険、被保険者の故意・重大な過失による損害、約款の定めを超えるグレードアップ工事などが挙げられます。疑義がある場合は約款条項と照合しましょう。
保険金と自治体補助は同一費用の重複受給ができません。保険で支払われた分は補助額算定から控除されるのが一般的です。
自治体の解体補助と空家対策補助
多くの自治体で、老朽・焼損により危険性が高い住宅・空き家の除却(解体)や、空家等対策に関する補助制度が整備されています。制度の名称・対象・上限額・募集時期は自治体ごとに異なるため、実施要綱の確認と事前相談が重要です。
| 制度類型 | 主な対象 | 補助対象経費の例 | 申請のタイミング | 留意点 |
|---|---|---|---|---|
| 空家等除却(解体)補助 | 倒壊等の恐れがある空き家、焼損で危険性が高い住宅等 | 解体工事費、分別・運搬・処分費、仮設足場・養生、安全対策、アスベスト事前調査・分析・除去に係る費用(自治体の要綱次第) | 交付決定後に契約・着工 | 交付決定前の契約・着工分は対象外が原則。 所有権・相続関係の整理、近隣説明が求められる。 |
| 空き家活用・改修支援 | 空き家の利活用につながる改修(火災後の再生を含む場合あり) | 利活用に資する改修費の一部(対象範囲は要綱次第) | 事前申請→交付決定→着工 | 単なる原状回復・災害復旧のみは対象外となる場合がある。 |
| 専門家派遣・調査支援 | 危険度診断、活用可能性調査、アスベスト事前調査等 | 調査・診断費用、報告書作成費 | 工事前 | 調査結果の提出が補助要件や工事仕様の根拠になる。 |
申請の基本フローは、事前相談(制度適合性の確認)→現地確認・写真撮影→交付申請(見積書・図面・位置図・所有者確認書類等を添付)→審査→交付決定→契約・着工→完了→実績報告→支払いです。年度予算により募集枠が限られるため、早めの相談が安全です。
提出書類の例として、申請書、罹災(り災)証明書、現況写真、工事見積書(内訳明細)、公図・案内図、所有者を示す登記事項証明書、相続関係の分かる書面、委任状、工事工程表、誓約書、反社会的勢力でないことの誓約、市税の納付状況が分かる証明などが挙げられます(自治体の要綱に従います)。
保険金と補助金は併用可でも「同一費用の二重取り」は不可です。 一般に、保険金で充当された金額は補助対象経費から控除されるため、保険金の支払確定後に補助額が精算される運用が多いです。申請時点で、保険の請求状況・見込みを明記しておくと手戻りを防げます。
不採択・減額の主な理由には、対象外工事(外構のみ等)、交付決定前の着工、書類不備、所有権・相続未整理、危険度要件未達、予算上限到達などがあります。工程写真・処分量の根拠、アスベスト調査結果の整合性が審査の肝になります。
「解体しない」場合に使える補助は限定的ですが、危険度の高い部分の除却のみを対象にする制度や、空き家の活用改修系の支援が適用されるケースもあります。修繕で再使用を目指す場合は、制度の適用可否が分かれるため、工事範囲と安全性の根拠(建築士の調査報告等)を持って相談すると判断が早まります。
補助制度は年度途中で予算消化により終了することがあるため、保険の査定と並行して早期に制度要綱を確認し、交付決定前着工を避ける工程設計が重要です。
東京都内の相談窓口

火災後に「解体しない」選択を検討する場合でも、現地の安全確保、法令順守、近隣対応、保険金の適切な請求には、公的機関と専門家の並行相談が不可欠です。まずは安全と手続の優先順位を明確にし、東京都内の所管窓口に早めに連絡することで、違反・再出火・賠償トラブル・費用増大のリスクを大きく減らせます。
以下では、東京消防庁、各区役所(建築指導課・空家対策担当)、および建築士・弁護士・保険代理店といった専門家に「何を相談できるのか」「事前に何を準備するとよいか」を具体的に整理します。
東京消防庁の相談窓口と問い合わせ先
東京消防庁は、再出火防止と現場の安全確保、火災調査、火災事実に関する証明に関する案内など、火災直後の初動段階で中心的な役割を担います。緊急時は119ですが、緊急性のない相談は最寄りの消防署(予防係等)の窓口・電話で確認します。現場への立入りや残置物の搬出は、調査・安全確認の指示に必ず従い、独自判断で作業を始めないことが重要です。
| 相談項目 | 主な担当 | 持参・伝えるとスムーズな情報 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 再出火防止・現場の安全確認 | 最寄りの消防署(予防係・担当者) | 発生場所の住所、火災発生日時、所有者・連絡先、建物の構造・規模、現場写真 | 倒壊・落下の危険があるため、立入り可否・養生の指示に従う |
| 火災に関する証明の案内 | 最寄りの消防署(窓口) | 本人確認書類、発生場所と日時、利用目的(保険・各種手続) | 発行まで日数を要する場合あり。用途を明確に伝える |
| 危険物・ガスボンベ・スプレー缶等の取扱相談 | 最寄りの消防署(危険物担当等) | 残存物の種類・数量・保管状況のメモや写真 | 不適切な保管・処分は再出火や事故の原因となる |
| り災証明書申請の流れの確認 | 最寄りの消防署(案内) | 住所・氏名、火災の概要 | り災証明書は市区町村が発行するため、最終的な申請先は区役所 |
119は救急・火災の通報専用です。緊急性のない相談は混雑時間を避け、最寄りの消防署の窓口・電話で落ち着いて伝えると円滑です。
各区の建築指導課 空家対策担当
建物の安全や法令順守、空家対策、税の取扱い、近隣環境への影響に関する相談は、原則として区役所が所管します。部署名は「建築指導課」「建築課」「住宅課」「空家対策担当」「環境衛生課」「税務課」など区により異なります。解体しない場合でも、危険除去・養生・維持管理の計画について早期に区役所へ相談すると、是正指導や特定空家等の指定、税優遇の失効といった不利益を回避しやすくなります。
| 区役所の主な窓口 | 主な相談・手続 | 持参・準備するとよいもの | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 建築指導課 | 危険な建築物の確認、是正指導、仮囲い・足場等の安全措置の相談、建築基準法に関する照会、解体・修繕の事前協議、建設リサイクル法の届出相談(規模要件該当時) | 現況写真・被災状況メモ、建物の概要(構造・階数・延床面積)、図面・確認済証の写し(あれば)、り災証明書の写し | 是正命令や行政代執行に至る前の任意協力が重要。占用・通行止めは道路管理者や警察署の手続が別途必要になる場合あり |
| 空家対策担当 | 空家等対策特別措置法に基づく助言・指導、特定空家等の可能性の相談、近隣苦情への対応支援、除却・修繕・管理の補助制度の案内 | 所有者確認資料(固定資産税の通知等)、外観写真、近隣からの苦情記録、管理計画の素案 | 放置が長期化すると「特定空家等」指定や勧告等につながるおそれ。早期相談で改善計画を共有 |
| 税務課(固定資産税) | 住宅用地特例の適用可否の確認、家屋の滅失・損壊に関する手続、評価・課税の照会 | り災証明書の写し、家屋の現況写真、家屋滅失登記(解体時)や修繕計画の概要 | 提出期限や評価替え時期に注意。用途や管理実態によって特例が失効する場合あり |
| 環境衛生・生活環境部門 | 悪臭・すす・害虫・害獣・不法投棄など生活環境被害の相談、清掃・防除に関する助言 | 被害の発生状況のメモ、写真・動画、発生頻度・時間帯 | 原因が建物内部の損壊にある場合、建築指導課との連携が必要 |
区役所内の所管が分かれるため、最初の窓口で状況を簡潔に説明し、必要に応じて担当間の連携を依頼すると手続がスムーズです。
建築士 弁護士 保険代理店への相談
行政の指導・手続と並行して、実務を担う専門家への相談体制を整えると、判断の遅れや再工事、想定外の費用発生を防げます。「構造安全性の判断=建築士」「補償・保険=保険代理店・保険会社」「賠償・契約紛争=弁護士」という役割分担を意識し、同じ資料を共有して意思決定を早めるのがコツです。
| 専門家 | 主な相談・支援内容 | 用意するとよい資料 | 成果物・確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 建築士(建築士事務所) | 構造・内外装の損傷評価、解体せず修繕する条件の整理、仮囲い・養生計画、修繕・解体の概算比較、行政協議の技術同席、復旧設計・監理 | 現地写真、図面・確認済証や検査済証(あれば)、り災証明書の写し、見積・損傷箇所メモ | 調査範囲と方法、報告書の内容(安全性評価・必要工事・費用概算)、第三者賠償保険の加入有無、工期の見通し |
| 弁護士 | 倒壊・落下物・悪臭などによる近隣トラブルや賠償請求、賃貸物件の責任分担、契約・合意書の作成、差止め・仮処分の検討、交渉・和解支援 | 被害状況の記録(写真・動画・日誌)、相手方とのやり取り、保険契約の条件、見積・契約書類 | 委任契約の範囲・費用・解決方針、時効や期限の管理、弁護士会の紛争解決手続(利用可能な場合)の活用 |
| 保険代理店・保険会社 | 火災保険の補償範囲の確認、残存物片付け費用や臨時費用の取扱い、支払手続と必要書類、修繕見積の妥当性の確認 | 保険証券、り災証明書の写し、被害写真、修繕・解体の見積、工事計画の概要 | 免責金額・支払限度・期間条件、自己負担の有無、追加書類の要請に備えた記録管理(写真・領収書等) |
専門家への相談は順序を固定せず、危険箇所の応急措置(建築士)・補償条件の確認(保険)・近隣対応の方針決定(弁護士)を並行させると、解体しない選択の可否判断が早まります。
いずれの窓口でも、所有者情報、物件の住所、被災日時・状況、写真・図面、り災証明書の写しなどの基礎資料を一式そろえておくと共通理解が早く、後日求められる追加書類にも対応しやすくなります。
まとめ

結論として、火事の後に直ちに解体しないこと自体は原則違法ではありません。ただし、倒壊の恐れや著しい衛生・防火上の支障があれば、国土交通省所管の建築基準法に基づく是正命令・行政代執行、消防法による使用制限の指導、空家等対策特別措置法の「特定空家等」指定の対象となり得ます。指定や長期放置は固定資産税の優遇喪失や近隣事故の賠償リスクにつながるため、り災証明書の取得、保険請求、近隣連絡、現場の安全確保を速やかに行いましょう。
解体せず再使用を目指す場合は、建築士による構造安全性の調査を実施し、仮囲い・足場・防音防塵シート等で養生、すす・臭気・消火水汚泥の清掃、害虫害獣と防犯対策を継続管理してください。工事内容に応じて、建設リサイクル法の届出(80平方メートル以上の解体等)、大気汚染防止法の石綿事前調査・届出、産業廃棄物マニフェストを適正に手配し、東京消防庁や各区の建築指導課、保険会社へ早期に相談することが失敗を防ぐ要点です。





